「説明文2時間目」の授業アップデート|子供の“読みたいこと”を軸に読む力を引き出す授業の技【中野裕己の授業技術アップデート14】

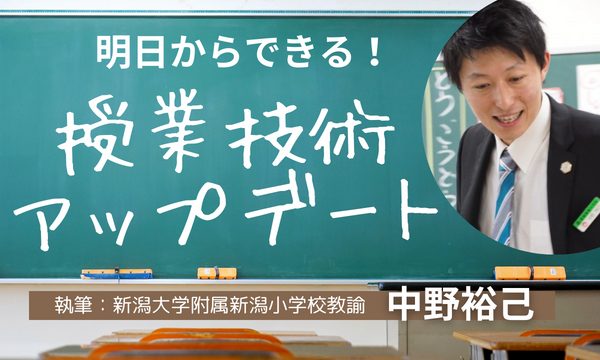
『授業はタイミングが9割』『対話型国語授業のつくりかた』の著者で、国語科、対話指導、ICT活用の研究を精力的に進める中野裕己先生による連載です。国語科の授業にとどまらず、“明日から”できて“ずっと”役に立つ授業の技を、多岐にわたってお届けします。
第14回目のテーマは、《国語(説明文)授業のアップデート》です。
執筆/新潟大学附属新潟小学校教諭・中野裕己
目次
説明文の授業がつまらなくなる原因
連載第14回目となりました。新潟大学附属新潟小学校の中野裕己(なかの・ゆうき)です。今回は、「説明文2時間目の授業」について取り上げたいと思います。
説明文といえば、物語文と比べて授業がしやすいと感じられている先生が多いのではないでしょうか。「主張」「文章構成」など、教えるべき事柄を明確にしやすいからでしょう。
一方で子供たちにとっては、物語文と比べて「つまらない」と感じることが多いようです。教師は授業しやすいのに、子供は「つまらない」…⋯これは大問題です。この原因は、一見メリットのように思われる「教えるべき事柄を明確にしやすい」ことにあります。
「教えるべき事柄を明確にしやすい」ゆえに、教師は「主張はどこ?」「文章構成はどのように分けられる?」と、教えるべき事柄を直接的に問うて授業を進めます。子供は、「主張は、最後の方にあるからこれ」「『はじめ』は主張がズバリ書いてある段落まで」などと回答していきます。このような教師の発問に回答していく子供の姿は、本当に「読んで」いるといえるのでしょうか。教科書教材のセオリーにしたがって、文章から論理を抜き出していく「作業」になってはいませんか。
説明文「想像力のスイッチを入れよう」(光村図書・国語五上)の筆者である下村健一氏は、そのような授業を指して「文章を解剖するような授業」と表現しています。「内臓はここ、骨はここ…」と体の仕組み(文章の論理)を明らかにすることに終始して、その人らしさ(文章の内容)に関心が向けられていないということです。
本来子供が関心を寄せるのは、文章の内容です。そのような子供の関心を考慮せずに、文章を解剖するような授業をしてしまえば、おもしろい授業になるわけはありません。
子供の読みはどのように創られるか
そもそも、子供の読みがどのように創られるか、私の考えを共有しておきたいと思います。前提として、真っ白なキャンバスに色をつけていくように読みが創られることはありません。つまり、子供は何らかの予備知識をもっていて、そこに文章の内容が位置づいていくということです。この予備知識には、文章の内容に関わる予備知識と、文章の論理に関わる予備知識があります。説明文「未来につなぐ工芸品」(光村図書・国語四下)を例として、整理してみましょう。
| 文章の内容に関わる予備知識 | 文章の論理に関わる予備知識 |
|---|---|
| ・「工芸品」は、昔から伝えられた物であり、おそらく壺やお椀などがある。 | ・文章の前半は「話題提示」であり、題材の解説が書かれる。 ・文章の「中」には、筆者の主張を支える理由、事例などが書かれる。 ・文章の後半は、「中」の内容を「このように」とまとめた内容が書かれる。 など… |
このような予備知識をもった子供は、まず「工芸品ってどのような物のことだろう」と考えて、文章を読み進めるでしょう。「工芸品」という内容に関わる予備知識が曖昧であるため、それを補完しようとするからです。このとき役立つのが、文章の論理に関わる予備知識です。「文章の前半は『話題提示』であり、題材の解説が書かれる」という予備知識があれば、どこを大切に読めばよいかの見当がつきます。
ここであげた子供は一例ですが、子供は多かれ少なかれ「〇〇って、どのようなもののことだろう」などと、それぞれに読みたいことをもっています。この読みたいことにしたがって、文章の論理に関わる予備知識を使いながら、読みは創られていくのです。

