謹慎・停学中の生徒をどうフォローする?<中高教員の実務>
- 連載
- 中高教員の実務
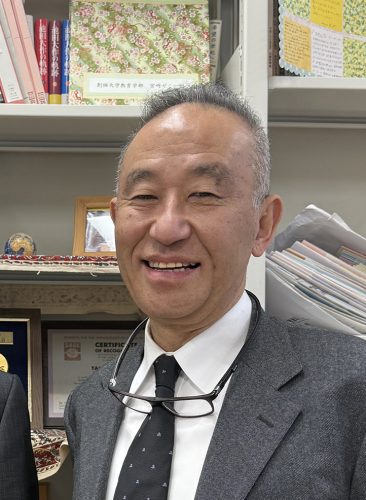

生徒が二度と問題を起こさないように、原因を責めすぎず毎日様子を確認しましょう。また、教育委員会や警察など関係諸機関と連携して相談することも大切です。
編著/小泉博明・宮崎 猛
【特集】中学校・高校教師 実務のすべて#25
うちのクラスのBくんが謹慎処分に! 初めてのケースなので、自分も戸惑うばかりで……。どう接すればいいんだろう?
謹慎や停学になった生徒は「学校や先生は冷たい」「自分はどうせダメだ」という意識をもっていることがあります。「あなたのことを心配しているよ」「自分を大切にしよう」「一緒に頑張っていこう」というメッセージを何度でも粘り強く発信していくことが重要です。
目次
二度と問題を起こさせないために
1.原因を責めすぎない
起こしてしまった問題について反省させることは必要ですが、人格を否定したり、責めすぎて逃げ場のないように話すと、生徒は自分を“ ダメな存在” ととらえ、他人を恨んだりするので、禁物です。原因を確かめ、再発防止を図ることは必要ですが、そのことで生徒を責めすぎないようにしましょう。
○「しっかり反省して、二度としないように頑張ろう!」
✕「取り返しのつかないことをしたんだぞ! もうお前のことなんか知らん!!」

2.毎日様子を確認する
謹慎や停学中は、できるだけ毎日、家庭訪問や電話をして、家庭での様子を確認します。また、学習課題を与えるなど、しっかりとした目標をもたせて生活させるようにします。なお、最近は学校に登校させたうえで別室で反省文などを書かせる「登校謹慎」の形をとるケースも増えています。
○「今日一日、どう過ごしていた? 変わりはないか?」
✕「あーあ、退屈だな~。先生も来ないんだな」

3.粘り強く接する
「悪いことをした」とその場では言うものの、再び同じようなことをくり返すなど、まったく反省していないように思えることがあります。しかし、卒業式などの場で「あのときは迷惑をかけました」「本当はわかっていました」などの言葉を聞くことが多いのも事実です。心に響く対話を粘り強く続け、生徒を思う真剣な態度と寛容さで接していくことが重要です。
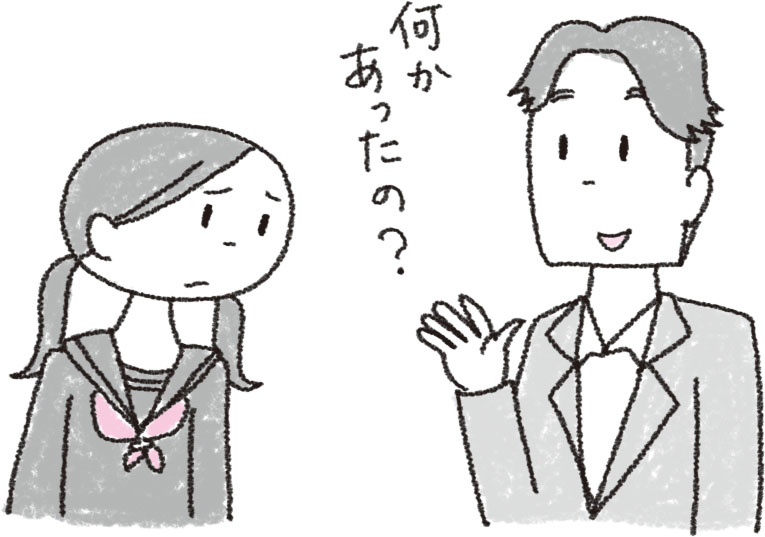
4.保護者と連携する
イラスト/タバタノリコ・畠山きょうこ

