学習意欲・活動意欲を高める 号令・指示の出し方【学ぶ意欲と力を育てる 学習指導の極意④】

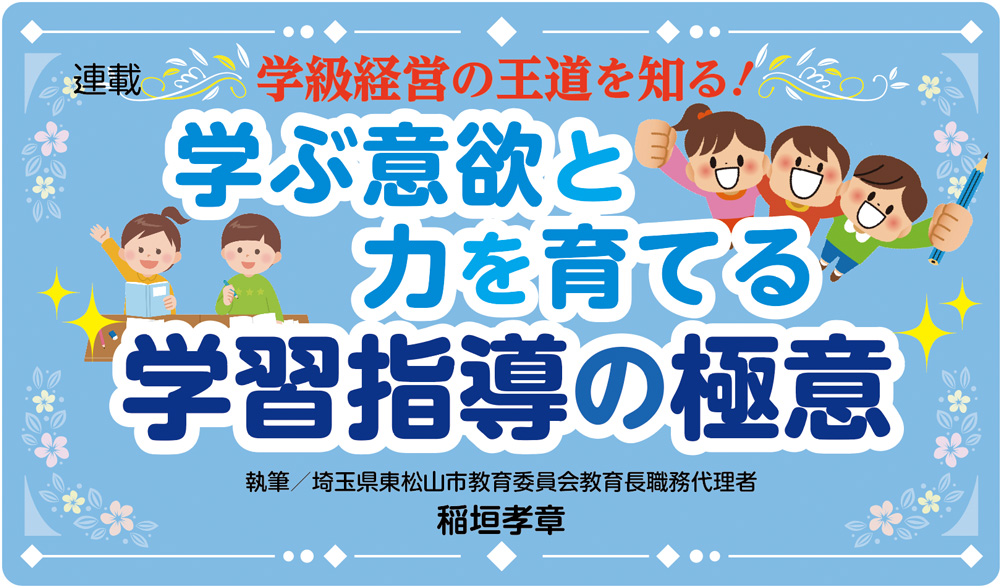
子供たちの学ぶ意欲と力を育てるためには、教師はどのような指導をしていけばよいのでしょうか。学級経営を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に学級経営の本流を踏まえて、学習指導の基礎基本を解説します。第4回は、号令と指示について解説します。
執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者
城西国際大学兼任講師
日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章
「号令や指示」は、教師の子供に対する指導の基本です。教師がどのような教育理念のもと、どのように子供に声をかけるかということは、学級経営の大切な視点の1つです。号令のかけ方、指示の出し方等について改めて確認し、学校として共通理解を図ると系統的な指導がしやすくなります。そこで、子供に指導するにあたって次の3つのキーワード「適切な号令のかけ方」「明確な指示の出し方」「実践上の配慮点」でチェックしてみましょう。
目次
CHECK① 適切な号令のかけ方
集団で生活する学校生活では、様々な場面で号令をかけることがあります。例えば、授業の開始終了の号令、体育の授業などで集団としての号令をかけることがあります。
基本的なこととして、集団行動では「前へ、ならえ」と言うとき、「前へ」と「ならえ」には、間をとります。それは、「前へ」は「予令」で、「ならえ」は「動令」であるため、心の準備をする間にするということです。今一度、号令の意義や号令のかけ方について再確認していきましょう。
授業の開始・終了は教師が号令をかけます
「これから〇時間目の国語の授業を始めます」という号令を日直等の子供が発する学級を見かけることがあります。授業を始め、終わりにするのは子供でしょうか。この言葉は、本来教師が発するものです。「起立、礼」等の言葉は、日直がかけることは不自然ではないでしょう。

もし、子供が授業の号令をかけることが慣例のようになっているとすれば、その意義を踏まえ、学級として、また学校として再考してみてはいかがでしょうか。
CHECK② 明確な指示の出し方
「教科書を開けてください」と若い担任の教師が子供たちに話しました。この言葉は丁寧であり、特に問題はないように感じることもあるかもしれません。しかし、ちょっと考えてみると、教師が教科書を開けることを子供に「~ください」とお願いすることでしょうか。子供への指示の出し方について、今一度振り返ってみる必要があるように感じています。
「指示・依頼・促進」の言葉の扱いを明確にします
○「教科書を開けてください」は、子供たちに依頼することでしょうか?
⇒「教科書を開けましょう」と行動を促すこと(促進)
※下学年では、子供の側に立った言い方として「教科書を開けます」と表現することもあります。
○「カーテンを開けなさい」は、子供たちに命じることでしょうか?
⇒「カーテンを開けてください」と行動を依頼すること(依頼)
○「机の下に入りましょう」と緊急時に行動を促すことでしょうか?
⇒「机の下に入りなさい」と行動を命じること(指示)
このように、子供たちへの指示等について、教師は子供の発達段階を踏まえて、その意図に応じた言葉遣いができるようにして再確認していくことが求められます。

