不登校がちな生徒への指導はどうすればいい?<中高教員の実務>
- 連載
- 中高教員の実務
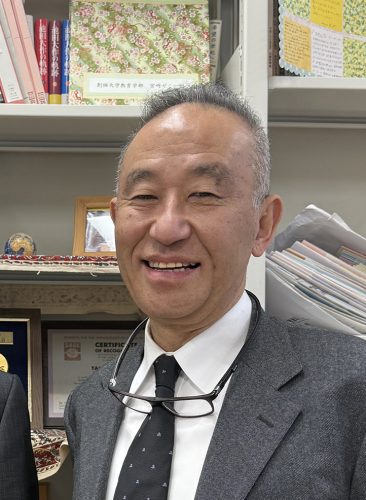

不登校につながる生徒の心の変化に気づき状況を把握しておきましょう。また、登校できない場合には定期的に連絡を続けることが大事です。
編著/小泉博明・宮崎 猛
【特集】中学校・高校教師 実務のすべて#19
最近、ふさぎ込みがちで欠席も多いAくん。学校に来たくない様子が見られるのが気
がかりです……。
「学校に行きたくない」「学校に行こうとすると、体の調子が悪くなる」などの “登校しぶり” は、不登校につながる前兆です。生徒の心の変化に気づき、素早い対応をとることが大切です。
目次
こんな変化が見られたら要注意
●教室にポツンといたり、休み時間に一人で過ごしている。
●食事を残したり、元気がなかったりする。
●頭痛や腹痛を訴え、保健室やトイレに行きたがる。
●イライラしたり、人との関わりを避けたりする。
●やる気がなくなり、部活動をサボることが増える。
↓声かけをして状況を把握します
★「どうしたの?」「何かあったの?」などと、自然な形で声をかけます。「いつも見ているよ」という安心感をもたせます。
★ 原因を無理に追及するのではなく、本人から話し出すのを待ち、様子を見ます。
★ 周りの生徒から話を聞くこともあります。
★ 養護教諭やほかの先生とも連絡をとり、情報を共有します。
★ 保護者と連絡をとって、学校での状況を伝えるとともに、家庭での様子を聞きます。

“ 登校しぶり” の兆候が見られたら
●朝になると、おなかが痛くなったり、気持ちが悪くなったりして登校できない。
●頭痛や腹痛を訴え、保健室に行く回数が増えたり、遅刻や早退が増えたりする。
●「疲れた」「つまらない」「意味ない」「面倒くさい」「無理」などの言葉が増える。
↓保護者と協力しながら状況の改善に努めます
★ 家庭では、プレッシャーをかけないようにしながら、規則正しい生活を送るよう、保護者にお願いします。
★ 本人の希望があれば、登校時に担任や友人が迎えに行くなどします。
★ 学校では、安心して生活できるように配慮します(保健室登校・カウンセラーへの相談)。
★ 原因が学校に起因している場合(いじめなど)は、その原因を解決します。

不登校が続く場合にはこう対応する!
イラスト/タバタノリコ・畠山きょうこ

