保護者への対応で困ったときはどうする?<中高教員の実務>
- 連載
- 中高教員の実務
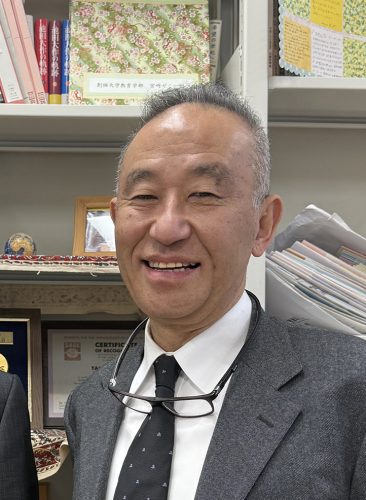

学校には様々なタイプの保護者がいます。保護者への対応をタイプごとに準備しつつ、クレームが来たときには保護者の言い分を聞き、最後まで丁寧に対応しましょう。
編著/小泉博明・宮崎 猛
【特集】中学校・高校教師 実務のすべて#14
保護者にはさまざまなタイプの人がいて、しかも全員私より年上。厳しい言葉を投げかけられることもあって、少し憂鬱です。
近年、教師の悩みの上位を占めているのが、保護者への対応についてです。その大半は、教師と保護者との“ 人間関係” における誤解から生じています。子どものことを大事に考えているのは、教師も保護者も同じ。信頼し合える関係を築けるよう、教師の努力も必要です。
目次
さまざまなタイプの保護者とその対応
不平や不満を言うタイプ
●近年多いタイプ。教育委員会などに訴えるケースも増えている。
●不平や不満に具体的に対処していく必要がある(学校側に非がある場合も)。
●担任は味方だという信頼関係を築いていく。
子どもの悪い部分を認めないタイプ
●保護者自身が責められていると思い込むことが多い。
●子どものためであり、保護者の責任を問うているのではない、とはっきり言う。
●教師と保護者が協力して、効果的な対応について話し合う。
ヒステリックに話をしてくるタイプ
●一通り話を聞く。まず感情を落ち着かせる努力をする。
●事実と推測を整理しながら、話を進めていく。
●精神的な病気の場合もあるので、慎重に話を進め、管理職などに相談する。
教師を甘く見てくるタイプ(とくに新任の場合)
●優越的な態度をとるが、その裏に劣等感を秘めている場合がある。
●丁寧に対応し、即答できないことについては、管理職と相談する。
●個人で対応するよりも、チームとして対応するほうが効果的。
子どもに威圧的なタイプ
●子育てに悩んでいる場合もあるので、悩みを共有するように話を進める。
●場合によっては、虐待が疑われることもあるので、管理職には一報を入れておく。
親子の分離ができないタイプ
●学校や教師に対する抵抗を刺激しない(厳しい対応を迫らない)。
●小さい積み重ね(学校からの連絡など)をしながら、人間関係を構築していく。
●話ができる関係づくりがまず第一歩。
組織的に対応をしなくてはいけないタイプ(虐待、ネグレクトなど)
●管理職と相談し、社会的機関とどうつなぐかを検討していく。
●必ず記録をとる。その際、事実と推測を分ける。
●保護者との信頼関係を築く努力をする(保護者や家庭の状況を確認する)。
クレームが来てしまったときの具体的な対応
学校や教師への不信感から感情的になり、クレームをつけてくる保護者は珍しくありません。教師も保護者も感情的になってしまえば、問題がこじれてしまいます。生徒の教育を真剣に考えていることは同じという立場に立って、話合いで保護者の不信感を一掃していくことが大事です。
また、担任が直接的にクレームに関わることも多いですが、課題のある保護者対応については学年で対応、共有することが徹底されてきています。自分一人で何とかしようとしないことが求められ、管理職にも些細なことでも共有することが大切とされています。具体的な対応としては、次のように進めていくとよいでしょう。
イラスト/タバタノリコ・畠山きょうこ

