『不登校』を問い直しませんか 【木村泰子「校長の責任はたったひとつ」 #18】

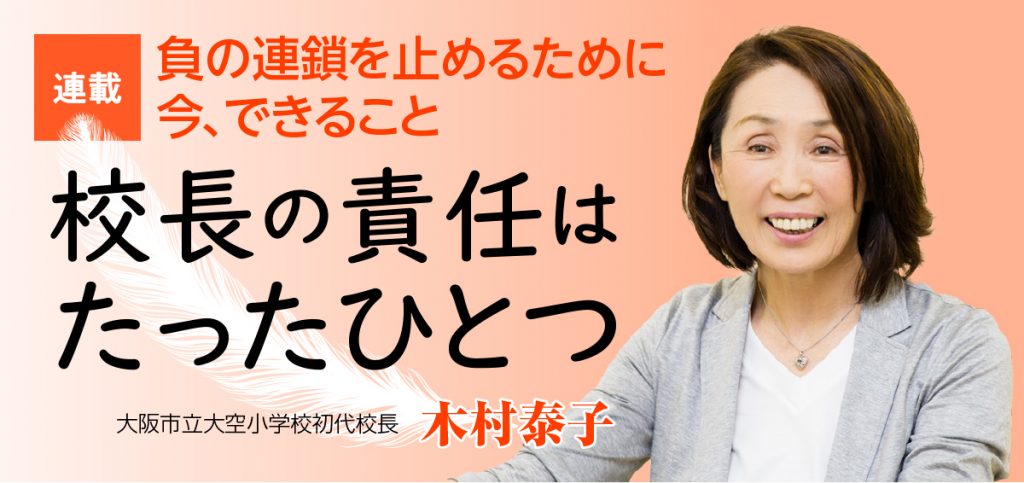
不登校やいじめなどが増え続ける今の学校を、変えることができるのは校長先生です。校長の「たったひとつの責任」とは何かを、大阪市立大空小学校で初代校長を務めた木村泰子先生が問いかけます。第18回は、<『不登校』を問い直しませんか>です。
管理職研修で耳にした残念な言葉
ある県の管理職研修に行きました。テーマは「どうすれば『不登校』がゼロになるだろうか」で、校長・教頭がグループに分かれて熱心な対話を続けました。その後、それぞれのグループが発表し、「自校の当たり前を問い直す」や「慣習を捨てる」など、学校を変えようとする前向きな発表が行われました。そのときです。一つのグループの発表者が次のように語りました。
「『不登校』の子どもたちのゴールは学校ではない。来たくなければ無理して学校に来させようとしなくてもいい。その子が行けるフリースクールや特例校などの場につないでやることが大事だ」
読者のみなさまはこの発言に対して、どのような感想を持たれるでしょうか。私はとても残念に思いました。『不登校』のレッテルを貼られている子どもたちは誰もが、地域のみんなが通学している学校に行きたいと思っているのです。学校をつくるリーダーによる「無理して地域の学校に来なくてもいい」というこの発言は、プロとして間違っても口にしてはいけない言葉ではありませんか。
パブリックの学校の使命は「誰一人取り残すことのない地域の学校をつくる」ことです。もちろん、様々な理由で学校に来ることができない子どもがいるでしょうが、地域の宝であるすべての子どもが誰一人取り残されることなく、当たり前に通える地域の学校をつくるにはどうすればいいのか、そこに目的をおいて学校づくりをしなければ、すべての子どもの未来を保障できないのではないでしょうか。
大空小の9年間で多くの子どもが『不登校』『発達障害』のレッテルを貼られて転校してきました。この子どもたちは本当に困り、苦しんでいました。親子で死んでしまおうと思っていたケースもありました。私自身、大空小に出合わなければ、『不登校』と言われる子どもや保護者がこれだけ苦しんでいるということは分からないでいたような気がします。
『不登校』の表記が出てきたのは平成10年からです。それまでは、学校に来ない子どもを「学校嫌い」というくくりに入れていました。30日以上登校しない子どもに対して平成10年から『不登校』という新たなくくりをつくったのです。この過去の経緯には疑問を感じませんか?
子どもは学校が嫌いだから学校に来ないのでしょうか。本来持つ子どもの本質はそうではありませんよね。子どもはみんな、子ども同士、一緒に遊んで一緒に過ごしたいと願っています。
『不登校』の解釈を「学校を嫌っている子」に置いている以上、パブリックの学校の使命は果たせません。まだまだ学校に浸透している否定的な「学校嫌いの子」という残念な当たり前を問い直しませんか。
卒業式に自分の席がなかった
ある中学校で、『不登校』のレッテルを貼られている子ども6名が勇気を出して卒業式に行ったが、自分の席はなかった。案内されたのは2階のギャラリーで、椅子がなかったので平均台に座っていた、との報道を目にしました。言葉を失います。学校に来なかった子に対するペナルティーだと思われても仕方がないでしょう。
ただ、この状況で卒業式が行われ、誰も「おかしい」と声を上げないこの学校の環境で、巣立っていくすべての子どもたちは育ち合っているのでしょうか。「社会につながる力」を獲得しているのでしょうか。卒業式に出席していた子どもたちは、2階のギャラリーにいる友達をどんな思いで見ていたのでしょうか。この環境を校長は「よし」としていたのでしょうか。
他校の事実かもしれませんが、自分事に変えて『不登校』を問い直すことが不可欠だと思います。
無理しないで行けるのがパブリックの学校です!
メディアも「学校は無理して行くところではない」と発信します。子どもの残念な事実『自殺』『不登校』『いじめ』をなくしたいからです。学校に行けていない子どもや保護者の方々やフリースクールの関係者の方々が「無理して行かなくてもいい」と発信してくださるのはとてもありがたいと思います。しかし、パブリックの学校のリーダーが言ってはいけない言葉です。地域住民の税金で運営されているパブリックの学校のリーダーは、すべての子どもが「無理しないで行ける地域の学校」をつくることが使命だからです。できるかできないかを問われているのではありません。リーダーが覚悟を持って「無理しないで行ける学校」をつくろうとしているかどうかを子どもたちが見ています。
日本社会に浸透し始めている「無理して行かなくていいよ」は、子どもを主語に問い直さない限りは当たり前にならず、苦しむ子どもはいなくならないと思います。
「無理しないで行ける学校」を子どもと教職員と保護者と地域の人たちと一緒につくりませんか!

1 公立学校の使命は「誰一人取り残すことのない地域の学校をつくる」こと。
2 不登校の子どもは「学校を嫌っている子」ではない。
3 「無理しないで行ける学校」をみんなでつくろう!

木村泰子(きむら・やすこ)
大阪市立大空小学校初代校長。
大阪府生まれ。「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに情熱を注ぎ、支援を要すると言われる子どもたちも同じ場でともに学び、育ち合う教育を具現化した。45年間の教職生活を経て2015年に退職。現在は全国各地で講演活動を行う。『「みんなの学校」が教えてくれたこと』(小学館)など著書多数。
【オンライン講座】子どもと大人の響き合い讃歌〜インクルーシブ(共生)な育ちの場づくり《全3回講座》(木村泰子先生✕堀智晴先生)参加申し込み受付中! 大空小学校時代の「同志」お二人によるスペシャルな対談企画です。詳しくは下記バナーをクリックしてご覧ください。

