野外で教材研究してみよう ~小学校理科の地球領域~【理科の壺】

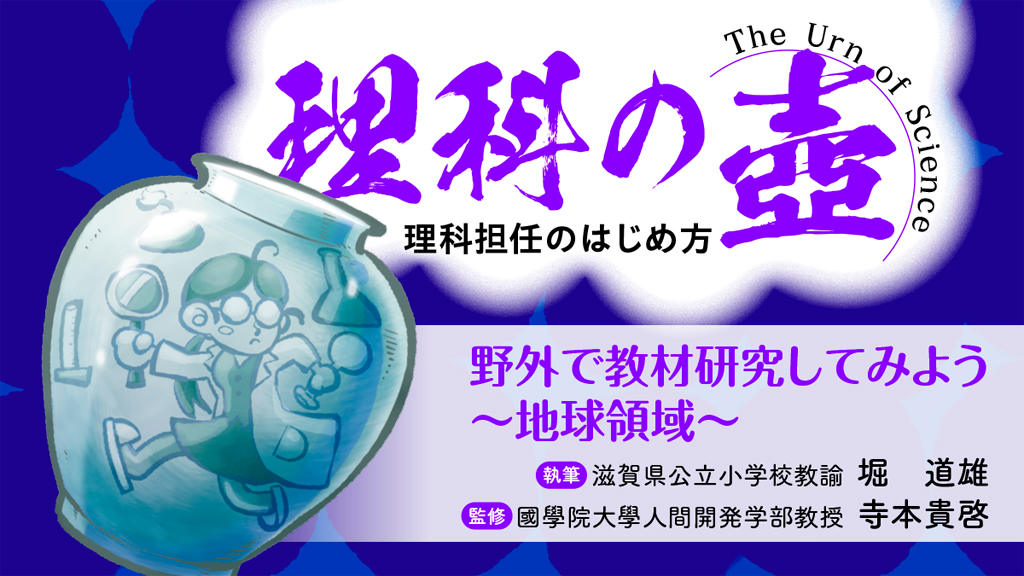
地学系の学習は、子どもたちに実際に体験や観察をさせたくても、天気や周囲の環境によって授業のやりやすさが変わってきます。しかし、複数の学年を通して考えてみると、どのようなつながりがあり、それぞれの学年で何を学んだらよいのかがはっきりしてきますので、授業づくりも工夫できそうです。例えば、先を見とおして事前に写真を撮っておいたりするとその後の授業づくりが楽になります。このように、一度地学系の教材をまとめて教材研究してみるのもいいかもしれません。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/滋賀県公立小学校教諭・堀 道雄
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
地球領域の学習は身近な地域の教材を活用しよう
小学校理科の地球領域の学習は、教科書の教材だけでなく、身のまわりにある場所を教材化できる、もってこいの領域です。それぞれの学年の地球領域の単元において、可能であれば子どもたちと実際に現地に足を運んで、もしそれが難しいようであれば、身近にある教材を写真や映像に撮影するなどして活用すると、子どもたちが自分の目で見たことと自然の事物・現象を結び付けられるようになります。本稿では、どのように教材化するかいくつかの単元を取り上げてみたいと思います。
1.第4学年「雨水のゆくえと地面の様子」
第4学年「雨水の行方と地面の様子」は、子どもたちにとって一番といってもいいくらい身近な運動場を活用することができます。雨が降ったときにどこに水がたまり、どのように流れているかを校舎の上の階から確認したり、傘をさしながら実際に見に行ったりすることができます。実際に子どもたちに観察させるためには、教師があらかじめ運動場の構造を理解しておく必要があります。また、タブレットのタイムラプス機能を使って、時間の経過による運動場の水のたまり方の変化を撮影しておくとその構造が理解できるだけでなく、子どもたちに導入等で提示する写真としても活用できます。また、下の写真のように雨が降っているとき(左)と雨が降った後の写真(右)を用意して、比較できるようにすることもよいでしょう。

さらに、雨水が高いところから低いところに流れる性質と関連する身近な場所も、校区や近隣の地域から紹介することもできます。例えば、道路のアンダーパスや地下鉄の駅の入り口が少し高くなっている場所を写真撮影しておくと発展的に活用することができます。

