<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #15 高知大学教育学部附属小学校2年B組③<前編>

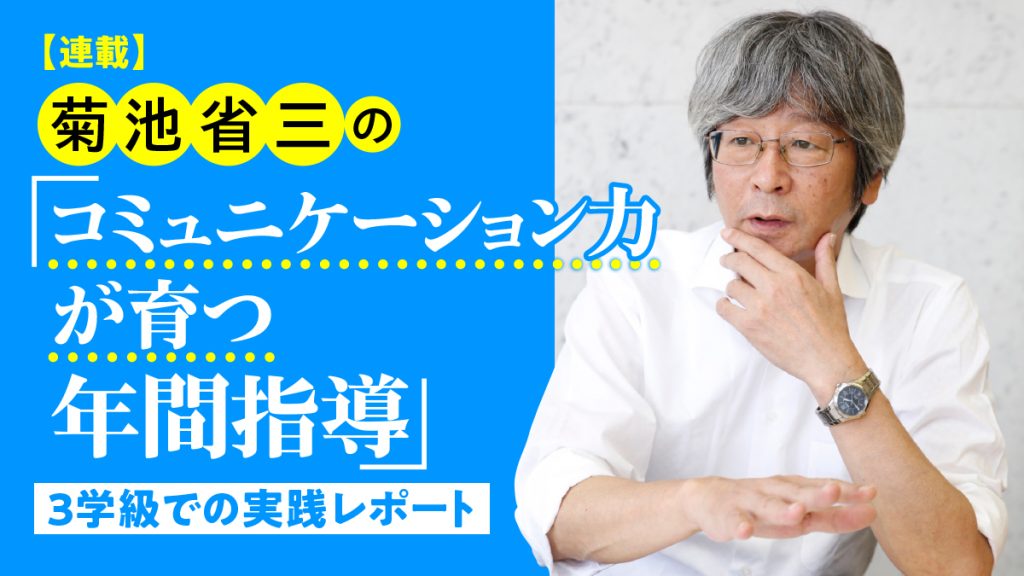
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする連載。今回から、高知の小笠原学級(2年生)における11月の授業レポートをお届けします。菊池先生と小笠原先生による、2時間続きの合同授業の記録です。

目次
担任・小笠原由衣先生より、学級の現状報告
ほめ言葉のシャワーには力を入れて取り組み続けています。
毎日記録している動画を見ると、子供たちの表情が明るくなってきていることがわかります。係活動も充実してきました。「やさしい係」「ポスター係」「漫画係」などの係活動が生まれ、おとなしい子が活躍できる場面が増えました。
最近は、担任と子供の呼応する関係が築けてきたと感じています。
子供たちとの言葉のキャッチボールで、楽しいやり取りができるようになってきました。少しずつ解放された学級に近づきつつあります。
男子女子関係なく話をすることは、まだまだですが、「今日は3人の男の子と聞き合いができたよ」「5人も女の子に聞いてもらった」と発言する子がいることで、「男子女子関係なく」という価値語が定着してきました。
とはいえ、まだお互いに高め合う集団にはなっていません。真面目にやらないことを「かっこいい」と思っている子、騒いだりつるんだりしてしまう子もおり、ばらばらでエネルギーが少ないようにも感じます。
一部の子のじゃれあいによって空気が悪くなっていることを改善し、エネルギーが低い子を引き上げて巻き込む力を高めるために、どこからアプローチしていけばよいか、日々考えています。
菊池先生と小笠原先生の合同授業レポート
小笠原先生が授業風景の写真を見せながら、
「この間、成長ノートに『フリートークのいいところ・困ったところ』を書いてもらったよね。それをまとめてみました」
<いいところ>
●友達を知ることができる
●笑い合える
●仲良くなれる
●言葉が出やすくなる
●普段しゃべらない人としゃべれる
●話すのが好きになる
●思いつかないとき、「どっちがいい?」と聞いてくれた
●笑顔で「どうぞ」
下から2番目の「いいところ」について、「え、どういうこと?」と子供たちが質問すると、
「『うどんとラーメン、どっちが好き?』と聞かれて思いつかずに黙ったとき、『じゃあ、うどんかカレーやったらどっち?』とAさんが聞いてくれたんだそうです。Aさんに大きな拍手!」
と小笠原先生が説明すると、子供たちがA君に大きな拍手を送った。
「(最後の)笑顔で『どうぞ』は、話に詰まったとき、Bさんが笑顔で手を添えて『どうぞ』って言ってくれたので話しやすくなったそうです。これもBさんに拍手でしょう」
みんな笑顔でBさんに拍手をした。
<困ったこと>
●動きが遅い
●お題をもっとしたい
●関係ないおしゃべり
●どんな順番で話したらいいかわからない
●ふざける子がいる
●途中、話が止まる
![]()
子供たちが困ったこととして挙げた意見の中には、「ふざける」「関係ないおしゃべり」など、対話中の態度や姿勢にかかわるものがありました。
フリートークは、4~5人が輪になって進めていきます。このとき、みんながきちんと向き合って話せているか、だらだらとしていないかなどを見取り、本気で対話に向かう姿勢を整えていくことが大切です。子供たちの発表後に、「じゃあ、今、みんなは4人で話し合う姿勢ができているかな?」と時々確認してもいいでしょう。
日々の話し合いの中で、話し合いの姿勢についてもレベルアップしていく意識が大切です。
「菊池先生は子供たちの感想を聞いて、どう思いますか?」
小笠原先生が菊池先生に尋ねると、菊池先生が、
「この2時間の授業で、みんなが出した『いいところ』がもっとよくなって、『困ったこと』を一緒に解決していけたら、素晴らしい教室になります。フリートークがもっと長く続いて、もっと楽しくなる “ヒミツ” をみなさんと一緒に見つけて、日本一のフリートークができる教室になってほしいな、と思っています」と答えた。
菊池先生の話を聞いて、小笠原先生が黒板に書いた。
<フリートークがもっと楽しく長く続くヒミツを見つけよう>
みんなが最高の姿勢で、ピシッと背筋を伸ばした。

