小学校の教室で行うアンガーマネジメント教育(中学年編) ~怒りの仕組みを理解し、自分でコントロールする力を育む~

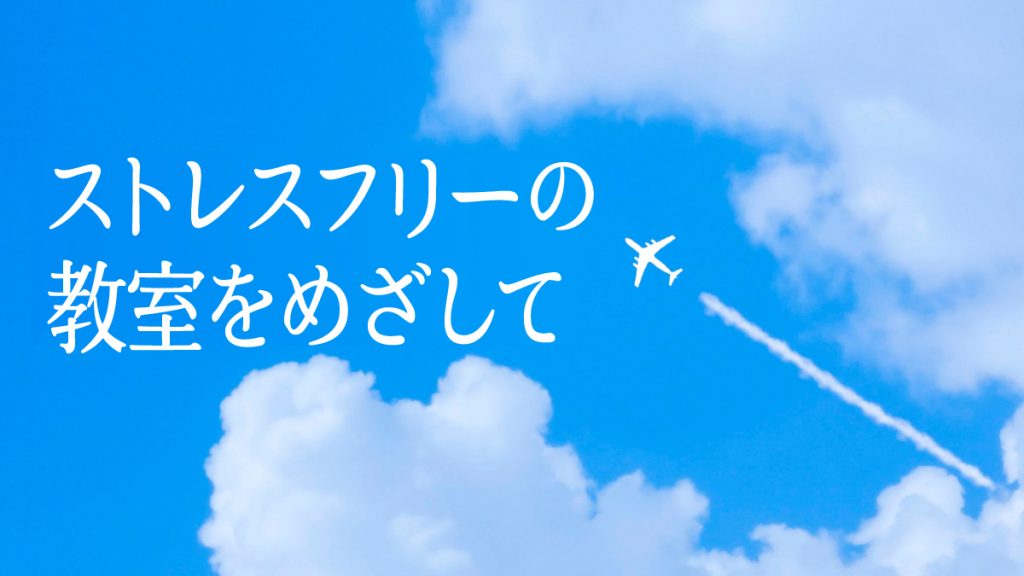
小学校中学年は、自己主張や対人関係が活発化する時期です。この頃になると、友だちとのトラブルや不満から怒りの感情が生まれることも増えます。中学年の子どもたちには、自分の怒りの原因を理解し、適切に対処する方法を学ぶことが重要です。今回は、小学校中学年を対象にしたアンガーマネジメント教育の指導アイディアについてまとめました。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #23
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
目次
中学年向けアンガーマネジメント教育のポイント
中学年のアンガーマネジメント教育では、次のようなポイントを押さえましょう。
①怒りの感情が生まれるメカニズムを知る。
②怒りを表現する方法としずめる方法を学ぶ。
③トラブルを解決するための建設的な対話スキルを身につける。
これらを通じて、子どもたちが怒りを感じた際に冷静に対処できる力を養います。
指導アイディア①「怒りの原因を探そう」
<目的>
・怒りの感情が生じる原因を考え、自分の感情を理解する力を育てる。
・怒りを引き起こす要因を把握し、冷静に対応するための土台を作る。
<準備物>
・怒りの場面カード:怒りを感じやすいシチュエーションを描いたイラストや文章のカード。
(例「友だちに悪口を言われた」「順番を飛ばされた」「大事なものを壊された」など)
・感情カード:おこる、かなしい、うれしい、びっくり、こわいなどの感情について、その表情が描かれたイラストのカードを用意します(感情ごとに複数枚)。
<導入>
・先生の説明:
「みなさんは最近、イライラしたり怒ったりしたことがありますか?今日は、怒りの原因を探して、どうしてそんな気持ちになったのかを考えてみたいと思います」
※怒りは悪い感情ではないことを伝え、「怒るのは自然なこと。その原因を知ると、もっと気持ちをコントロールしやすくなること」を説明します。
<展開>
ゲーム① 「怒りの場面」を考える
①場面を提示する
教師が1枚ずつ「場面カード」を見せます。
(例:「友だちが自分の発表をバカにした」「先生に叱られた」など)
②感情を言葉にする
「この場面で、どんな気持ちになるかな?」と子どもたちに尋ねます。
※子どもたちに自由に答えさせ、板書していきます。
(例:怒り、悲しみ、恥ずかしさなど)
③原因を探す
「どうしてそんな気持ちになったんだろう?」と問いかけ、グループで話し合います。
④グループごとに発表
怒りの原因を考え、グループの代表者が発表します。
【ポイント】
・結局「友だちが自分の発表をバカにしたから」という結論になってしまう場合があります。ここで考えたいのは、「なぜ怒ってしまったのか」についてです。この例では、「自分は一生懸命発表して自信があったから嫌だった」「みんなが聞いている前でバカにされたのが嫌だった」などと、その場面を膨らませて深掘りしていきます。
・必ずしも「怒り」の感情にならない場合があります(悲しい、恥ずかしいなど)。その場合は、その感情に至る過程について話し合ってもOKです。
ゲーム② 「怒りの温度計」
①場面カードを使い、個人が怒りの強さを1~5段階で評価します。
(例:「友だちに順番を飛ばされた → 怒りレベル3」「先生に不公平に注意された → 怒りレベル5」など)
②グループを作ります。
③怒りの強さをみんなで共有し、「なぜその温度にしたか」を話し合います。
【ポイント】
・同じ出来事でも、人によって怒りの温度が異なることに気付かせましょう。
<終末>
「今日は、怒りの原因についてどんなことを学びましたか?」
「これから怒ったときに、どうやって対処しようと思いますか?」
【アドバイス】
①安心できる環境を作る
子どもたちが自分の気持ちを正直に話せるよう、穏やかで受容的な雰囲気を作ることが大切です。
②感情を多角的に見る
「怒り」だけでなく、「悲しみ」や「恥ずかしさ」など、他の感情も取り上げることで理解が深まります。
③多様な場面を扱う
子どもたちが共感しやすい、身近な場面を題材に選ぶと効果的です。

指導アイディア②「6秒ルールの練習」
<目的>
・怒りを感じたときに衝動的な行動を防ぎ、冷静に行動するスキルを身につける。
・「6秒ルール」を実践し、感情を落ち着かせる具体的な方法を学ぶ。
<準備物>
・タイマーまたは時計:6秒間を計測するために使用します。
・怒りの場面カード: 怒りを感じやすいシチュエーションを描いたイラストや文章のカード。
(例「友だちに名前をからかわれた」「順番を飛ばされた」など)
<導入>
・先生の説明:
「みなさんは、怒ったりイライラしたりしたとき、すぐに何か言ったり、行動してしまったことがありますか?今日は、そのイライラを少し落ち着かせるための方法を練習したいと思います。その方法の名前は『6秒ルール』です」
<展開>
活動①「6秒ルール」の基礎を学ぶ
①怒りの仕組みを簡単に説明
「怒りは、体の中でわき上がってくる感情です。怒りは、最初の6秒間は何も言わず、何もせずに深呼吸すると、不思議と落ち着いてくると言われています。」
②実際に6秒を体感
・先生がタイマーで6秒を計り、「6秒間、何もしないでじっとしてみよう」と子どもたちに指示します。
・「思ったより短かった?長かった?」と問いかけ、6秒の長さを実感します。
活動②「6秒間の過ごし方」を練習する
①6秒間の行動の提案
・深呼吸をする(鼻からゆっくり吸い、口から吐く)。
・1から6まで心の中で数える。
・頭の中で好きなことを思い浮かべる(ペットや好きな景色など)。
②実践練習
・怒りの場面カードを引き、その場面で6秒間をどう過ごすかを子どもたちに選んでもらいます。
・「友だちに名前をからかわれたら、6秒間何をする?」と問いかけ、それぞれ実践します。
③ペアワーク
・子どもたちをペアに分け、一人が怒りの場面を説明し、もう一人が6秒間の対処法を考えて発表します。
活動③「6秒ルール」のロールプレイ
①ロールプレイ
学校で起こりやすいトラブルをシナリオ化し、子どもたちにロールプレイをしてもらいます。
(「友だちが自分の絵をバカにした」「順番を飛ばされた」など)
②6秒ルールを実践
子どもたちが6秒間を上手に使って気持ちを落ち着かせられるか試します。
③振り返り
「6秒間何をしたら気持ちが落ち着いた?」を発表させます。
<終末>
「怒ったとき、6秒ルールを使うとどんな気持ちになった?」
「これから怒ったら、どんな方法を試してみたい?」
【アドバイス】
①肯定的な雰囲気
子どもたちが怒りを感じることを否定せず、「怒りをコントロールするのはすごいことだよ」と伝えましょう。
②選択肢を広げる
6秒間の過ごし方を自由に選べるよう、複数のアイディアを提示しましょう。
③繰り返し練習
短い時間でも頻繁に練習を繰り返すことで、習慣化を目指します。
家庭との連携
低学年同様、家庭でのサポートも重要です。以下のような活動を通じて保護者との連携を図ります。
①保護者への情報提供
「子どもの怒りにどう向き合うか」についてアドバイスをまとめたプリントを配布します。
②家庭での実践
授業で学んだ「怒りの温度計」や「6秒ルール」を家庭でも実践してもらえるよう保護者に啓発します。
中学年の子どもたちにとって、怒りの感情をコントロールする力を身につけることは、対人関係を円滑にするだけでなく、自分自身を成長させるためにも重要な学びです。学校や家庭が協力して、子どもたちが感情を上手に扱える力を育てていきましょう。
イラスト/坂齊諒一
<プロフィール>
春日智稀(かすが・ともき)
2015年より埼玉県公立小学校教諭。体育主任・生徒指導主任・研究主任・教務主任などを担当。
学校心理士/ケアストレスカウンセラー/青少年ケアストレスカウンセラー/アンガーマネジメントキッズインストラクター/アンガーマネジメントティーンインストラクター
日本生徒指導学会・日本学校教育相談学会・日本教育心理学会・NPO日本教育カウンセラー協会/所属

