「認定こども園」とは?【知っておきたい教育用語】
幼児教育と保育を一体的に行う「認定こども園」。今回は、子育て支援としての機能や役割も果たす認定こども園の種類とその概要、通園するメリットやデメリット、職員の資格などについて解説します。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・宮崎猛
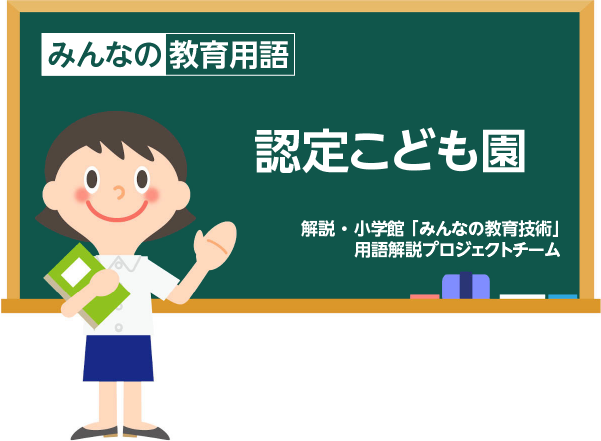
目次
認定こども園とは
【認定こども園】
幼稚園と保育所の機能を一体的に実施する施設で、0歳から就学前の子どもが利用できる教育・保育機関。2006年に制度が誕生し、従来の縦割り制度の課題解決や待機児童問題の解消、さらには子どもの集団生活の充実をめざして設置された。
認定こども園は地域や保護者のニーズに合わせて、主に4つのタイプに分類されます。保護者の就労状況にかかわらず利用可能で、長時間保育や異年齢交流を実現し、子どもの健やかな成長を支援しようとするものです。認定こども園の認定基準は、主に内閣総理大臣・文部科学大臣および厚生労働大臣が定める国の基準に基づいています。
●幼保連携型
幼稚園的機能と保育所的機能を一体的に備えた単一施設。幼児教育と保育が統合されたカリキュラムが実施され、異年齢の子どもたちがともに過ごすことで、自然な形での社会性や自立心が育まれる。また、長時間保育が可能なため、保護者の働き方に柔軟に対応できるという特徴がある。
●幼稚園型
従来の認可幼稚園を基盤とし、保育機能を追加したもの。幼稚園として学習指導要領に沿いつつ、延長保育や早朝・夜間保育を提供し、転園の必要なく継続して利用できる。
●保育所型
認可保育園を基に幼児教育の要素を取り入れたタイプ。保育士による専門的な保育を維持しながら教育プログラムを組むことで、保育の安心感と教育の充実を両立している。
●地方裁量型
認可外の施設を自治体独自の基準で認定し、地域の実情に合わせた柔軟な運営を実施。待機児童解消や地域資源の活用を目的とし、施設ごとに特色あるカリキュラムやサービスを展開している。
認定こども園では利用対象の子どもに応じ、1号認定(子どもの年齢が満3歳児以上で約4時間の標準時間)と2号・3号認定(最大11時間の標準時間または最大8時間の短時間)に区分されます。給食、延長保育、送迎などのサービスは各施設・自治体の特色を反映しており、家庭の多様なニーズに対応した運営体制が整備されています。
認定こども園に通うメリットとデメリット
認定こども園のメリットは、幼稚園と保育所の両機能を同一施設で受けられる点です。転園の必要がなく、継続的な環境のなかで子どもが成長できるほか、異年齢交流により社会性が養われます。さらに、給食や延長保育、送迎など、保護者のライフスタイルに合わせたサービスが充実している点も魅力です。
一方、デメリットとして、保育料無償化の対象であっても食費や行事費などの追加費用がかかることや、利用枠が限られているため希望の園に必ず入園できるとは限らない点が挙げられます。
実際の運用や具体的な運営基準は各自治体により若干のちがいがあるため、最新の詳細情報は各自治体の公式サイトで確認する必要があります。
職員の資格
認定こども園の職員は園のタイプや対象年齢に応じた資格要件が設定されています。幼保連携型では、原則として幼稚園教諭免許と保育士資格の両方が求められます。他のタイプでは3歳以上の子どもに対して幼稚園教諭免許または保育士資格、3歳未満の場合は保育士資格が必須です。
認定こども園は、幼稚園と保育所の両面の特徴を兼ね備えた柔軟な子育て支援施設です。教育と保育が一体となった環境は子どもの成長を促す一方で、利用条件や費用面での注意点も存在します。各家庭の事情や地域の特色に合わせた適切な選択が、安心して子育てを行ううえでの重要なポイントとなります。
▼参考資料
こども家庭庁(ウェブサイト)「認定こども園概要」
こども家庭庁(PDF)「未来をつくり出す力の基礎を培うために 幼保連携型認定こども園ってどんなところ?」
Benesse(ウェブサイト)「認定こども園とは? 保育所・幼稚園との違いやメリット・注意点を簡単に解説!」2024年12月23日

