小3特別活動「3年○組 なかよくなろう集会をしよう」指導アイデア

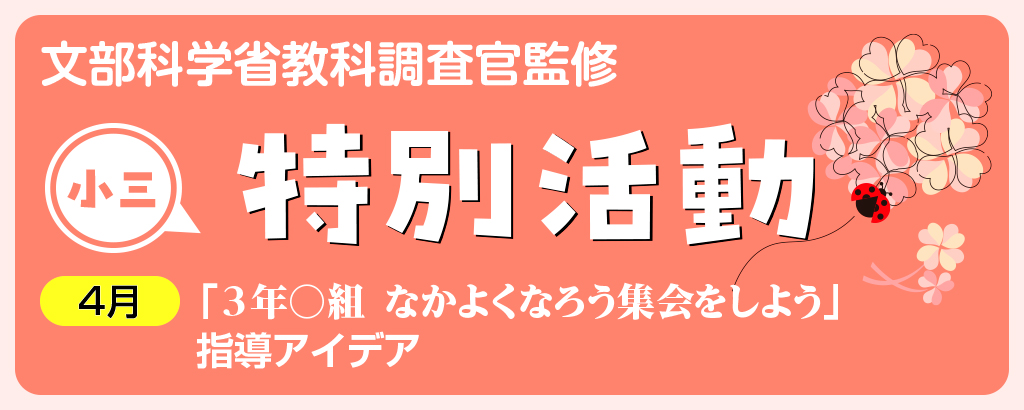
文部科学省教科調査官監修による、小3特別活動の指導アイデアです。4月は、学級活動(1)「3年○組 なかよくなろう集会をしよう」の実践を紹介します。活動を通して年度当初において学級生活への前向きな気持ちと、協力して活動することの楽しさを味わうことができるようにすることを目指します。
執筆/神奈川県公立小学校主幹教諭・池田恭平
監修/文部科学省教科調査官・和久井伸彦
神奈川県公立小学校校長・源関正浩
目次
年間執筆計画
4月 学級活動(1) ア 3年○組 なかよくなろう集会をしよう
5月 学級活動(2) エ バランスのよい食事
6月 学級活動(3) イ パワーアップ係活動
7月 学級活動(1) ア 1学期がんばったね集会をしよう
9月 学級活動(3) ウ 広げよう!読書の楽しさ
10月 学級活動(1) ア 運動会がんばったね集会をしよう
11月 学級活動(1) イ 係活動発表WEEKをしよう
12月 学級活動(2) イ 友達のよいところ~みんなニコニコ大作戦~
1月 学級活動(1) ア 新春!昔遊びをしよう
2月 学級活動(1) ア ペア学年と集会をしよう
3月 学級活動(3) ア もうすぐ4年生~ワンアップ大作戦~
本議題のねらい
新しい学級になった4月。「これから楽しみだな」「どんな担任の先生なんだろう」「新しい友達ができるかな」と期待や不安をもつ子供たち。
今回の活動を通して、「これからみんなと過ごす1年が楽しみになりそうだな」という学級への前向きな気持ちと、協力して活動することの楽しさを味わうことができるようにすることを目指します。

