公立学校の教員と地方公務員の違いって?教育職員免許法と教育公務員の身分・服務~シリーズ「実践教育法規」~
- 連載
- シリーズ「実践教育法規」


教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第32回は「教育職員免許法と教育公務員の身分・服務」について。地方公務員のうち、幼稚園や学校に務めるのが教育公務員。任用期間などにおいて、その他の地方公務員とは異なる規定が適用されていることを知っていますか?
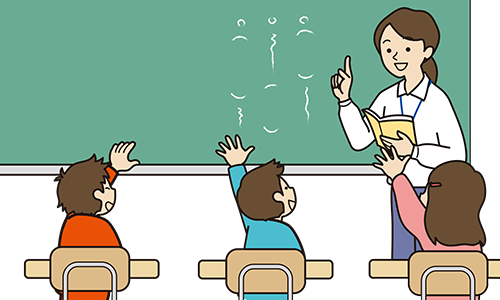
執筆/千々布 敏弥(国立教育政策研究所総括研究官)
監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)
【連載】実践教育法規#32
目次
教育職員免許法
教育職員免許法により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教員は、それぞれの学校種に相当する教員免許状が必要であると規定されています。
また、義務教育学校の教員は、小学校と中学校両方の教員免許状、中等教育学校の教員は、中学校と高等学校両方の教員免許状が必要であり、特別支援学校の教員は、特別支援学校と特別支援学校の各部に相当する教員免許状が必要です。
教育公務員とは
教育公務員とは、地方公務員のうち、市町村や都道府県が設置する幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校に勤務する職員を意味しています。
基本的に義務教育段階の小中学校は市町村に設置義務があります(都道府県や国が設置することは可能)。したがって、小中学校の教員の多くは人事権が都道府県にありながら市町村の公務員となり(都道府県立小中学校の場合は都道府県の公務員となる)、地方公務員法の適用を受けています。
服務とは、公務員が職務遂行上または公務員としての身分に伴って守るべき義務ないし規律のことを言います。地方公務員法は「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定されています。

