子供たちといっしょに読みたい 今月の本#9 防災・災害を考える本

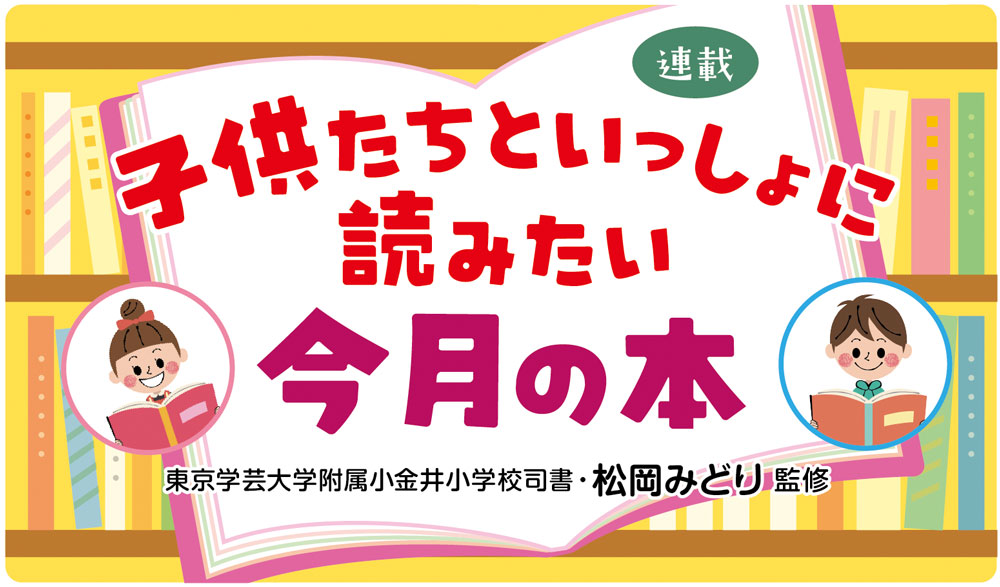
連載9回目のテーマは、「防災・災害を考える本」です。日本は自然災害が多い国。自然災害が起こったときにどのようにするかなど、防災意識を高めるきっかけになるような本を紹介します。子供たちの1人読み、先生が読む、読み聞かせなど学級の実態に合わせてください。
監修/東京学芸大学附属小金井小学校司書・松岡みどり

目次
絵本
低学年にも親しみやすい絵本で、地震の際の自分自身の守り方を知り、防災について考えることができます。ストーリー仕立ての絵本なので、子供たちが自分事として興味をもつことができるでしょう。
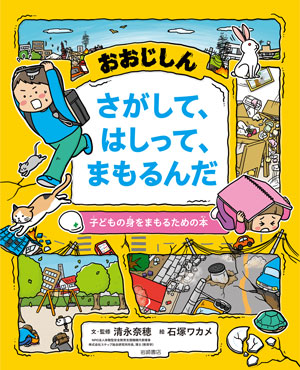
『おおじしん さがして、はしって、まもるんだ』
文・監修/清永奈穂 絵/石塚ワカメ
岩崎書店刊
大地震発生直後の8秒が生死を分ける、と言われています。子供が1人のとき、この8秒間にどうやって自分の身を守ればよいのかが分かる絵本です。
松岡司書のおすすめポイント
地震直後にどのように動くかが分かりやすく描かれているストーリー形式の絵本です。「さがして(うさぎ)、はしって(ねずみ)、まもるんだ(かめ)」という合言葉は子供にとって覚えやすく、逃げる場所を確保し、次の揺れに備えることが初期動作として大切だということを教えてくれます。低学年だけでなく、中・高学年にも読んでほしい内容です。
読み物
地震が起きたときには、誰しも慌てることでしょう。日ごろから地震についての知識をもっていれば、具体的な行動をイメージしやすく、いざという場合に備えることができます。
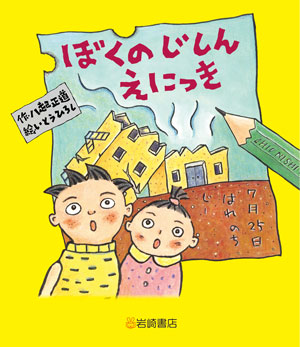
『ぼくのじしんえにっき 新装版』
作/八起正道 絵/いとうひろし
岩崎書店刊
大地震で町がメチャンコになった! そのときのことを主人公の僕が絵日記に描きました。子供目線で淡々と描かれる厳しい場面が、阪神淡路大震災、東日本大震災を経験した今、リアルに迫ります。1989年に刊行された第6回福島正実記念SF童話賞大賞受賞作。
松岡司書のおすすめポイント
この作品は、阪神淡路大震災より前に書かれた創作の物語です。主人公が読者の子供たちに近い年齢で、地震が起きたときの様子がイメージしやすい内容になっています。東日本大震災から10年以上が経過し、災害に遭ったことのない子供たちに大切なことを伝えてくれることでしょう。1人読みがおすすめです。

