著作権者の承諾なしに利用できるものがある?著作権と例外規定の適用~シリーズ「実践教育法規」~
- 連載
- シリーズ「実践教育法規」


教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第26回は「著作権と例外規定の適用」について。著作権の定義について今一度確かめるとともに、学校教育に関わる例外規定や、許諾手続きが容易になる制度についても押さえておきましょう。
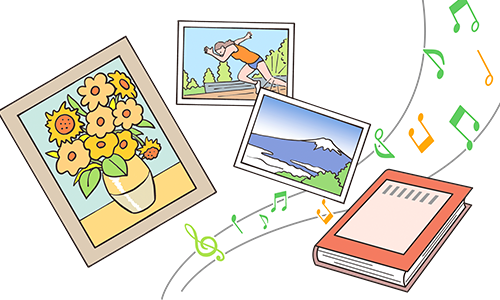
執筆/鶴田 利郎(国際医療福祉大学小田原保健医療学部講師)
監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)
【連載】実践教育法規#26
目次
著作権法とは
「著作権法」とは「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的」として定められたものです(著作権法第1条)。
著作権とは
人間の知的で創作的な活動によって生産されたものを利用する権利の総称を「知的財産権」といい、そのうち「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作物)」(著作権法第2条)を対象としたものを「著作権」といいます。小説、音楽、絵画、映画、写真、コンピュータ・プログラムなどに加え、児童生徒の作品にも著作権が適用されます。
著作権は産業財産権とは異なり、権利を得るための手続きを必要としません。著作物が創作された時点で自動的に権利が発生します。これを無方式主義といいます。
著作権は「著作者の権利」と伝達者の権利である「著作隣接権」の2つに大別されます。そのうち「著作者の権利」は「著作者人格権」と「著作権(財産権)」に分けられます。


