次年度、みんなが気持ちよく仕事ができるように!「学年配置」の考え方|校長なら押さえておきたい12のメソッド #11

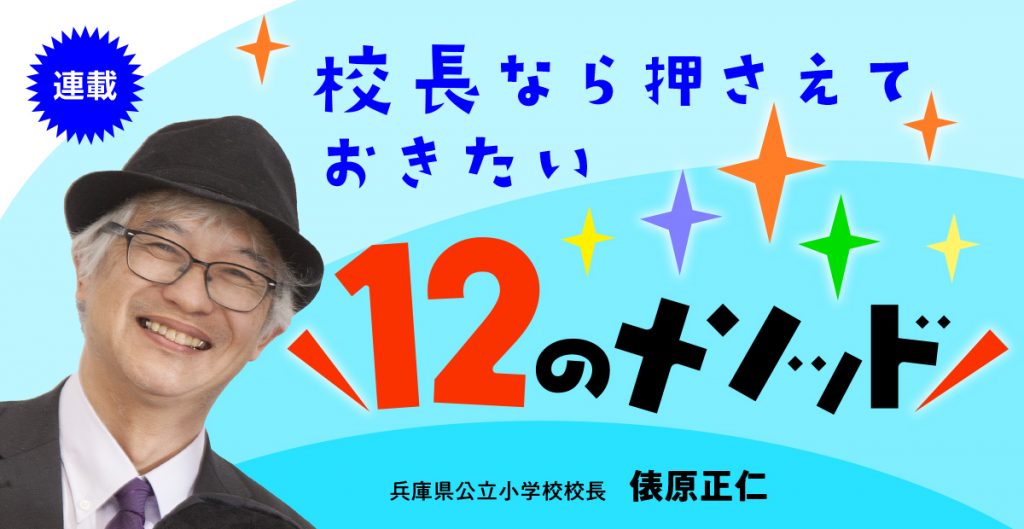
新任や経験の浅い校長先生に向けて、学校経営術についての12の提言(月1回公開、全12回)。校長として最低限押さえておくべきポイントを、俵原正仁先生がユーモアを交えて解説します。第11回は、学年配置の考え方についてレクチャーします。
執筆/兵庫県公立小学校校長・俵原正仁
目次
早いもので、次年度のことを考える時期になりました
2月になりました。そろそろ次年度のことが気になり始める頃です。私の勤務する兵庫県芦屋市では、異動などの関係もあってどの学年を担任するのか確定するのは3月末になるのですが、私は、大体これぐらいの時期から次年度の学年構成をぼんやりと考え始めます。
一方で、次年度の学年配置や校務分掌などが3月ではなく2月中にはほぼ確定している地域もあると聞きました。そのような地域の校長先生は、現在、学年配置を考えている真っ最中ではないでしょうか。ということで、今回は次年度の学年配置を考えるにあたって、2月から3月にかけて私が行っていることをお話しさせていただきます。ご参考にしていただければ、幸いです。
次年度の学年予想は当たらない……
担任時代の話です。この時期になると、仲のいい先生方と行っていた遊びがありました。題して、「次年度の担任予想ゲーム」。何の情報も入ってこない2月のこの時期に、次年度の担任を予想する遊びです。2月中に予想を書き留めて封印し、4月になったら答え合わせをします。的中率が高かったからといって、特にいいことがあるわけでもないのですが、わいわいと楽しんでいました。ところが、この「担任予想」がなかなか当たらない。4月当初の職員室で行われる担任発表とは、大きく違っていることがほとんどでした。
当時は、「校長は、分かってないわ。自分が考えている案の方が絶対にいいのに……」と思っていたのですが、校長になって、実際に自分が原案を考える立場になって、それが大間違いだということが分かりました。
いっしょに勤務している先生方の情報のうち、一担任が正確に把握できるのは、経験年数ぐらいです。同じ学年を組んでみて、あるいは、飲み会でいっしょに騒いでみて、初めてこの先生は、こんなキャラクターだったんだと感じたことってありませんか? つまり、それぞれの先生方の人となりなど、よっぽど仲のよい先生ぐらいしか分かっていないのです。さらに、どのように子供たちに関わっているか、授業の腕前はどうかなどは、普段、他のクラスの様子を見に行くことができない一担任が把握することは不可能です。何よりも、先生方の個人的な思いは分かりません。
つまり、独りよがりの勝手なイメージで組んだ学年予想が当たるはずなかったのです。このことは次のように言い換えることができます。
校長は、個々の状況、事情を全て把握した上で学年配置を行わなければいけない。
釈迦に説法。校長先生にとっては、自明の理のことですよね。

