事務職員の仕事の範囲はどこまで?学校事務と学校財務~シリーズ「実践教育法規」~
- 連載
- シリーズ「実践教育法規」


教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第18回は「学校事務と学校財務」について。事務職員の標準的な職務の内容や、財務に関わる教育委員会との連携などを解説します。
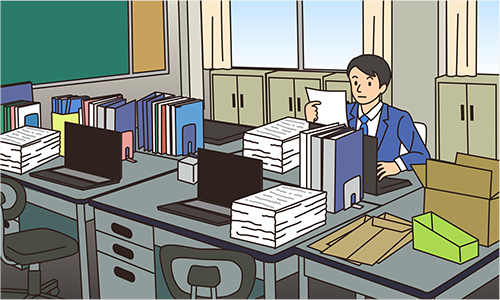
執筆/江口 和美(敬和学園大学人文学部准教授)
監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)
【連載】実践教育法規#18
目次
体制の充実と運営改善
学校事務が担う職務は、2017年3月の「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律」成立を機に、標準的な職務の内容が文部科学省から初めて例示されました。この法改正には、学校の「体制の充実」と「運営改善」を実現するために、基礎定数化に伴う教職員定数標準の改正や学校運営協議会の役割見直し、事務職員の職務内容の改正と「共同学校事務室」の規定整備が含まれていました。
改正のポイントは、以下の2つでした。①事務職員の校務運営への主体的な参画を目指し、学校教育法第37条14項を従前の「事務に従事する」から「事務をつかさどる」に変更、②地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)に第47条の4を新設し、教育委員会規則で所管する2校以上を指定し、共同学校事務室を設置することが可能とされました。
さらに2019年1月に中央教育審議会が「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」で、働き方改革推進には学校と教員が担う業務の明確化と適正化の確実な実施が必要と指摘。文部科学省は「学校・教師が担うべき業務の範囲について、学校現場や地域、保護者等の間における共有のため、学校管理規則のモデル(学校や教師・事務職員等の標準的職務の明確化)を周知」することとされました。
以上を受け、2020年7月に初等中等教育局が「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)」を発出。この中で「事務職員の標準的な職務の内容及びその例」が示されました(文部科学省「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)」(2020 年7月17 日)別添2)。
この法改正に至る経緯を概観します。2015年3月の国立教育政策研究所「小中学校の学校事務職員の職務と専門的力量に関する調査報告書」で、職務内容の明確化や事務の共同実施を進めると職務範囲の拡大や高度な思考力等を必要とする「運営系事務」を担当するようになる傾向が示されました。さらに、2015年12月の中央教育審議会「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)」では「学校のマネジメント機能の強化」策として事務体制の強化が提言され、学校教育法上の事務職員の職務規定の見直しと共同学校事務室の法令上の明確化が提案されました。以上を受けて、法改正や事務職員の標準的職務の内容が例示されるに至りました。

