トップダウンではなくボトムアップの提案をするための戦略|校長なら押さえておきたい12のメソッド #10

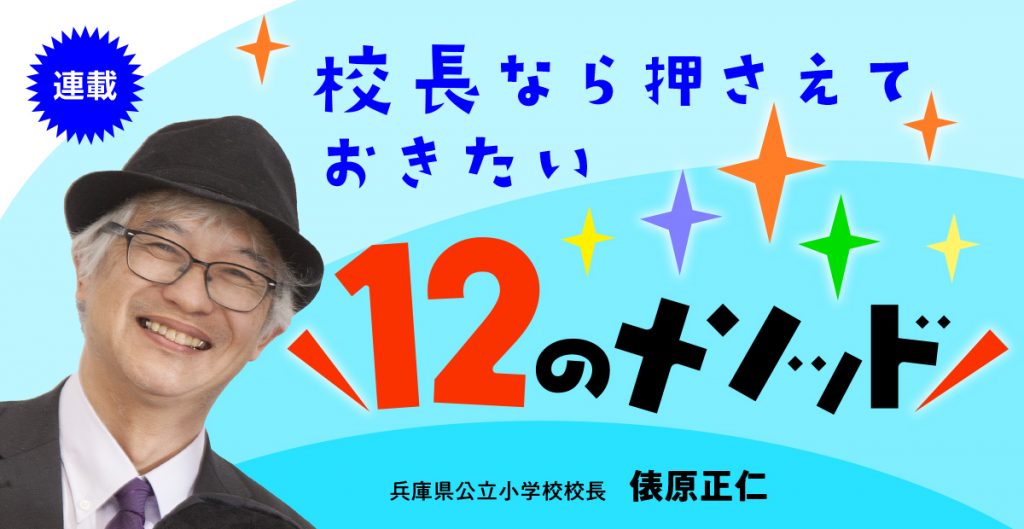
新任や経験の浅い校長先生に向けて、学校経営術についての12の提言(月1回公開、全12回)。校長として最低限押さえておくべきポイントを、俵原正仁先生がユーモアを交えて解説します。第10回は、管理職からのやらされ感を減らし、教職員のやる気がアップする「ボトムアップ」の提案を実現させるためのテクニックを伝授します。
執筆/兵庫県公立小学校校長・俵原正仁
目次
3年連続の研究指定!……ということは、来年も?
初めて、校長として赴任したその年、全学年授業公開という形でICT利活用の研究発表会を行いました。市内だけでなく阪神間や他府県から300名弱の先生方に参加していただき、盛況のうちに幕を閉じることができました。公開授業や研究発表に対するアンケートも好評、たくさんの学びがあったという振り返りも多く、関わった多くの先生方が達成感、満足感を得ることができた1日でした。
ただ、この日に向けて本校職員がかけたエネルギーは相当なものでした。実は、私が赴任する前の年も、この年ほどの規模ではないものの同様のテーマで授業公開を伴う研究発表会を行っていました。この新しい赴任校は、県から3年間ICT利活用による教育の質の向上支援事業の指定を受けていたのです。ということは、次年度が3年目。
つまり、研究指定はまだ続くということです。
指定を受けることで、加配教員が配置されたり、ICT機器について優先的に充実させてもらえたりするなどのメリットもあり、職員から指定を受けることに対して表立って反対の声が聞こえることはありません。ただ、今年から関わっている私でさえ、来年もこれが続くのは、正直しんどいなぁと感じました。そこで、改めて研究指定校の要項を熟読しました。「楽をしたい、なんとか抜け道はないか」という姑息な考えからです。そして、私は、次の一文を見つけました。
「推進校は研究発表を行い、他校への啓発を図る。」
これはいけるかもしれない……そう感じた私は、放課後、授業研究推進担当の先生に話しかけることにしました。
3年連続、授業を公開するのってしんどいよね
「推進校は研究発表を行い、他校への啓発を図る。」
この一文を素直に読めば、「研究を行い、研究成果を発表することで他校へ周知・啓発することができればいい」ということになります。この文中のどこにも、「必ず授業公開を行うこと」とは書かれていません。言い換えれば、「発表の形式は、授業公開という形を取らなくてもいい」と読み取ることができます。(もしかしたら、暗黙の了解的に行間に書かれていたのかもしれませんが、そこはあえて読み取りませんでした。)
そこで、ある日の放課後、授業研究推進担当の先生に、何気ない世間話をするようなテンションで次のように話しかけることにしました。

俵原「3年連続、授業を公開するのってしんどいよね」
担当教員「えっ、まぁ、そうですね」
降ってわいたような校長のネガティブ発言に戸惑いの表情を浮かべながら、彼も同意しました。
俵原「ということで、授業公開をしない方法を見つけたんだけど、聞いてくれる?」
彼の表情が変ります。
担当教員「そんな方法があるんですか?」
俵原「研究指定の要項をもう一度見てみたら、『推進校は研究発表を行い、他校への啓発を図る』って書いているけど、この文のどこにも『公開授業を行う』とは書かれてないんよ。要するに、研究発表をして、他の学校の先生に知らせることができればいいということやろ」
担当教員「まぁ、そうですが……」
俵原「もちろん、何かはしないといけないけど、公開授業に代わるものをすれば、多分、大丈夫だと思う」
そこで、私が提案したのは、セミナー形式の研究発表会です。公開授業を行うのではなく、ICT利活用とプログラミング教育の二つの分科会を開き、そこで本校の研究成果を発表しつつ参加者相手に模擬授業を行い、実際にICT機器の使い方やプログラミングの授業を体験してもらうという形で研究発表会を行ってはどうかというものです。
一方的に研究成果を伝えるだけでなく、模擬授業を行い実際に参加者に体験してもらうという付加価値をつけたのです。これなら新しい試みとして、上から文句を言われることはないだろうという計算がありました。ちなみに、模擬授業などは、全て本校の先生方が行います。
俵原「このセミナー形式なら、『研究発表を行い、他校への啓発を図る』という点もクリアできるし、授業公開をしないので、子供のいない夏休みに開催することもできると思うんだけれど」
担当教員「それ、面白そうですね」
この提案に彼は食いついてきました。
この時、私が意識したのは決してトップダウン的な提案にならないことでした。実際に、研究発表会を行うのは先生方です。今回のような新しい動きをする場合、多くの先生方が納得した上で行った方が、いいに決まっています。そこで、賛同してくれた授業推進の担当から提案してもらうことにしました。
俵原「でも、このパターンは初めて行うので、勝手が分かっている従来通りの方がいいという意見があるかもしれません。だから、A案、B案という形で、今度の推進委員会で提案してくれないかな」
彼は二つ返事で引き受けてくれました。
かくして、次年度の夏休みに開催した新しい形の研究発表会も、大盛況のうちに幕を閉じたのでした。

