秋は研究授業の季節。研究授業で校長が行うべきこと|校長なら押さえておきたい12のメソッド #6

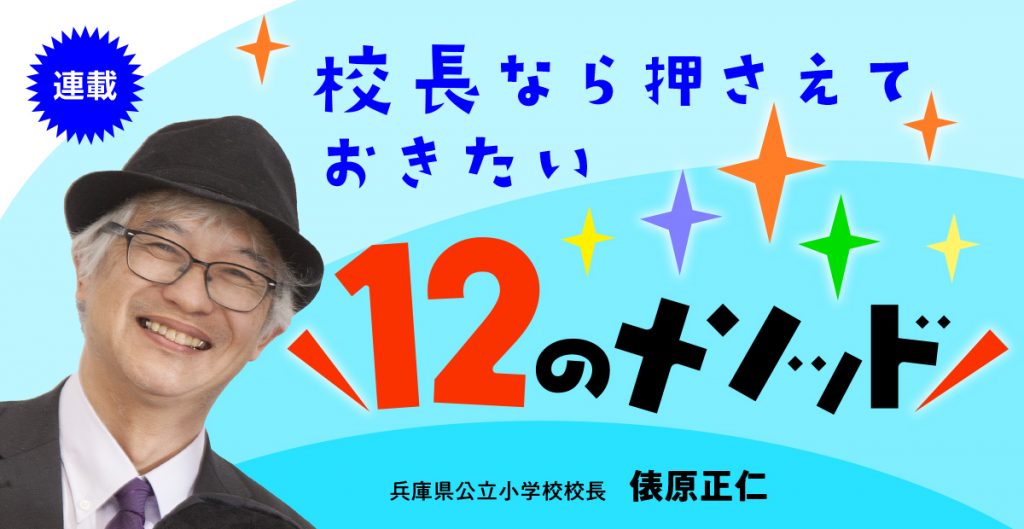
新任や経験の浅い校長先生に向けて、学校経営術についての12の提言(月1回公開、全12回)。校長として最低限押さえておくべきポイントを、俵原正仁先生がユーモアを交えて解説します。第6回は、研究授業における校長の役割と所作を取り上げます。
執筆/兵庫県公立小学校校長・俵原正仁
目次
はじめに~2学期は、研究授業の季節です~
まだまだ残暑厳しく、秋っぽさを感じることもありませんが、秋は確実に近づいています。そして、秋と言えば、頭に浮かぶのが「食欲の秋」「スポーツの秋」「読書の秋」という定番フレーズです。先生目線で言えば、運動会や学芸会など多くの行事が行われる2学期は「行事の秋」という言い方もできそうです。
さらに、私の場合、「行事の秋」のほかにもう一つ「研究授業の秋」という言葉も頭に浮かびます。全国大会規模の研究発表大会から学年公開のみの校内研究まで、大小さまざまな研究授業の多くが2学期に行われているからです。
そこで、今回は「研究授業の秋」に向けて、管理職の立場からの研究授業との向き合い方についてお話しします。しばし、お付き合いください。
気持ちよく講師の先生をお迎えしよう

自分の学校に講師の先生をお呼びする場合、研究会当日、講師の先生の接待は管理職の仕事になります。講師の先生に気分よく話してもらうことができれば、そのぶん話の質も高まります。ぜひ、がんばって接待しましょう(笑)。そのために、私が意識している押さえどころが二つあります。
一つ目の押さえどころは、
講師の先生を予備知識0(ゼロ)でお迎えしない
ということです。授業研究推進の担当が講師の先生を依頼した場合、校長は講師の先生のことをよく知らない場合があります。にもかかわらず、講師の先生が学校に来られたら、はじめにお迎えをするのは多くの場合校長です。その時、何の予備知識もなく会話をすることだけは避けてほしいのです。
予備知識がなければ、当然、当たり障りのない会話しかできません。それよりも、開口一番「先生の新しい本を読ませていただきました。特に印象に残ったのは……」とお迎えする方が、講師の先生からの印象が100倍よくなります。ウェルカムな雰囲気で迎えられれば、講師も人の子、やる気もアップするはずです。「よし、いっちょやったるか」と気合が入ること間違いなしです。
私の場合、講師の先生に著書がある場合は、一番売れている本と最新の本の2冊は目を通すようにしています。また、その講師の先生を呼びたいと言ってきた先生から情報を集めることもあります。「〇〇先生から話を聞いています。今日は、○○についてお話をしてくださるということで楽しみにしていました」という感じでお迎えします。
二つ目の押さえどころは、
講師の先生の話を否定しない
ということです。「〇〇先生の言うことは間違っています」というようなド直球の否定をすることはさすがにないでしょうが、話の途中に首をかしげてみたり、終始硬い表情で話を聞いていたりしたことはありませんか。これらの行動も講師の話を否定していることになります。
特に、講師の先生が自分より若い場合、無意識の内にこのような態度をとってしまいがちです。私の年齢も大幅アップしているので、最近は失礼なことをされることはありませんが、私も40代ぐらいの時に講師として呼ばれた際には、何度かこのような対応をされたことがありました。自分の力量の方が上だと感じたとしても、それを表に出すのは本当に大人げないことです(そもそも、本当に自分の力量の方が上なのでしょうか。そう感じているのは自分だけということは、ありがちです。そして、何よりも「自分の方が上だ」とひけらかすことは、「人間力としては下だ」と自ら宣言するようなものです)。
以上のことは、「できる校長のメソッド」というようなものではなく、講師というゲストをお迎えするための最低限のマナーというようなものですので、多くの校長先生はすでに意識していることかもしれません。釈迦に説法的な感じもしますが、(特に上記の黄色下線のようなことは)自分でも気付かないうちに行っていることもあります。自戒の意味も込めてお話しさせていただきました。

