「会食恐怖症」とは?【知っておきたい教育用語】
人前で食事することや他人との会食において、過剰にストレスを感じてしまう「会食恐怖症」。発症の原因の多くが、学校給食による完食指導にあると指摘されています。
執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム
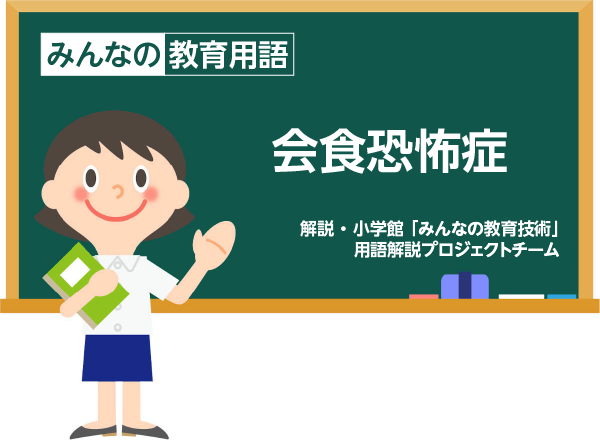
目次
給食の完食指導によって、会食恐怖症を発症するケースが多い
【会食恐怖症】
人前で食事することや他人と食事を共にすることなど、社交場での食事に対して強い恐怖や不安を感じる症状のこと。社交場での食事によって、震えや吐き気などの症状が出ることが特徴。
会食恐怖症は、社交不安障害(他人から注目される状況で過剰なストレスを感じ、社会生活に支障をきたす精神障害)に分類される病気で、子どもから大人までどの年代でも発症する可能性があります。
発症の要因は様々ありますが、特に大きく関わっているのが、学校給食における「完食指導」であるとされています。
「給食を残してはいけない」というプレッシャーや食べきることの強要などから、給食の時間に過度の緊張感が生じてしまい、食べ物がのどを通らなくなってしまったり、口にすると吐き気をもよおしてしまったりするなど、嚥下に悪影響を及ぼします。また、会食恐怖症を抱える人々の中には、給食の時間を苦痛に感じ、不登校になってしまったというケースも多くあります。
学校給食における食の指導とは
文部科学省「食に関する指導の手引-第二次改訂版-」(平成31年3月)における、「第5章 給食の時間における食に関する指導」では、学校給食による、子どもたちが目指す資質・能力に関して、次のように定義しています。
小学校では、例えば、望ましい食習慣の形成を図ることの大切さや、食事を通して人間
関係をより良くすることのよさや意義などを理解すること、給食の時間の楽しい食事の在
り方や健康に良い食事のとり方などについて考え、改善を図って望ましい食習慣を形成す
るために判断し行動することができるようにすることが考えられます。そのような過程を通して、主体的に望ましい食習慣や食生活を実現しようとする態度を
文部科学省(PDF)「第5章 給食の時間における食に関する指導」
養います。
中学校では、例えば、健康や食習慣の正しい知識が大切であることを理解し、給食の時
間の衛生的で共同的な楽しい食事の在り方等を工夫するとともに、自らの生活や今後の成
長、将来の生活と食生活の関係について考え、望ましい食習慣を形成するために判断し行
動ができるようにすることが考えられます。そのような過程を通して、健康な心身や充実
した生活を意識して、主体的に適切な食習慣を形成する態度を育てます。
以上のことから、小学校・中学校のいずれも、学校給食による食の指導には、子どもたち自身が食事を楽しむこと、食事を通して他人と円滑なコミュニケーションを図れることが前提にあります。
そのため、居残りさせて給食を食べさせる、無理やり口に詰め込むといった行為は、指導ではなく体罰に当たるものであり、絶対にあってはならないことなのです。

