何のための「働き方改革」なのかを問い直しませんか 【木村泰子「校長の責任はたったひとつ」 #13】

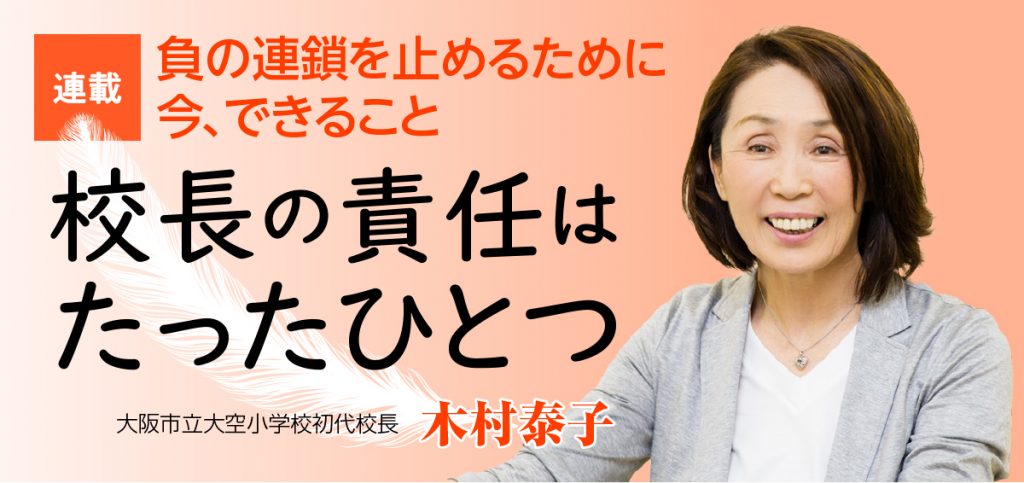
不登校やいじめなどが増え続ける今の学校を、変えることができるのは校長先生です。校長の「たったひとつの責任」とは何かを、大阪市立大空小学校で初代校長を務めた木村泰子先生が問いかけます。
第13回は、<何のための「働き方改革」なのかを問い直しませんか>です。
「働き方改革」は「時短」ではない
最近は全国のどの学校現場でも聞かれる声が、「働き方改革でやりたいことができない……」です。「働き方改革」の目的は「時短」ではありません。
教員は働く時間を制限され、困り感を抱えたままに学校を退勤する。自宅に帰り、その困り感を一人で抱えながら悶々と過ごし、翌日は足取り重く出勤する。
学校行事をはじめとして、やってみたい活動や子どもたちと考えたことを実現したくても「働き方改革」の名のもとに、却下され、どんどん縮小される。
新たな取組や今必要な学びなどについて提案しても、教員同士が「働き方改革」を理由に挙げ、前例踏襲を誇示しようとする傾向が表れてくる。どれだけ必要なことだとわかっていても、「働き方改革」をできない理由に挙げられると、黙ってしまう。
また、保護者は、「働き方改革」を錦の御旗にできない理由を挙げてくる学校に対して、(どうせ、言ってもだめだから……)とますます学校に対する信頼を失っていく。
このような大人たちの出すシャワーを子どもたちは全身で浴びています。 このあたりで少し立ち止まって、何のための「働き方改革」なのかを問い直しませんか。
「働き方改革」の目的は
「働き方改革」は手段です。現行の「働き方改革」は手段が目的化していませんか。
「働き方改革」の目的は、学校で働くすべての教職員が「働くことが楽しい」と感じる環境をつくることにあるのではないでしょうか。少々勤務時間を超えても、働くことが楽しかったら「教員の仕事」はブラックなどと言われないはずです。
教職員が活き活きと働く学校現場で、そんな大人を目の前にする子どもたちはどうでしょうか。大人にあこがれをもち、「学校って楽しい!」と感じるのではないでしょうか。
保護者は子どもが楽しんでいる学校に対して「文句」は言わないでしょう。
こんな職場をつくるために学校のリーダーのみなさんがまず行うことは何でしょうか。
大人も、子どもと同様に一方的に決められた画一的なルールや規律を守りなさいと指示されることに、決して「やりがい」など見いだせません。子どもと同様に教職員も得意なことや苦手なことはみんな違っています。また、チャレンジしたいことも違います。もっと言えば、一人一人の教職員の置かれている背景も家庭環境もすべて違っています。このような自校のすべての教職員が、自校で働くことが楽しいと思える「職場づくり」はどうすればいいかの問いを投げかけることから始めませんか。
ここで決して忘れてはいけないこと、ぶれてはいけないことは、校長のたったひとつの責任「すべての子どもの学習権を保障する学校をつくる」ことです。

