「こども大綱」とは?【知っておきたい教育用語】
令和5年12月22日に閣議決定された、こども政策の基本的な方針を定める「こども大綱」について、解説します。
執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム
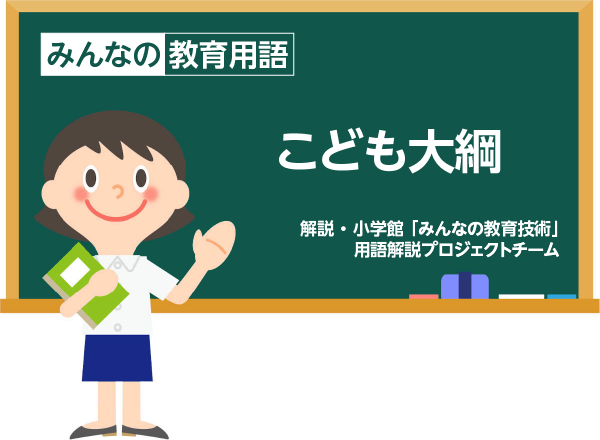
目次
子どもや若者が生きやすい社会を実現するための大綱
【こども大綱】
こども家庭庁が推進する、こども政策を総合的に推進するための大綱。こども大綱に基づいて、こども家庭庁がリーダーシップをとり、政府全体のこども政策を推進することとしている。2023(令和5)年12月22日に閣議決定された。
そもそも大綱とは、物事の基本や大元を指す言葉です。こども大綱は、こども家庭庁が掲げる「こどもまんなか社会」の実現に向けた、基本的な取組を実行していくための方針を定めています。こどもまんなか社会とは、すべての子ども・若者が身体的、精神的、社会的に幸福な生活を送ることができる社会を指します。
こども大綱の閣議決定にあたって、内閣府特命担当大臣である加藤鮎子大臣は、次のようなメッセージを寄せています(一部抜粋して紹介します)。
第1に、目指す「こどもまんなか社会」の姿を、こども・若者の視点で描き、それに対応する目標を定めました。
第2に、こども・若者が「権利の主体」であることを明示するとともに、こどもや若者・子育て当事者と「ともに進めていく」としました。
第3に、政策に関する重要事項について、こども・若者の視点でわかりやすく示すため、こども・若者のライフステージごとに提示しました。
第4に、こども大綱の下で具体的に進める施策について、今後、毎年、「こどもまんなか実行計画」を策定し、骨太の方針や各省庁の概算要求などに反映することにしました。
第5に、こども・若者、子育て当事者を始めとする様々な方々から、対面・オンライン・チャット、パブリックコメント、アンケート、ヒアリング、児童館や児童養護施設への訪問など、様々な方法で意見を聴き、いただいた意見を反映するとともに、こどもや若者にもなるべくわかりやすくフィードバックしました。
こども大綱は、全ての子どもと若者がウェルビーイングの向上を図っていけるよう、子どもと若者の意見を尊重することはもちろん、子育て当事者の意見も踏まえ、効果的な政策を推進していくための大綱なのです。

