授業中、校舎内をうろうろしよう|校長なら押さえておきたい12のメソッド #4

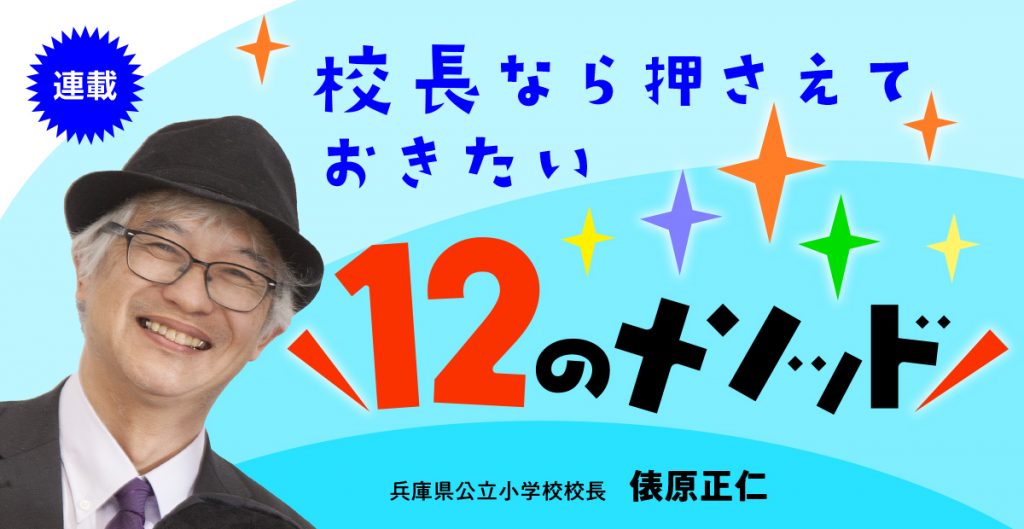
新任や経験の浅い校長先生に向けて、学校経営術についての12の提言(月1回公開、全12回)。校長として最低限押さえておくべきポイントを、俵原正仁先生がユーモアを交えて解説します。第4回は、「授業中、校舎をうろうろしよう~学校運営上メリットしかない簡単にできること~」を取り上げます。
執筆/兵庫県公立小学校校長・俵原正仁
目次
校長の仕事って何?
低学年の子からよく聞かれる質問の1つに「校長先生はどんなお仕事をしているんですか?」というものがあります。
みなさんは、なんと答えていますか?
私は、毎回この答えに詰まります。直近の答えは「みんなや先生たちが笑顔で過ごせるようにいろいろなことをしているんですよ」でした。なんともふわっとした回答です。「いろいろなことって何?」とさらに突っ込まれると困るところですが、続いて「好きな食べ物は何ですか?」に話題が移り、幸いにも事なきを得ました。
それにしても、子供にとって、校長の仕事ほど謎に包まれたものはないのかもしれません。私も子供の頃は、校長先生の仕事は、「朝会で話をすること」と「お花の世話をすること」だと思っていました。当時の校長先生がいつも土をいじっていたからです。そんな俵原少年が今の私を見たら、校長先生の仕事は「朝、門であいさつをすること」「朝会で話をすること」「授業中、校舎内をうろうろすること」になるはずです。今回は、その中から「授業中、校舎内をうろうろすること」についてお話しします。口の悪い6年生からは「校長先生、暇なん?」と言われることもありますが、私にとっては、学校経営上、なくてはならない重要な位置を占める校長の仕事になります。
うろうろすることのメリット
なぜ、重要度が高いのかというと、それだけのメリットがあるからです。「校舎内の設備や備品の点検ができる」「たくさん歩くので健康になれる」「四季を感じることができる」「学校の七不思議に遭遇することができるかもしれない」などなど、細かいものまで上げるとたくさんありますが、今回はその中から大真面目な次の2つのメリットについてお話しします。
・子供とつながることができる
・教師とつながることができる
この中でも、特に私が重視しているのが、「子供とつながること」です。
校長という立場は、意識してつくらない限り、子供たちとつながる機会はほとんどありません。朝、門に立って挨拶をするのも1つの手ですが、子供との絡みはほんの一瞬です。この一瞬で、その子のことが分かるという仙人レベルの力量を持った人はそう多くはないでしょう。また、たとえそのような教育の仙人レベルの人でも、あくまでもつながったと感じているのは、校長側の視点です。朝の挨拶のみで校長先生とつながったという意識を子供たちにもたせることは、仙人レベルでもなかなかできるものではありません。
校長が、自分の学校の子どもたちのことを知っておくことは大切です。ただ、それと同じぐらい、子供に校長のことを知ってもらうことも大切です。「つながる」ということは、お互いを知るということです。……と考えると、朝の挨拶だけでは、不十分ということになります。
「教師とつながること」は、「子供とつながること」に比べれば、重要度はグッと低くなります。ただ、子供と直に触れあっている授業にこそ、放課後の雑談だけでは分からないその先生の人となりが表れます。
私は、授業の力量を見るというよりも、その先生のパーソナリティを知ることに比重を置いています。こう書くと、先生方の一挙手一投足まで見ているように感じるかもしれませんが、子供を見るついでにちらっと見るぐらいです。ただ、授業の中でその先生ががんばっていることを見つけて、放課後に、その内容を伝えることはあります。また、崩壊フラグが立っていたときにはそれとなく話をします。このように「教師とつながる」のですが、あくまでも、メインは子供です。これが逆になると、先生方が毎日校長に査定されている感覚になり、嫌がられますので、ご注意ください。

