一人一人が自立した学習者に! 個別最適な学びの充実 【理科の壺】

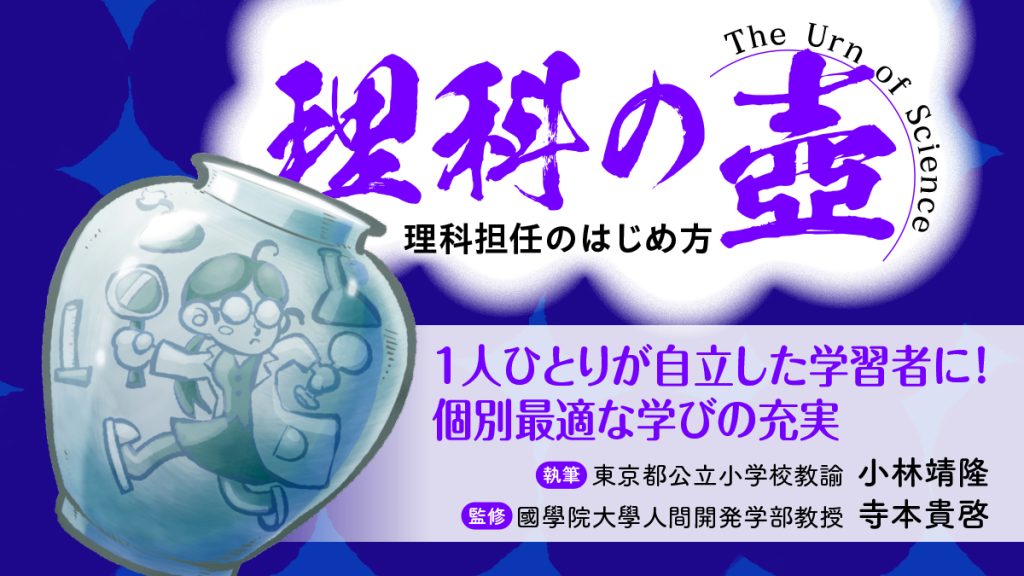
個別最適な学びは、自立した学習者を育てるためにあります。一見、子どもたちが活動的に動いていたとしても、教師の言われたとおりに動いているだけでは、本当の意味で主体的に自立して学習をしているとは言えません。主体的な学びのためには、子どもに委ねる時間を増やすことが重要です。理科の学習においては、「どの場面でどの程度まで子どもたちに委ねられるか」によって、自立した学習者を育てられるかどうかが決まってきます。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/東京都公立小学校教諭・小林靖隆
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1 自立した学習者を育てよう!
令和3年、中央教育審議会で『令和の日本型学校教育』の構築について答申が出ました。そこでは、今までの日本型学校教育を評価しつつ、新しい観点が提示されました。その1つが「自立した学習者」を育むための個別最適な学びの充実です。
小学校理科における「自立した学習者」とは、どのような姿なのでしょうか。そもそも、個別最適な学びとはどのような学習なのでしょうか。
私は、小学校理科における「自立した学習者」とは、理科の見方・考え方を自在に働かせ、問題解決の力を柔軟に発揮して、学び続ける姿と捉えています。
これまでは、児童の思考を深めるための指示や発問を授業者が繰り返していく、という授業スタイルが多かったと思います。
これからは、児童が自分たちに対して自ら働きかけると共に、さらに新たな問題を見出して探究的に学び続けることができる、という、自立した学習者による授業へと転換していかねばならないと考えます。
この授業方法の転換には、「個別最適な学び」の導入が必要です。これは次の2つの視点で構成されています。
①児童一人一人の特性や学習到達に応じて、指導方法・教材や学習時間を柔軟に提供・設定する「指導の個別化」です。書字が苦手な児童はノートではなくタブレットで記録をしたり、耳からの情報の方が優位な児童には音声教材で、目からの情報が優位な児童には視覚教材を用意したりといったハード面の充実といえます。
②児童一人一人に応じた活動や、問題に取り組む機会を提供することで、児童の学習が最適化するように調整する「学習の個性化」です。
私は、この「学習の個性化」こそが小学校理科の授業をさらに変化させる契機になると考えています。
2 全体授業失敗の経験から
これまで理科の授業では、学級全体で問題を設定したり、予想を議論したり、一緒に実験を計画したりしてきました。
このように多くの学習者と共に学ぶことは、客観性を大切にする、という点で非常に価値高いと言えます。しかし、
自分でせっかく問題を見いだしても、結局授業では別の問題をやるんだよな…
せっかく予想をしたのに、みんなで話し合った結果、自分が予想したことを確かめられない実験になっちゃうんだよね…
上記のように、せっかく考えたことが授業で生かされずに問題解決が進んでしまうことで、問題解決の形骸化を起こしてしまった苦い経験が、私にはあります。
その反省を生かし、児童の思考に合わせて学習集団をグループ化したり、枝分かれさせたりすることで、理科における個別最適な学びを充実させ、自立した学習者を育成することができると考えるようになりました。

