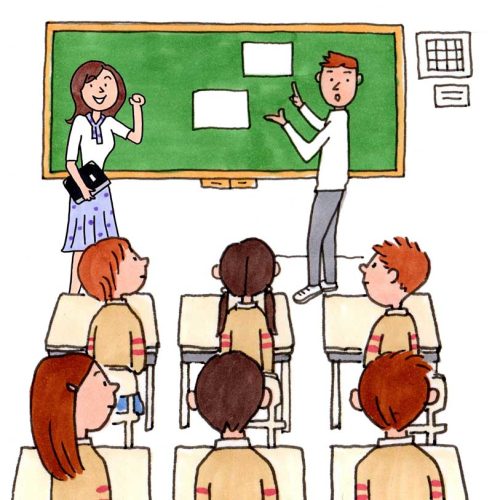専科教員のもつべきマインドセットとは【教科担任制 最前線!! 算数専科を楽しもう】①
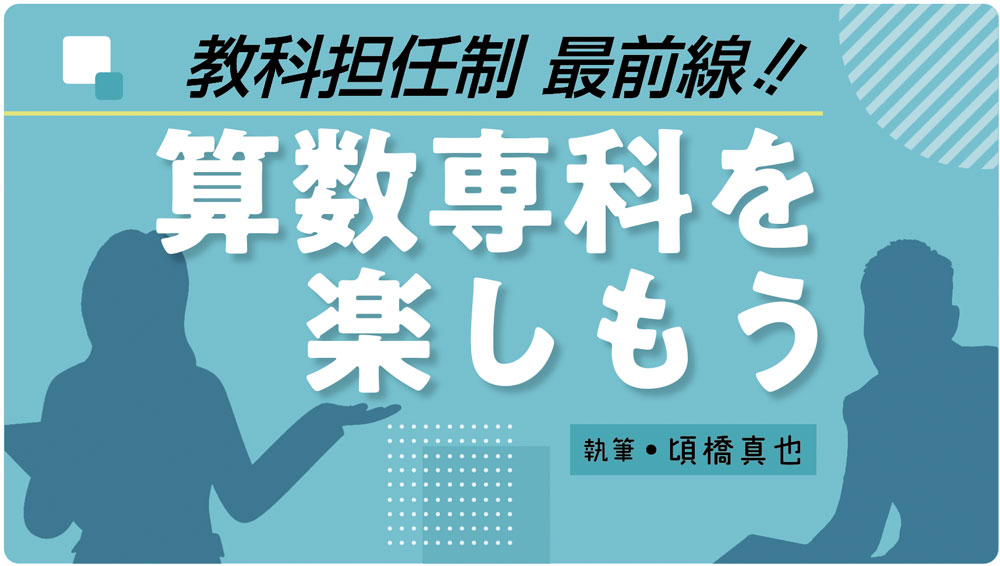
教師の働き方改革が喫緊の課題であるという声が高まる中、文部科学省は、小学校の教科担任制導入を急ピッチで進める方策を打ち出しました。メリットも大いにありますが、新しい制度の導入には現場の戸惑いも少なからずあるでしょう。今年度、算数の専科教員を初めて任された頃橋真也先生が、この1年で分かった教科担任制の課題について深く掘り下げていきます。今回はその第1回「専科教員のマインドセット」について考えます。
執筆/奈良県公立小学校教諭・頃橋真也
目次
教科担任制って何?
私は、今年で教員歴14年を迎えました。これまで13年間、学級担任として1~6年生の様々な学年の担任をしてきました。そして14年目、初めて専科教員になりました。
中教審答申の「義務教育9年間を見通した教科担任制の在り方について(報告)概要」によれば、外国語・理科・算数及び体育の4教科を優先的に専科指導の対象とすることが適当であるとされています。3800人程度の定数改善をめざしす本施策は、当初、令和4年度から4年程度かけて段階的に推進する予定でしたが、令和6年度の予算案でこの計画を1年前倒しで実施し、取り組みをより強化することが決まり、令和6年度に一気に1900人増員して計画を完了させることになりました。
つまり、教科担任制の制度の下、専科教員の役割を担う先生がこの3年間で3800人いるということになりました。しかし、その形態は各自治体や学校の実態により多様なものになると思います。
① 学級担任をしながら、他学級や他学年の特定の教科を担当する教員(教科分担制)
② 学級担任をせず、複数の教科を担当する教員
③ 学級担任をせず、1つの教科を担当する教員
④ 複数の学校で勤務し、1つの教科を担当する教員
他にも様々な専科教員の在り方があると思います。
そして、私は令和5年度から、教科担任制の加配措置を受けて、算数専科として3~6年生の算数を教えることになりました。上記の番号でいえば③「学級担任をせず、1つの教科を担当する教員」ということになります。
私の勤めている学校は、全校児童約120名の小規模校です。そのため、3~6年生の全ての算数の授業コマ(各学年週5コマ×4学年=全20コマ)を担当するという、極めて珍しい教科担任制の経験をすることになりました。
小学校は学級担任の個性という名のカラーと、クラスの児童一人一人が醸し出すカラーが交わることで、学級が築かれていきます。多くの授業を学級担任が担当することから、中学校の教科担当とは、全く異なる学級経営が行われます。
元々、小学校現場では音楽や家庭科などいくつかの教科において、専科教員が授業を担当することは多くの学校であったと思います。教科担任制は、決して新しいものではありません。しかし、教科担任制が全国的に試行された今、学級担任が自分の学級の授業に関わることができる時間が減ることは言うまでもありません。つまり、学級経営は1人の担任が行うものではなくなりつつある時代に突入したということです。
それでは、教科担任制が一般的になりつつある今、専科教員はどのようなマインドセット(心構え)が必要となってくるのでしょうか? 一緒に専科教員としてのマインドセット(心構え)について考えていきたいと思います。
専科教員に望むことって?
はじめに、1つ質問です。
「みなさんは、専科教員にどのようなことを望みますか?」
おそらく、立場によってその答えは変わってきます。学級担任・児童・保護者の立場で考えると、下記のようなものになるのではないでしょうか?
[学級担任が求める専科教員]
① 45分間授業を任せたい。(学級担任がT2として入ることなく)
② 教科担任として、テスト採点や成績付けも含めて全てしてほしい。
③ 授業中の児童の様子など、必要に応じて教えてほしい。
[児童が求める専科教員]
① 学級担任がする授業では得られない、スペシャル感のある授業をしてほしい。
② 楽しく学べる授業をしてほしい。
[保護者が求める専科教員]
① 子どもがその教科を好きになるような授業をしてほしい。
② 子どもが深く学び、学力が付くようにしてほしい。
今回は、学級担任が求める専科の在り方について考えてみます(児童・保護者が求める専科教員の在り方は、次回以降で紹介します)。
まず、学級担任目線で考えると、専科教員が担当する時間は、自分の空きコマとなるわけです。そのため、最も強く願うのは、『専科教員に45分間授業をしてほしい』に尽きると思います。つまり、安心して授業を任せられる専科教員を望むということです。
これは、私が学級担任をしていたときのエピソードです。専科教員が行う授業の際に、その授業の見守りとして(ときにはT2として)入るということがよくありました。多くの場合は、専科教員からの相談を受けて、入り込むことが多かったです。
「頃橋先生のクラスの〇〇さんが、授業中△△△で困っているのだけれど、様子を見にきてもらえない?」とか「私が授業しているとき、クラスの〇〇さんが指示を全く聞いてくれないのだけれど、入ってもらえる?」などです。
先生方もこのような経験はないでしょうか? 一度や二度、子どもたちの様子を見に授業に入るだけならよいのですが、これで授業が安定すると、「これからも入ってもらっていい?」という次なるお願いがあったりしますよね。その結果、本来の自分の空きコマは、気が付けば児童の見守りで毎回授業に入り込みをしたり、T2 として一緒に授業をしたりなど、『授業コマ』へと変化することがあります。
そして、往々にして、このような相談を受ける少し前段階で、子どもたちに異変が起きるものです。「あ~、次は〇〇(教科)の授業や~…」とか「行きたくな~い…」などと、子どもたちから愚痴や相談のようなものを受けるということはないでしょうか?
このようなときは、「どうして?」などと児童から理由を聞きつつも、最終的には「何とか授業に参加してほしいなぁ~」という考えから、児童の手を引きながら授業に連れていっていました。私が若かりし頃は、「空き時間だから、専科の先生に何とか見てもらいたいなぁ」と思い、子どもたちに「どの先生の授業であっても、普段学級で受けているように受けましょうね」などと語って、その場しのぎの対応をしてしまっていました。
しかし、実際には、学級の実態などでどうしても入らなければならないこともあるかと思います。当時の私に欠けていたこと、それは、専科教員の苦労や悩みを考えようとしなかったことに尽きます。
学級担任はどうしても、自分の学級を中心に物事を見てしまいがちになります。学級担任目線で物事を考えることが悪いというわけではありません。ただ、専科教員の先生の立場になって、物事を考えるという視点が限りなく抜けていた気がします。つまり、子どもたちの立場や専科教員の立場に立って物事を考え、子どもたちが行きたがらない理由を真剣に考え切れていなかったように思います。
では専科教員の難しさや大変さとは何なのでしょうか?