個別支援学級での、一人一人の学習進度に応じた理科授業とは 【理科の壺】

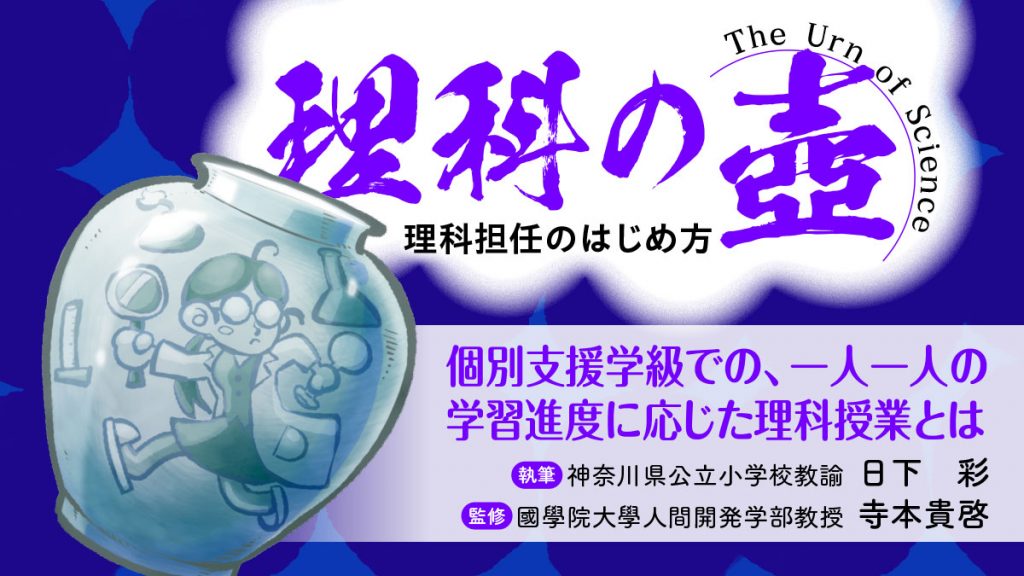
自ら問題解決できる子どもを育てたい、というのが理科の目当てですが、それは個別支援学級でも同じです。「個別最適な学び」と「協働的な学び」が言われているなかで、進度が異なる子どもたちに対して先生はどのように関わっていくべきなのか、また、他の子どもとどのように関わり、学びを深くしていくのか。今回は、個別支援学級における一人一人の学習進度に応じた理科授業について触れていきます。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/神奈川県公立小学校教諭・日下彩
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.一人一人の実態、学習進度に応じた理科授業
私が現在担任している個別支援学級には、1~6年生の子どもが所属しています。ここで子どもたちは学年別ではなく、それぞれの実態に応じて、特別支援学校相当の目標をもって学習を行う「生活単元学習グループ」に分かれたり、生活科の目標をもって学習を行う「生活科グループ」と理科の目標をもって学習を行う「理科グループ」に分かれたりして学習を行っています。
今回は個別支援学級「理科グループ」での学習について、3~6年の生物分野の学習事例を通して紹介します。「個別支援学級だからできること」もありますが、一般級の学習に応用できる部分もあると思っています。

2.一人一人、自分が解決したい問題に取り組む
「生命」の学習で、生き物を取り扱うときは、それぞれの子どもが自分の飼いたい虫やメダカなどを飼育し、解決したい問題に取り組みます。
ある3年生の子どもは、自分が飼っているモンシロチョウの体の構造が気になり、「モンシロチョウのからだはどのようなつくりになっているだろうか」という問題を見いだし、実物や模型を観察して問題を解決しました。
またある5年生の子どもは「アゲハチョウが卵から生まれて、チョウになるまでどのように育つのだろうか」という問題を。ある6年生の子どもは「ビオトープのメダカは何を食べて生きているのだろうか」という問題を見いだし、それぞれ問題を解決しました。
子どもが生き物を育て、観察する中で感じた困り感や疑問から問題を見いだしたので、子どもは解決まで意欲をもって学習に取り組むことができました。
5・6年生は解決方法を自分で発想したり、実験をする中で、納得のいかない結果が出れば何度も方法を見直したりすることができ、問題の解決に向け、生き生きと学習していました。このように一人一人が本当に解決したいと思っている問題を見いだすことで、主体的に学習することができます。それが「個別最適な学び」には欠かせないと考えています。

