「教育虐待」とは?【知っておきたい教育用語】
近年、聞くことが多くなってきた「教育虐待」という言葉。教育虐待を発端とする事件も報告されています。今回は、教育虐待が起こる背景について解説していきます。
執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム
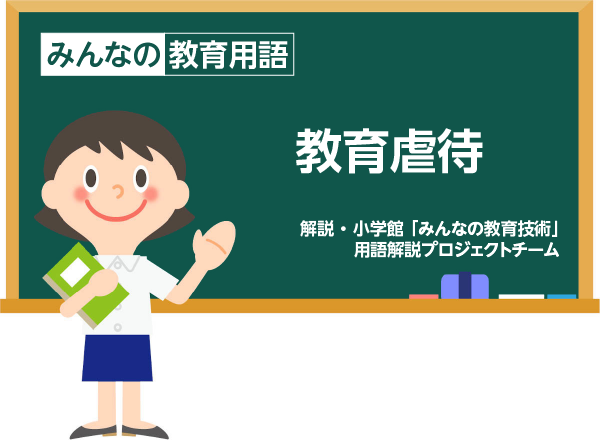
目次
「教育虐待」とは?
「教育虐待」という言葉は、2011年に日本子ども虐待防止学会において報告され、広まってきました。同学会は、教育虐待を「子どもの受忍限度を超えて勉強させること」としています。また、近年では、勉強だけでなく習い事を含む教育全般のことを指すようにもなってきています。
教育虐待の例は、「夜遅い時間まで勉強することを強制する」「テストで親が思った点を取れないと罵倒する」などです。教育虐待に陥りやすい親の特徴の一つとして、自身の学歴にコンプレックスがあることが挙げられます。子どもにはよい教育を受けさせようと「教育熱心」が行き過ぎて、子どもの許容範囲を超えた勉強を強制したり、子どもの自尊心を傷つける発言をしたりすると、教育虐待となってしまいます。
教育虐待の末に親が子どもを殺害したり、逆に教育虐待を受けたとされる子どもが親を殺害してしまうという、痛ましい事件も起こっています。
「教育虐待」が増えている背景
近年「教育虐待」が問題となっている背景には、次の要因があると考えられます。
まず一つは、中学受験の過熱化です。世帯当たりの子どもの数が減っていることもあり、1人の子どもに過度な期待をかけたり、良い学校に入れたいという親の願望が高まっていたりということが考えられます。首都圏模試センターの調査によると、2023年、首都圏の私立・国立中学受験者数は過去最多の52,600名、受験率も過去最高の17.86%となっています。
そしてもう一つは、先行きの見えない時代だということです。昔は、高偏差値の大学に入って、大企業に就職すれば安泰という考え方もありました。しかし、今はそうではなく、今ある仕事もいずれなくなるかもしれません。そのため、英語、プログラミング、課題解決能力など、子どもに求められることも増え、何が子どもの将来のためになるのか正解がわからず不安になり、あれこれ子どもにやらせるという状態に陥りやすくなっています。

