解説|田中博之 生成AIの意義と夏休み中の家庭での使い方<子ども用チェックリスト付き> 【「生成AI利用ガイドライン」徹底解説 #1】

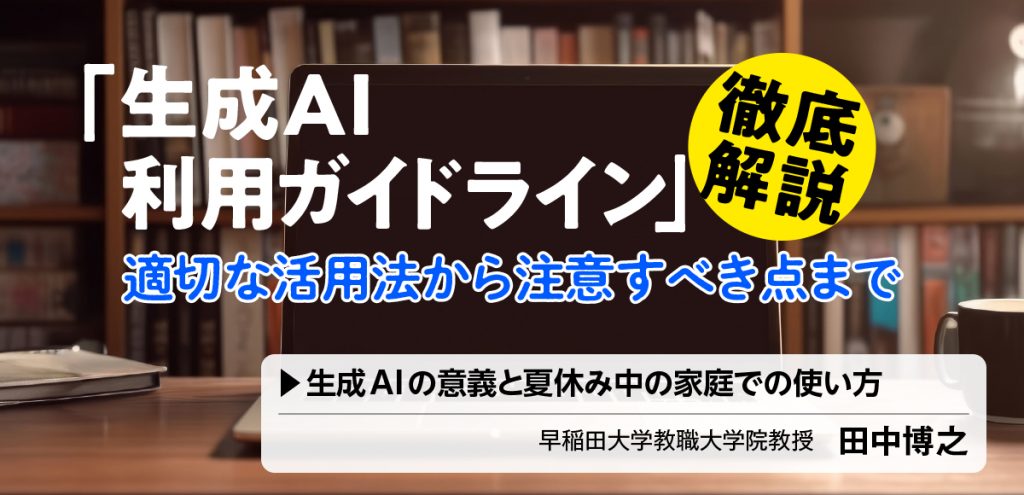
生成AIが世界中で急速に普及していることを受けて、2023年7月、文部科学省は「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的ガイドライン」(以下、ガイドライン)を公表しました。今後、学校で、家庭で、ガイドラインに沿った適切な使い方をしていくためのポイントを、AIの教育利用について研究を進めている早稲田大学の田中博之教授に聞きました。第1回目は、生成AIの意義と夏休み中の家庭での使い方についてです。最後に子ども用のチェックリストがありますので、ご活用ください!

田中博之(たなか・ひろゆき)
1960年北九州市生まれ。大阪大学人間科学部卒業後、大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程在学中に大阪大学人間科学部助手となり、その後大阪教育大学専任講師、助教授、教授を経て、2009年4月より現職。2007~2018年度、文部科学省の全国的な学力調査に関する専門家会議委員。現在、21世紀の学校に求められる新しい教育を作り出すための先進的な研究に取り組んでいる。『NEW学級力向上プロジェクト』(共編著、金子書房、2021)など著書多数。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全3回予定)
●解説|田中博之 生成AIの意義と夏休み中の家庭での使い方<子ども用チェックリスト付き>(本記事)
目次
生成AIの何がすごいのか
文部科学省が作成したガイドラインは、幅広くいろいろな分野の人に話を聞いているためか、メリットやデメリットも含めて、多面的、多角的に書いてあります。非常にバランスのいいガイドラインになっていると感じています。
表紙には、「Ver1.0 機動的な改定を想定」と書いてあります。これは文部科学省としてはかなり異例なことで、取り急ぎまとめた暫定版ということのようです。ですから、まだ十分に議論がなされていない部分もあるでしょうし、すぐにVersion2を出したいのかもしれません。そのせいか、バランスはいいのですが、具体性がなかったり、抽象的に書かれたりしている部分があり、現場の先生方にとっては少々わかりにくいところがあるかもしれません。そのあたりを解説したいと思います。
まず、ガイドラインでは言及されていないことで、少々補足しておきたいことがあります。それは、生成AIを人類が使うことの歴史的な意義です。
人類の歴史を振り返ってみますと、あるものの発明が人間の行動を大きく変え、飛躍的な発展につながった、とされるものがいくつかありました。例えば、蒸気機関車です。人間が歩かなくても安全に、安価で、遠距離の移動ができるようになりましたし、遠い場所へ大量の物資を運べるようになり、物流に革命が起き、経済的に大きく発展しました。このほかにも、自動車、飛行機、コンピューター、インターネットなど、いろいろありますが、生成AIもこれらに匹敵する革命的な発明だと私は思っています。
どういう点で革命的なのかというと、人間の思考、創造性、問題解決力を向上させ、人間の知的な生産性を非常に高めてくれるからです。今後、人類は飛躍的に賢くなる可能性があります。
生成AIのひとつである、ChatGPTが公開されたのは、2022年11月でした。日本でAIの研究が始まったのは、今から約40年前だと言われています。40年の時を経て、私たち一般市民も使えるAIがようやく登場したのです。それからさらにバージョンアップしたGPT-4が2023年3月、有料版で登場しました。私がGPT-4を使ってみて感じたことは、教授や准教授と話をしているかのような、高いレベルの対話が非常に自然な日本語や英語でできるツールであるということです。私はこの3か月ほど、毎日使っていますが、教育学の専門家である私でも、GPT-4と対話する中で、知らなかった視点や観点、アイデアに出合えることがあります。
学校の先生が使うメリットは?
先生方が生成AIを使うメリットは、2つあります。1つ目は、教材づくりの面で、素晴らしいアイデアを出してくれますので、知的生産性の向上が期待できることです。例えば、これまでは深い学びのためのレベルの高い教材づくりをあきらめていた先生であっても、ChatGPTを適切に使えばクリエイティブになれますので、学習指導要領の趣旨に沿った教材が短時間でできます。多くの先生方がレベルの高い教材をつくれるようになれば、学習のレベルも上がるでしょう。そういった意味では、学習指導要領の趣旨を徹底できる可能性が出てきたといえます。
2つ目は、「働き方改革」を推進してくれることです。単純な繰り返しの知的作業に、今まで1時間かかっていたのが、10分で終わるようになるかもしれません。通知表の評価文の作成や学級通信づくりも、短時間でできるようになり、負担が減る可能性があります。

