文部科学省 教員勤務実態調査(令和四年)出る! 待ったなしの働き方改革に、チーム学校で挑もう!

文部科学省から教員勤務実態調査(令和四年)の結果が発表されました。以前よりはだいぶ改善が見られますが、いまだに「時間外勤務45時間超」の教員が8割以上という実態です。課題も山積みです。管理職(教頭)、学校現場最前線(ミドルリーダー・ベテラン層)、若手教員の3つの視点から、これから対策していけることを考えてみましょう。疲弊している学校や教職員に一刻の猶予もありません!
【連載】がんばれ教頭クラブ スペシャル
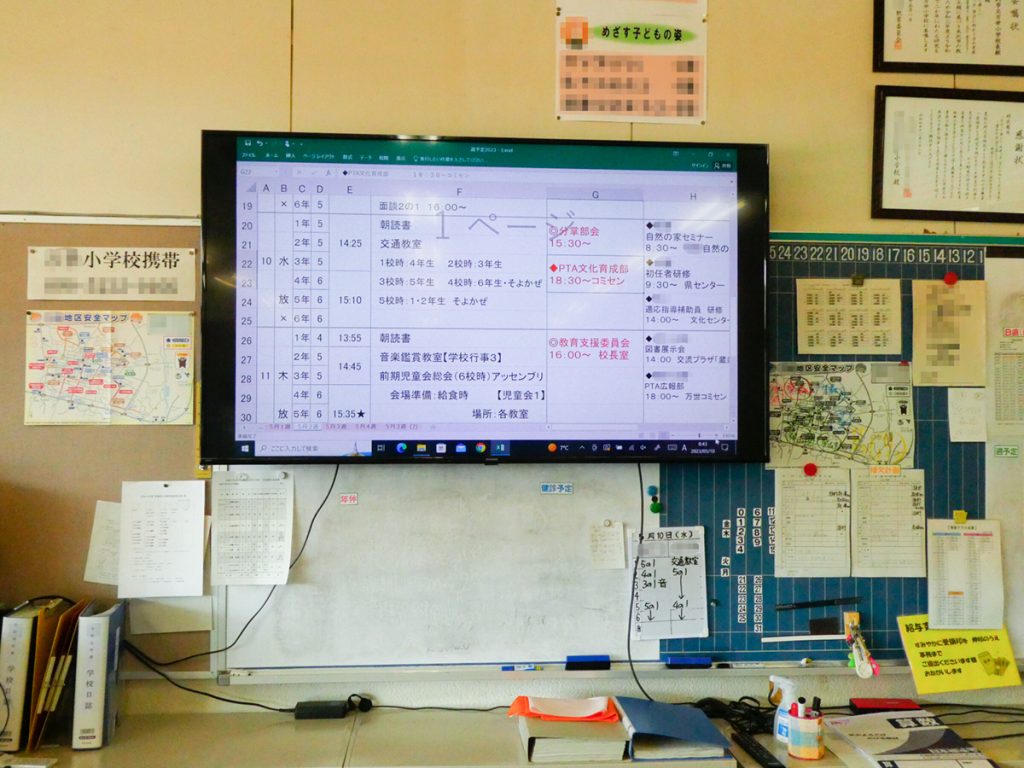
目次
1 教育指導行政からも本気のメッセージ
文部科学省からの実態調査に前後する形で、過日、わたしの勤務地の全県校長会会議でも、教育指導行政担当者から、働き方改革への強い要請があったそうです。
目に見えること…つまり具体的な姿を示すことや数字で証明することが、今後必要になってきます。
管理職の過労死、教職員のメンタル面での体調不良が、身近でどんどん増大しています。
自助努力でできることは、管理職が先頭に立って進めていきましょう。学校の教職員が心身整った状態で児童に接していけるようにすることが、児童の健やかな成長のための最低限の条件だからです。
2 管理職(教頭)ができること
① 配り物改革
学校のせんせいはマジメなので、学校に持ち込まれる配付物を、ちゃんと配ろうと対応される方も多いのではないかと思います。
しかし、担任が学級の児童分を数えて振り分け、帰りの会で配付したり、チラシの内容に関する問い合わせが学校に来て、担任が対応する…といったこともしばしば。これは本来必要のない労力です。
こういったチラシを配布する必要性から、管理職のレベルで精査しましょう。
まず、判断をしやすくするための大方針を決めます。
原則的に、教育委員会の公認や推薦がないものは取り扱わない
というのが、分かりやすくてオススメです。その上で…、
ア 公共機関からのお知らせについては、配付の要請があった時点で、当該機関に各学級の人数を知らせ、学級ごとに配分してもらったもののみを受託します。
イ イベントや映画のチラシなどは、各児童に配付せず、置きチラシにします。
ウ 寄付行為のようなものは、そもそも学校として取り組むべきかきびしく精査します。
★以上で、かなりの労力が削減されます。
② 会議改革
ダラダラ会議はやめたいです。
そもそもこのような会議は、議題の選別がなされていないことが多く、会議に対する教職員の意識が変わっていないことが要因。こんな改革をしていきたいです。
ア 議題を整理する
会議が長引く要因の多くは、協議事項(児童のために教育活動をどう設計していくか)、報告事項、連絡事項の選別がなされていないことです。こんなポイントで進めてみます。
まずは、会議にかける議題を選別する大方針から。
職員会議は協議することのみ。
…と、このくらい、思い切ってみてはどうでしょうか。その上で…。
●報告事項や連絡事項は、週1回程度の手短な打ち合わせを設け、必要最小限の人数で行いましょう。
●行事運営などについては、まず担当者がマニュアルを作成します。それを会議前に全員で共有し、会議の際に読む時間を取らなくていいようにします。各人はマニュアルを事前に確認し、疑問点や変更すべき点があったら職員会議のときに発言します。
●発言は1回あたり1分以内を目標とするよう、管理職が進行係となって皆を促します。
●職員会議での協議事項は、何を協議するのか、具体的に示します。
例えば、運動会において集団競技はどうあるべきか、学習発表会の発表のしかたはどうあるべきかといったテーマを設定し、具体的な原案を出して協議します。
★これだけで、会議に要する時間は半分になります。
イ 意識改革を促す
会議を早く済ませるお膳立てをしたとしても、会議の参加者の意識が変わらなければ、なかなか効果も出ません。
こんな風景を見たことはありませんか?
 「たいへん貴重な役に立つお話を拝聴し…」など、前置きが長い!
「たいへん貴重な役に立つお話を拝聴し…」など、前置きが長い! 整理されていない文書を読む(または読ませる)。
整理されていない文書を読む(または読ませる)。 「ここは大事なので『ねらい』から読みます」など、各人が黙読すれば済むことを音読する。
「ここは大事なので『ねらい』から読みます」など、各人が黙読すれば済むことを音読する。 「こんないいお話を聞いたので、お時間をいただいて報告します」と直接的な関係のない話をする。
「こんないいお話を聞いたので、お時間をいただいて報告します」と直接的な関係のない話をする。
丁寧にコミュニケーションしたい、というのも分かりますが、まずは徹底的に無駄を省き、時間と心の余裕を生み出しましょう。その後で心に響く話をしたほうが、よほど相手の心に届きます。
 報告が必要な場合、必ず3分以内に収める
報告が必要な場合、必ず3分以内に収める  質問は前略でズバリ聞く
質問は前略でズバリ聞く 回答も質問に対することだけをズバリ答える
回答も質問に対することだけをズバリ答える
「会議は参加者全員の大切な時間をいただいているのだ」という意識をもつようにアドバイスをしていきたいです。
★短く整理された質疑応答のほうが、すっと頭に入ります!
ウ とにかくコーチング!
もしかすると、会議の手法や教職員の意識改革については、管理職がコーチしないことがいちばんの問題かもしれません!
法的には職員会議は必置ではありません。最終決裁は校長が行います。そのため、会議を行う意味というのは、職員全員が同じ情報や問題を共有し、同じ方向を向いて学校を経営していけるようにするという、マインド的な部分こそ大事なのではないでしょうか。
「最終決裁は校長なのですから、校長が決めやすいよう事項を収れんするのが会議の目的です」と、言い換えてもよいかもしれませんね。そのために、「ズバリ質問」「要点回答」ということを前提に、みんなをコーチングしていきましょう。
時短や要点化という意味では、みんなで立ったまま会議をするのもよい方法です。
これで、自然と会議時間が短縮できます。
★管理職が重要な鍵を握っています。
③ 校内外アウトソーシング
学校に配置された人材の仕事内容を精査し、教員がしている業務を分担していきます。
印刷業務、学級事務補助、学級費の管理、清掃活動などを依頼していきます。
また、地域の皆さんから学校ボランティアを募り、畑や植栽園、花壇などの管理をお願いするのも非常に効果的です。地域によっては、これが予算化され制度化されているところもあります。
中学校では、部活動顧問をアウトソーシングでどんどん外の専門家にお任せしていますし、同じような発想で小学校も進めていきたいです。
★授業づくりや児童と接する時間へ力をかけていくことができます。
いずれにしても、まずリーダーの管理職が動けば、時間差でフォロワーもどんどん動いていきます!

