本当に必要かつ有益か ー身近な実践のあり方改革ー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第32回】

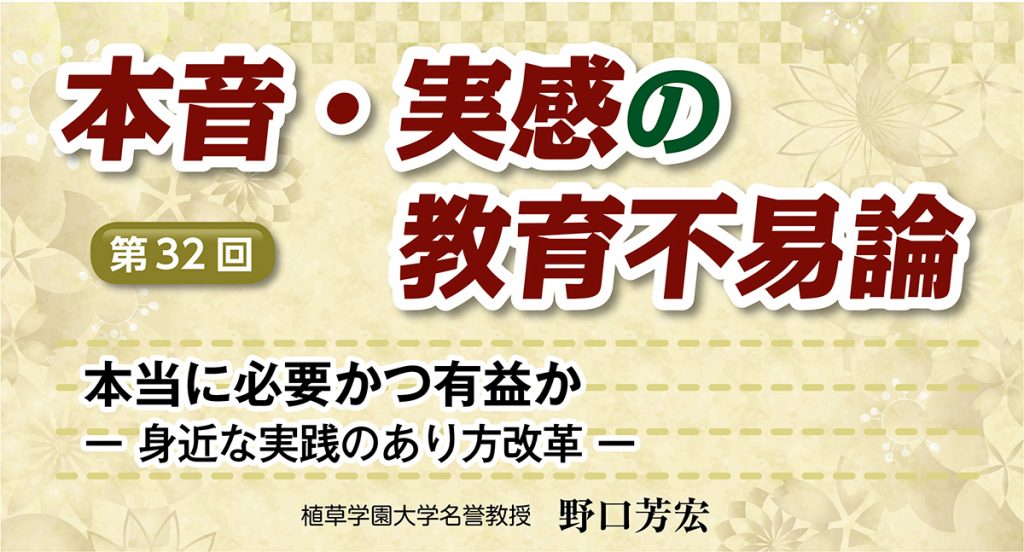
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第32回は、【本当に必要かつ有益か ー身近な実践のあり方改革ー】です。
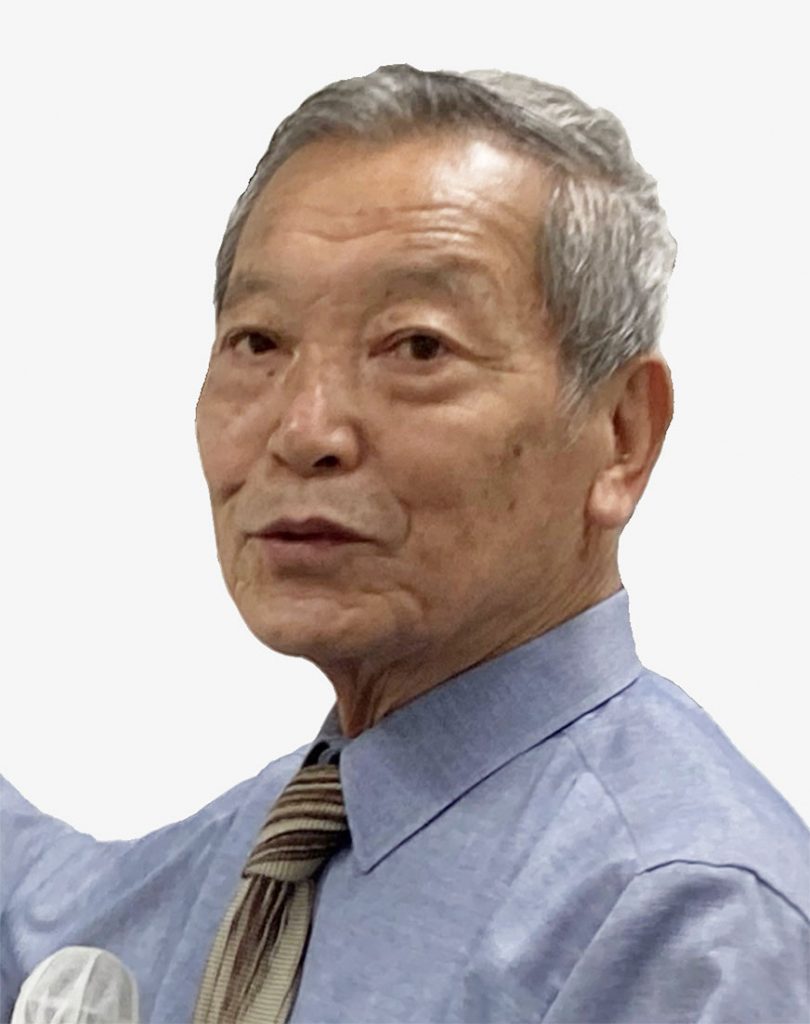
執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
1 「本時のめあて」は必要か
研究授業を参観すると、どのクラスでも「本時のめあて」をまず明示して、授業がスタートする。例えば「ごんの行動と気持ちを考えましょう」というようなことが、黒板の右端に書かれる。ボール紙に予め「本時のめあて」と書いてあるものをマグネットで固定する場合もある。つまり常用されているということである。
同様に「ふり返り」などと書かれたボール紙も用意されていることもある。
これらについては、授業の然るべき折に必ず黒板に書かなくてはいけないと決められていることが多いそうで、授業がパターン化されているという嘆息に何度か出合っている。
すでに半世紀もの昔になる若い頃、授業はすべからく「6過程15ステップ」で進行するのがよい、という主張の下に全学年、全教科の授業展開がこれに従っている学校に勤めたことがある。
6過程を45分間にこなすとなると、1過程が6、7分ということになる。さらに15ステップとなれば、1ステップがざっと3分間ということになる。多少の融通を利かせたとしても、6、7分ごとに過程が区切られ、3、4分ごとにステップが変わり、進行する授業など想像するまでもなく窮屈かつ形式的で、到底現実の子供や教室には合う訳がない。私は随分苦労しつつ勤めた。
この論拠は、ある心理学者が考案した認識のプロセスにある。例えば「導入」という段階では、「前時の学習の想起」をし、「本時のめあて」が示されると、前時と本時との「異同弁別」をしてみるのがよい、と言う。前時に習ったことと、本時に学ぶこととでは、どこが似ていてどこが違うのか、それを分析することによって本時の課題にスムーズに取りかかれるというのである。
前時と本時の異同が分かったら、自分なりの解決予測を立てる。これが「自力解決予測」であり、それに基づいて「自力試行」がなされ、その解決の妥当性をめぐって「相互吟味」をさせれば、「加除訂正」を経て「解決と確認」がなされることになる。これによって、所期の解決は得られたので、次はその学習原理の「転移応用の予想」を立てさせる。かくて、他の問題解決への幅が広がっていくというのである。
一つ一つ聞いていると、なるほど「認識」のメカニズムはそうなのか、と納得できるような気にもなってくる。だが、全ての子供が、全ての学びについて、常にこのように進行するなどということは到底あり得ない。これらは、単なる論理の「逆算」であり、「机上の空論」「絵空ごと」に等しい。
私は、強い違和感を感じて批判発言をしたのだが、「新参者にはまだ分からないよ」と一笑に付されてしまった思い出がある。だが、いつの間にか誰一人それを続けることもなく、その理論は消滅してしまった。
私は、今でも頼まれさえすれば、どこでも授業をし、公開しているが、一度たりとも「本時のめあて」を書いたことがない。ある範囲を通読させた後は、いきなり「なぜごんは、栗を固めて置いたのだろうか。分かるよという人は○を、分からないなあという人は×を書きなさい」というように問い、書かせる。大方の子供が×をつけ、僅かの子供が○をつける。そこで、「分からない人が断然多いね。実は、その答えは本文をよく読めば誰でも分かるんだよ。一緒に考えていこう」という具合に授業の核心に直行する。
導入らしい導入というのは一般に、
- 前の時間はどんな勉強でしたか。
- この時間は何をすることになっていたっけねえ。
- 前の時間の勉強を覚えていますか。
という具合になされることが多い。私はこのような「導入然とした導入」はしない。「本時のめあて」も書かない。
授業の後でしばしば「本時のめあてを書かなかったが、それでよいのか」というように問われることがある。私は「そのことによって、何か不都合なことが生じましたか」と反問すると、「特になかったと思います」という答えが返ってくる。そうなら不要だ。
「必要なこと」はしなくてはいけない。「通読」は必要である。「発問」も必要である。○か×をノートに書かせることも「必要」なのである。
授業にとっては、「必要」なことのみの連続している流れこそが、重要なのである。式次第のように固定した、順序通りに進行することがよいのでは決してない。ところが、学校現場では授業の本質としての「学力形成」よりも、形式化されたパターン化が強く求められているようで心外であり、残念でもある。ある一定のパターンを踏んでいないと、必ず指導者から注意されるのが耐えられない、との声もよく耳にする。
「本時のめあて」を「書くこと」が、「必要」な時もあれば、不要なこともある。必要なら書くべきだし、不要なら書かなくていい。私は「必要の連続こそが良い授業の条件だ」と言っている。本質を忘れた形式的パターン化にこそ警戒が「必要」なのである。

2 「研究の仮説」は必要か
さる市の教育研究所から「研究主任研修」に招かれたことがある。私は、教育研究が重視されている割には、子供の学力向上が具現されていないこと、部厚い「研究紀要」が発行されている割には、その成果が具体的に子供の上に実っていないことに、常々不満と疑問を感じていたので、よい機会を戴いたと喜んで出かけていった。
ざっと30人ほどの研究主任が出席していた。それぞれが各学校の教育研究を担う中堅のベテランである。くれぐれも、実質的な研究の実りによって子供の学力形成、学習意欲、学ぶ喜びに貢献をして欲しいと思った。
さて、開口一番、私は次のように言った。「研究の推進に当たっては、研究仮説が絶対に必要である、と思いますか。○か×をノートに書いてください」「まだ書かない人がいますか」と問い、全員に挙手を求めた。○が全員であり、×はゼロであった。
続けて「御自分の学校の研究仮説が書けますか。書ける人は○、書けない人は×を」と指示の後、挙手を求めると、何と! 全員が×であった。研究主任は、研究計画の立案者であり、熟慮の果てに研究仮説を決めた筈である。本来なら、研究主任たる者は即座に思い出せて然るべきであろう。ところがそうではない。
この事実に注目すべきである。頭の中の観念としてはその大切さが分かったように思えても、実際は、「忘れても何ら支障はない日常」なのである。ここに、学校教育の形骸化、形式化、画餅化、絵空ごと化の実体がある。
研究仮説は、毎年その正しさが研究紀要の上では「実証」され、「検証」されている。だが、さて、それが教師の日常や子供の現実に具現され、結実しているかと言うと、一向にその徴候は見られない。残念ながら「画餅化」「絵空ごと化」されたままである。
そもそも、教育現場の研究について「科学化」が言われ始めたのは、昭和30年代ではなかったか。長野県の教育研究所の著になる教育研究ハンドブックのような書名で、それまでの「参観と感想」による「印象批評」レベルの授業研究のあり方を否定し、科学的、学術的研究手法がとり入れられたことにルーツがある。書名も発行所も、もはや漠然としか思い出せないが、この本は売れに売れ、それから学校の教育研究は手続き上非常に面倒くさくなった。
ある講師は「研究計画」について執心し、「計画ができさえすれば、半ば研究は成功」とか、「研究仮説が決まるまでに半年はかけないと本物にはならない」などと言われた。かくて、手続きや文書の作成は途方もなく面倒になったが、その苦労や努力が現場の日常実践を変え、向上させるまでにはなかなか具現しないまま今日を迎えている。

