「破邪顕正」論と「不破邪」論 ー学び続ける意義と楽しみー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第27回】

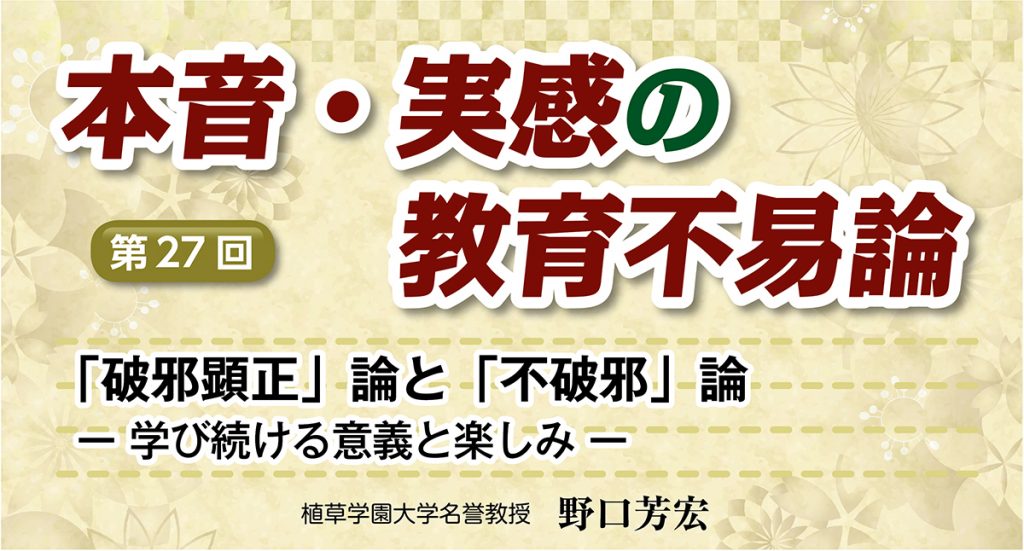
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第27回は、【「破邪顕正」論と「不破邪」論 ー学び続ける意義と楽しみー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
1 「破邪顕正」の実践
私の好きな言葉に「破邪顕正」という四字熟語がある。四つの文字を見てすぐに合点がいった気分になって、長い間「はじゃけんせい」と読み、話してきたのだが、つい先日その誤りを知った。「はじゃけんしょう」と読むのが正しく、出典は仏教用語であるとの事。次のように説かれている。
仏教で、邪説・邪道を打ち破って、正道を明らかにすること。一般に、誤った考え方を打ち破って、正しい考え方を明らかにすること。悪を破って、正義を明らかにすること。(広辞苑)
「顕正」は、「正しい仏の教えを明らかにすること」とも加えられている。
この四字熟語は、教育の本質を端的に表している。「悪を破って、正義を明らかにする」というのは、まさに教育の営みそのものだと言えよう。よく似た言葉に「勧善懲悪」がある。「善を勧め、悪を懲らしめる」というこの四字熟語もまた、教育の本質を言い当てている。そして、明快かつ簡潔である。私の教育実践を振り返ってみると、これらを貫いてきたと言えそうである。
6年生の担任時代、格別体調不良とも見えないのに、体育の時間になると、体調の不良を訴えることが何度かあった子供がいた。「おかしいな」とは何となく感じながらも、黙認をしていたある日のこと、クラスの子供からその子について「体育の時間にテストの答えを見ているようだ」という情報が入った。市販のテストの教師用のものは、正解と判定の基準などが赤刷りにされていたのだが、私はそれを机の横に無雑作にぶら下げていた。
それを見ることは、当然よくないことだから、そんなことをする子はいないと考えていたのだ。不用意、不注意と言えばそれまでだが、ある意味では子供を信頼していた証しとも言える。私は大体そのような考えでずっと過ごしてきていた。
そう言えば、クラスで中の下ぐらいにいたその子のテストの点数が、近頃になって急に高くなっている。それらがぼんやり気になっていたことを思い出した。
早速問い糺してみると、あっさりと白状した。あの高い得点はカンニングの故であったことが分かった。
「そんなに高い点数が欲しければ、お前のテストは全部100点にしてやろう。但し、正解かどうかの点検は一切しない。それでよいか」
と言うと、彼は強く首を振った。
「やっぱり、きちんと正誤を判定してください」
と言うのである。私は、カンニングなどするのは止めろと伝え、相変わらずテストの教師用の赤刷りは机の脇にぶら下げておいた。彼は二度とそのようなことはしなかった。
子供には、今回のことについては私から親に伝える旨を話し、この件を報告した。親は恐縮して詫びながら、成績にこだわりすぎたかもしれないと反省の弁を述べた。
私は、この一件を思い出しつつ、私のとった処置、指導は適切だったと今でも考えているのだが、少し気になる新聞のコラムを眼にしていささか心が揺れている。

2 「破邪」即善ではない
「子供の心の痛みを理解する」というその新聞コラムの大要は、次のとおりである。
某中学校の生徒が、教師の採点が間違っている、と言って自分のテストを教師に見せに来た。その生徒は、他の教師にも「採点ミス」を訴えていたらしく、それが話題になって教師が調べてみると、思いがけないことが分かった。テストが返されてから、生徒が自分の間違いを書き直していたということが分かったのである。
そこで教師が問い糺してみると、生徒は頑として自分の非を認めようとしない。生徒のこのような態度をそのままにしておくのはよくないと考えた担任は、親に電話をかけて事情を説明したのだが、これが親を怒らせるという結果を招いた。「うちの子供がそんなことをする筈がない」と憤慨して、ひと騒ぎになったというのである。
この一件があってから、その学校では採点をした答案用紙をこっそりとコピーをしておくことにしたそうだ。頑として書き直しを否定した生徒が、同様の訴えをまたしてきた。教師は今度こそ明らかに生徒の噓であることの証拠をつかんだと思った。そこで、そのコピーを親にも見せ、生徒にも見せ、白か黒かをはっきりさせようという方向に話が進んだ、というところでひとまず話を止めて少し考えてみたい。
まず、この一連の事件の事実を確認しておこう。中学生は、明らかにテストを返された後に、自分の誤答を抹消して正解に書き換えるという不正行為をした。
教師がその一件に気づいて子供に糺すと、「頑として自分の非を認めない」という事態が大きな問題である。こういう子供の行動があること自体が、教育の荒廃事実なのだ。明らかに、子供は「自分を守っている」。悪いことをしている。噓をついている。それを十分に承知していながら「白を切る」こと、その心のありようが問題なのだ。証拠を表立てない限り「白を切る」ことを通そうとする。そこが最も許し難い一点だ。
コピーを取っておいて証拠を見せれば、さすがに白を切ることはできまいけれど、それによって一件落着ということにはならぬ。教師は「その場」を切り抜けた快感を味わうことはできても、子供を教育したことにはなるまい。「白を切る」自分を見つめさせ、その不純を恥じるようにするのが教育本来のあり方なのである。
子供に問うてみるといい。「君は、正義を愛しているのか。それとも点数を愛しているのか」──と。「点数です」と答えたら、以後「全て100点をやろう」と言えばよい。その無意味さをとくと分からせたい。「正義です」と答えたら、念の為、「確と相違ないか」と確認しよう。そうだ、と言ったら、「では──」と言ってコピーを見せたらいい。彼は白状せざるを得まい。「一度噓をつくと、その噓を隠す為に次の噓を重ねなくてはならなくなる。噓は愚行だ。

