「給特法」とは?【知っておきたい教育用語】
近年、見直しの議論が活発化している「給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)」。その成立の経緯や、問題とされている点について解説します。
執筆/茨城大学大学院教育学研究科教授・加藤崇英
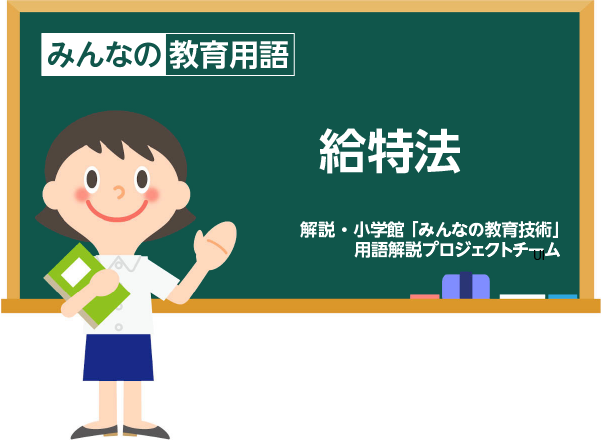
目次
給特法成立の経緯
第二次大戦後、わが国において新たな学校制度のもとで教育が始まると、まもなく、公立学校における教員の労務管理上の課題が明らかとなっていきます。その一つに給与と勤務時間の関係がありました。つまり、公立学校の教員の給与と勤務時間については、一方では労働基準法に照らして時間外勤務手当を支給するという考え方を適用するのか、あるいは他方では教育公務員特例法に照らして教育公務員に時間外手当を支給しないこと(同時にそれは国立学校の教育公務員給与の考え方に準拠するということ)という考え方を適用するのかという、それぞれの取扱いの違い、いわばそうした矛盾の間に置かれていました。そして教員の超過勤務が大きな問題となるにしたがって、この給与と勤務時間の関係も大きな議論を呼ぶようになっていきました。
その後、当時の文部省は、1966年に全国的な教員勤務状況調査を実施します。その結果から、教員について月平均で約8時間の時間外労働を行っていると捉えることとしました。この調査結果を踏まえて、1971年に国公立学校の教員に対し、俸給月額の4%相当の「教職調整額」を支給することとしました。これは1972年度(昭和47年度)から適用されました。なお、その当時の法律は「国立及び公立学校の義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置法」であり、現在は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」です。この法律を略称として「給特法」と呼んでいます。
教員の勤務条件と「教職調整額」
給特法では、教員の「職務」と「勤務態様の特殊性」に基づき、勤務条件を定めるとしています。つまり、教員の勤務については、勤務時間内・外を問わず、また、労働基準法における時間外勤務・休日勤務手当の制度を適用せずに、「教職調整額」を支給するという仕組みです。
公立の教育公務員に時間外勤務を命ずる場合は、以下に掲げる公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令で定められている業務(いわゆる「超勤4項目」)に従事する場合であって、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限られるとされます。
超勤4項目
1.校外実習その他生徒の実習に関する業務
2.修学旅行その他学校の行事に関する業務
3.職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
4.非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
しかし、いわゆる「教員の多忙化」が大きな問題として取り上げられるなど、実際には、教員の業務はとても勤務時間内には収まり切らない状況が学校現場において続いてきたことは周知の通りです。ですが、法律の解釈では、つまり「超勤4項目」に該当しない業務を時間外に行った場合は、そのような業務は、校長の職務命令によらない「教員の自発性、創造性に基づく勤務」とみなされてしまうことになります。
給特法の法規定と関わって、勤務時間についてはこうした運用をしてきたために、教員が勤務時間を超えてさまざまな業務にあたってきたものについては、教員が自主的に従事しているものとみなされてきました。よって、超過勤務として行っている教員の業務については、それは学校が組織として必要なものとしてやむなくやっている仕事なのか、あるいは自主的に自発的にやっているものなのか、それらの区別があいまいなまま、超過勤務という実態がいわば常態化してしまった学校があったことは否定できません。

