明治天皇の六大巡幸に学ぶ【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第15回】

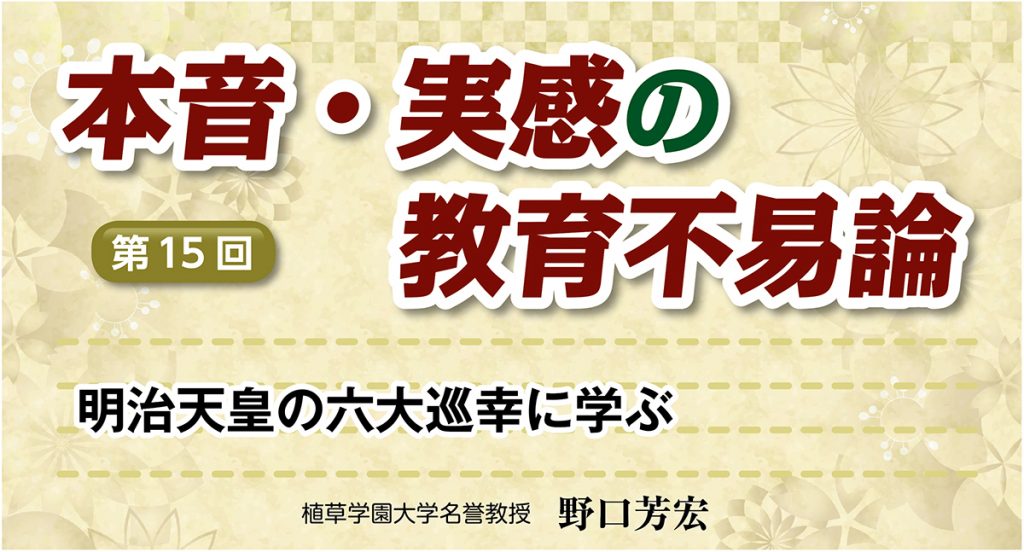
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第15回目は、【明治天皇の六大巡幸に学ぶ】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVD等多数。
目次
1 御巡幸への建白
仁徳天皇に有名な「国見」の御製がある。「高き屋(や)にのぼりて見れば煙(けぶり)たつ民のかまどはにぎはひにけり」(新古今和歌集)
見晴らしのよい高台に登って見ると、家々のかまどから盛んに煙が立ち上っていた。民の暮らしが豊かになった証で誠に喜ばしい、との歌意である。「国見」というのは「国の形勢を高所から望み見ること」だ。古(いにしえ)の天皇は外出をして人々の暮らしぶりを親しく御覧になっていたことが分かる。
だが、江戸時代の天皇は幕府に監視され、京都御所の中から一歩も出られなかったそうである。それだけ天皇の権威を幕府が恐れていたとも言える。
そして、ペリーの来航によって幕府の威信は失墜し、逆に朝廷の権威が増すことになる。孝明天皇が賀茂神社に行幸、参拝された折には、幕府の将軍家茂が馬上で随行した。これは、この国の元首が将軍ではなく、天皇なのだということを国民にはっきりと意識づけることになった。
明治天皇の御代になったので、政府は一般国民にも「天子様」の御存在を明確に認識させ、国家意識を高める必要があった。また、数え年16歳という新天皇にも日本の国の実情を知って戴き、新しい国づくりの英主としての力を備えて貰わねばならない。
明治初年の政府の高官大久保利通は、明治天皇に次のような趣旨の奏上をしている。
「皇居の外に一歩も出られないほど天皇を過度に尊び、御自身も高貴、尊大に構えてきた結果、日本の国情が揺らいできた。仁徳天皇の故事が今も称賛されているのは、親しく国民の中に出られたからだ。外国でも、君主が従者を伴い国中を歩いているのは正しい君主のあり方と申せましょう」
かくて、明治元年3月21日、明治天皇は京都を出発し大阪に行幸され、約50日間滞在されている。五箇条の御誓文布告後1週間というお忙しさである。これが明治天皇の行幸、巡幸の最初の機会となった。
因みに、行幸とは天皇の外出。その外出が何箇所かに及ぶときは巡幸と称している。
大久保利通の奏上を容れて、計画的に各地を巡幸されるようになるのは、明治維新が一段落した明治5年からである。御巡幸は、「朕自(みずから)身骨(しんこつ)を労し心志(しんし)を苦(くるし)め、艱難(かんなん)の先(さき)に立(たち)」と、明治天皇が天地神明に宸翰(しんかん)にて誓われた方針の具現の一つである。

2 第1回の西国御巡幸
明治天皇は、明治5年5月23日から7月12日まで1か月半に亘って近畿・九州方面を巡幸される。70余名の随行の主席随行員は参議を務める西郷隆盛である。一行は、お召艦(めしかん)「龍驤(りゅうじょう)」で品川から海路鳥羽に向かい、まず伊勢神宮に御親拝され、6月13日下関に到着されている。
この折のできごとを『西郷隆盛全集』第3巻には次のように記されている由である。
これらは、全て、『明治の御代』(勝岡寛次著、明成社刊、平成4年8月初版二刷)に記述されているところからの紹介であることをお断りしておきたい。とても私如き菲才には及びもつかない学識に支えられた御労作であり、有難い貴重な文献である。
「小生にも供奉(ぐぶ)を仰(おお)せ付けられ、全行程をお伴しましたが、……下関では、島根県で近来稀な大地震が起り、天皇は県知事を召されつぶさに震災の次第をお聞き取りになった上、御前に於いてすぐさま、取り敢えず三千金を、義捐金として下賜されたところ、夢想だにせぬことで知事は感激の余り落涙して、天皇陛下の御前に打ち伏し、頭を上げ得ないといったことがありました。側にいた者までも落涙しない者はいないという有様で、御巡幸の中でも一番御巡幸らしいことでした」(現代仮名遣いと現代語に野口が抄訳して紹介)
最後に「御巡幸の中でも一番御巡幸らしいことでした」とある。「御巡幸らしい」というのは、恐らく「御巡幸されたからこそ出合うことのできた成果」というほどの意味と解してよいであろう。
著者の勝岡氏は、巡幸先のできごととして次のような紹介も載せている。
「実は、行幸先で善行のあった老若男女を顕彰したり、高齢者に金一封を下賜したり、災害に遭った困窮者に義捐金を渡すといったことは、明治元年の東京行幸時にも行われていたことで、全ての巡幸に共通する事柄です」(p.37)
また、「その意味で御巡幸は、『億兆を安撫し、……天下を富岳の安きに置かん』(前掲書 宸翰)という当初の意図そのままに行われた、と言っていいでしょう」との所感も添えている。同感、共感の極みである。

