「平等と差別」再考【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第5回】

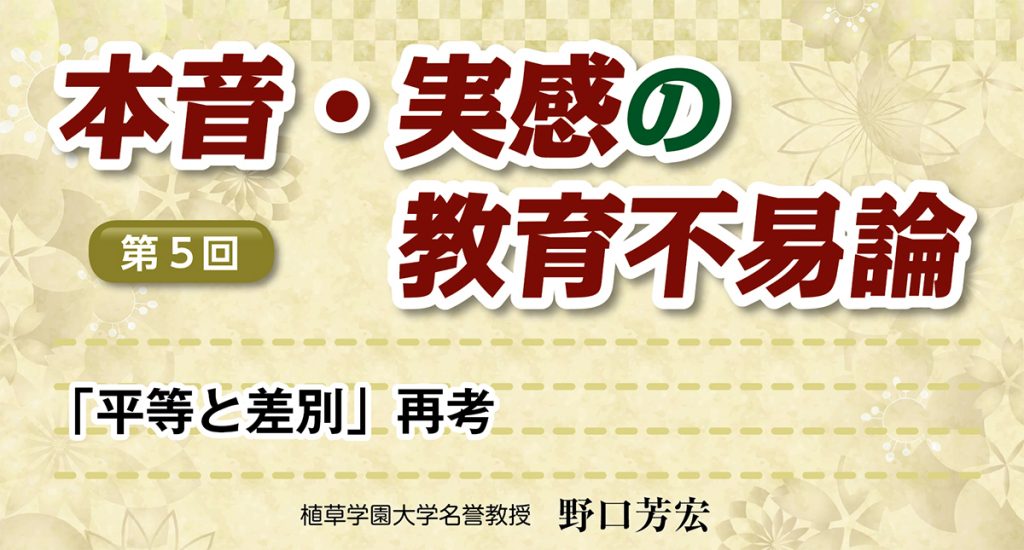
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第5回目は、【「平等と差別」再考】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVD等多数。
目次
1 平和で自由で平等で豊かな日本
私的な思いではあるが、「平和、自由、平等、富裕」の四つが、戦後日本の共通した「夢」であり、理想であり、憧れであったのではないか。この四つのキーワードは、戦前と戦中の日本という国家の対極にあった思想と言えよう。平和論者は捕らえられて投獄され、自由を求める思想は軟弱と軽蔑され、富裕は「贅沢は敵」「欲しがりません、勝つまでは」という合言葉によって抹殺され、平等、対等は家長制や巡査や権力者によって危険思想視され、排撃されていたことなどによっても頷かれよう。
それ故にこそ、敗戦によって「民主主義」「民主化」の美名の下にもたらされた四つのキーワードは、日本国民に熱狂的にとも言えるほど歓迎されて広まり、正しい考え、善なる考え、新しい考えとして国民の間にほぼ定着したのであろう。
このような考え方は、社会的な思潮のうねりの中で当然のように日本の教育界にも大きな影響を与えた。教育界でも、何の疑いも挟むことなくこの四つのキーワードを受け入れ、自然に定着したようである。
そしていつか70年の時を経た。70年の間に四つの夢と期待はいずれもほぼ実現されたと言えよう。少なくとも世界各国の状況と比べれば日本ほど、「平和」で、「自由が保障され」、「豊か」で「平等」な国家はあるまい。近頃貧困家庭の問題が紙面を賑わすこともあるが、少なくとも「餓死」者などは絶無であることを思えば、やはり日本は総じて豊かであることは否めまい。
国民の生活はかなりの程度「安定」し、「快適」であり、「安全」である。
だがしかし、我が国の「この先」を思うと、「今のままでよい」と考えている人は少ないようだ。大方の国民は、この国の「先行き」については不安を抱いていると言っても誤りではあるまい。
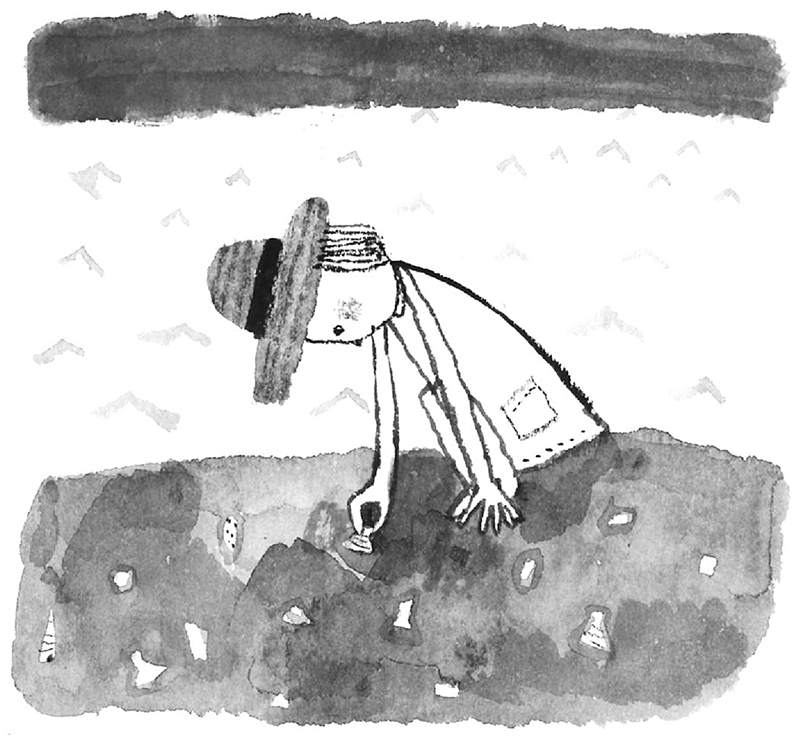
2 「平等」の具現、実現
この「先行きの不安」は教育界にも大きく存在する。私も、大きな不安を抱いているひとりだ。「このまま進んではいけないのではないか」とも考えている。
教育の在り方について「これでよい」とされている現在の風潮の中に潜む不安を少しじっくりと考えてみたい。とりわけ「平等」観への過度の憧れと期待に対する不安を考えてみたい。
戦後は、男女同権、女性の参政権の成立、家父長制の廃止、農村の農地解放、財閥の解体、教育制度の新制化、思想犯の解放、言論の自由等々によって、従来の権威、権力、秩序、系列等が崩され、いわゆる「平等思想」が急速に広まることになった。
それらは大方「光」の部分として国民の間に歓迎され、価値観を変えられ、広まり、定着していったと言ってよいだろう。夫唱婦随、男尊女卑という言葉は封建思想の残滓として死語と化し、師弟関係、親子関係、夫婦関係も急速に対等、平等という波によって変貌を遂げていくことになる。「お上」という言葉も死語となり、今の若い者はこの言葉を知らない。
さて、戦争も70年余の時を経て今がある。平等思想は、果たして人々を幸福に導いたと言い切れるのだろうか。
「平等思想」が生み出した「陰の部分」も大きく存在するのではないか。以下に私見を述べ、読者諸賢の批判を乞いたい。

