理科の学習で使用する、植物の計画的準備のポイント 【理科の壺】

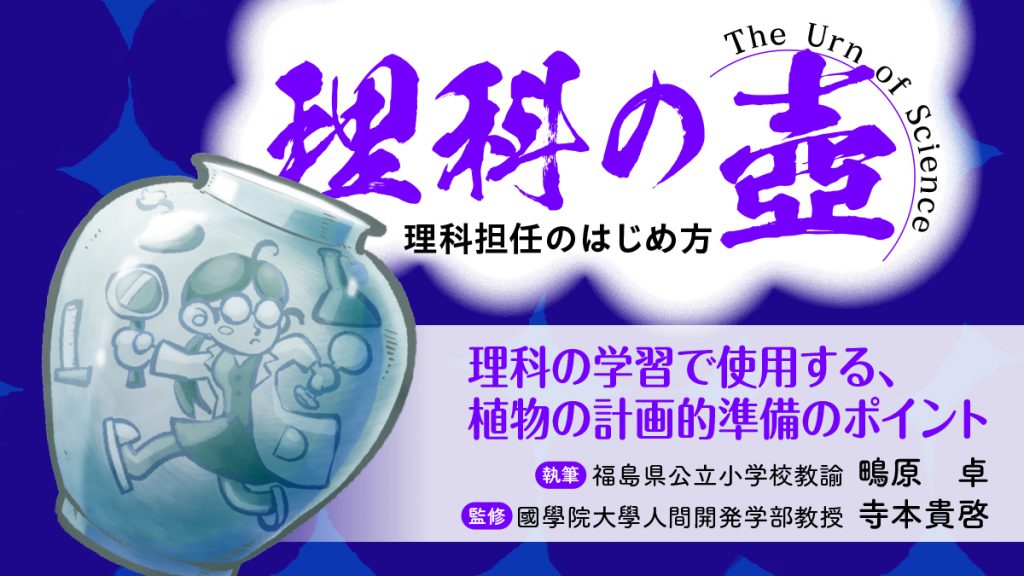
植物を育てる単元は、教科書によって載っている植物が異なるうえ、地域によって植える時期も異なります。授業をいつ行うかによって、逆算して準備する必要もあり、計画的に準備をしなければならない単元の1つです。また栽培方法においても、連作(繰り返し同じ場所で同じ種類を植えること)ができない※ものもあり、こちらも、1年前、2年前くらいまでどの場所で何年生が植えたのか記録し、種類によっては場所をローテーションするなどの工夫も必要になるかもしれません。今回は植物の育成のポイント。うまく育てられるといいですね。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
※連作障害=ナス科、アブラナ科、ウリ科などの特定の植物を同じ場所で何年も栽培していると、その植物が土壌の性質を変えてしまうことで、育ちにくくなる現象のこと。ジャガイモや白菜、大根、キュウリなどが有名で、種類によって1年〜4年休むことで土壌の性質が戻り、また栽培できるようになります。
執筆/福島県公立小学校教諭・鴫原卓
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
理科の学習は子どもたちが「自然に親しむ」ことから始まります。
しかし、いざ植物を扱う単元になった際、事前に植物が準備されていなければ、子どもたちに自然を出合わせ親しませることはできません。今回は、学年ごとの植物を準備する時期や栽培のポイントと、植物栽培と学年のつながりについて述べていきます。
今回は筆者の勤務する福島県を例に紹介をしますが、本稿を参考にしていただきながら、地域やその年の気温や天候に合わせつつ、理科を担当する先生が楽しんで栽培していただきたいと思います。
また、新しく理科主任となった先生は、本稿を基に年間を見通した栽培計画を各学年の先生方へ伝えることで、先生方が見通しをもちながら植物を栽培するためのきっかけになれば幸いです。
1.4年生 ヘチマの栽培のポイント
ヘチマの実が結実しない、小さい実しかできないというお話をよく聞きます。次の視点で見直してみてください。
⑴ プランターでの栽培の場合
ヘチマは土の栄養を多く使用する植物です。プランター栽培の場合は、土に栄養が豊かであることがポイントになります。特にヘチマがよく育つ夏季に追肥を行うことで、より大きな実を結実することができます。
⑵ 畑での栽培の場合
畑でのヘチマの栽培は、マルチシートがけが断然お勧めです。マルチシートをかけることで畑の地温が上がり、肥料の流れ出しが少なくなるので、ヘチマの根付きが良くなります。さらに、水の蒸発を防ぐので、夏場の水やりもあまり必要ありません。防草シートの役割も持つので、雑草が生えてくるのを防ぎ、雑草に栄養を取られることなくヘチマを育てることができます。


⑶ 土は一年毎に土壌改良
ヘチマは土の養分をたくさん使って結実します。ヘチマを植えた後の畑や花壇、プランターの土は栄養不足になっていることが多いので、毎年冬になったら計画的に落ち葉や化成肥料を加えて土壌を改良し、次年度へ引継ぎましょう。
2.5年生 植物の結実のポイント
雄花・雌花のあるヘチマ(雌雄異花)と共に、一つの花の中におしべとめしべのあるアサガオ(両性花)も植えておきましょう。2種類以上の花の結実の仕方の違いを比較することで、子どもたちが植物の共通性・多様性について気付くことができます。
ヘチマの場合、雄花が先に咲きだし、その後気温が少し下がってから、雌花がヘチマのネット上部に咲きます。ぜひ子どもたちと一緒に確認してみてください。

