小1算数「かたちづくり」指導アイデア《かぞえぼうをつかって、いろいろなかたちをつくろう》
執筆/福岡県公立小学校教諭・小野祐揮
編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏
目次
本時のねらいと評価規準
(本時の位置 3/4)
本時のねらい
ものの形に着目し、数え棒で形を構成する活動を通して、いろいろな形を作るとともに、形を作ることに関心をもつ。
評価規準
数え棒を使って、いろいろな形を作ることができる。(技能)

問題場面
かぞえぼうをつかって、かたちをつくりましょう。
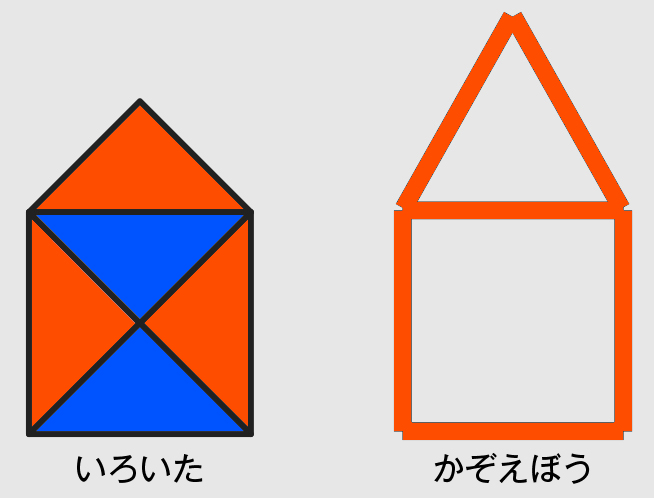
これは、どんな形でしょうか(色板で作った形)。
ロケットだ。
家みたいだ。
では、この形は?(数え棒で作った形)
これも家みたい。
2つの形を見て、違うところはどこですか。
左は色板で形ができているけれど、右は数え棒で形ができています。
形の大きさが違います。
今日は、数え棒で形を作ってみましょう。
本時の学習のねらい
かぞえぼうをつかって、いろいろなかたちをつくろう。
見通し
・数え棒をくっつける。
・数え棒を並べる。
・「さんかく」や「しかく」を作る。
数え棒で作った家の形には、どんな形が並んでいますか。
「さんかく」と「しかく」が、並んでいる。
数え棒で「さんかく」と「しかく」を作っていくと、いろいろな形が作れそうですね。
自力解決の様子
A:つまずいている子
形を構成することが、できない。
B:素朴に解いている子
提示された家の形などを、構成している。
C:ねらい通りに解いている子
形を多様に構成し、作った形を「さんかく」や「しかく」という観点から捉え、説明している。
自力解決と学び合いのポイント
イラスト/佐藤雅枝、横井智美
『小一教育技術』2019年2/3月号より

