小1算数「ひきざん」指導アイデア《10のまとまりを使って12-7を解こう》
執筆/福岡県公立小学校教諭・石丸こずえ
編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井 健一、福岡教育大学教授・清水紀宏
目次
本時のねらいと評価規準
(本時の位置 2/ 12)
本時のねらい
10 のまとまりに着目し、具体物の操作、言葉、式を使って考え、説明する活動を通して、減加法を理解することができる。
評価規準
減加法について理解し、それを言葉や式で表現することができる。(数学的な考え方)
問題場面
やきいもが 12 こあります。7こ たべると、なんこ のこりますか。
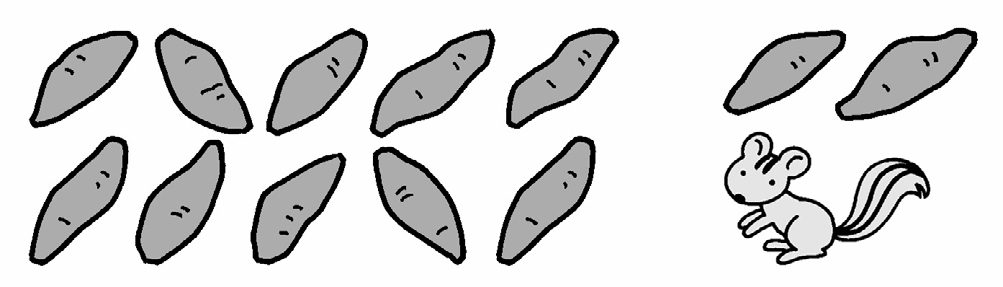
本時の学習のねらい
12 -7の けいさんの しかたを かんがえ、せつめいしよう。
見通し
・答えは、5になりそう(結果の見通し)。
・「10 のまとまり」から、取ればよい(方法の見通し)。
自力解決の様子とそこでの指導の手立て
A:つまずいている子
ブロック操作ができない。
または、ブロック操作を言葉で説明できない。
B:素朴に解いている子
10 から7を取ることなど、一部のブロック操作を言葉で説明する。
C:ねらい通りに解いている子
「はじめに」「次に」「最後に」のように、ブロック操作の過程を筋道立てて言葉で説明する。
ブロック操作と言葉、式を関連付けることで、減加法を理解し、正しく計算することができることをねらいます。
具体から抽象の方向だけではなく、抽象から具体の方向の関連付けも大切にしましょう。
Aの子供については、前時の学習を振り返りながら、減加法の仕組みを確実に操作できるようにしましょう。また、その核心である「10から7を引くこと」を言葉で表現するよう促しましょう。
Bの子供については、問題文に10という数がないことを知らせ、10のまとまりがどのようにできたか、答えの5がどのようにできたかを問い、言葉で説明させましょう。
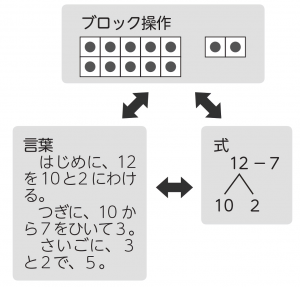
全体発表とそれぞれの考えの関連付け
12 -7の計算をブロックを使って、答えを出してみましょう(ブロックの操作をする)。
イラスト/佐藤雅枝 横井智美
『小一教育技術』2018年12月号より

