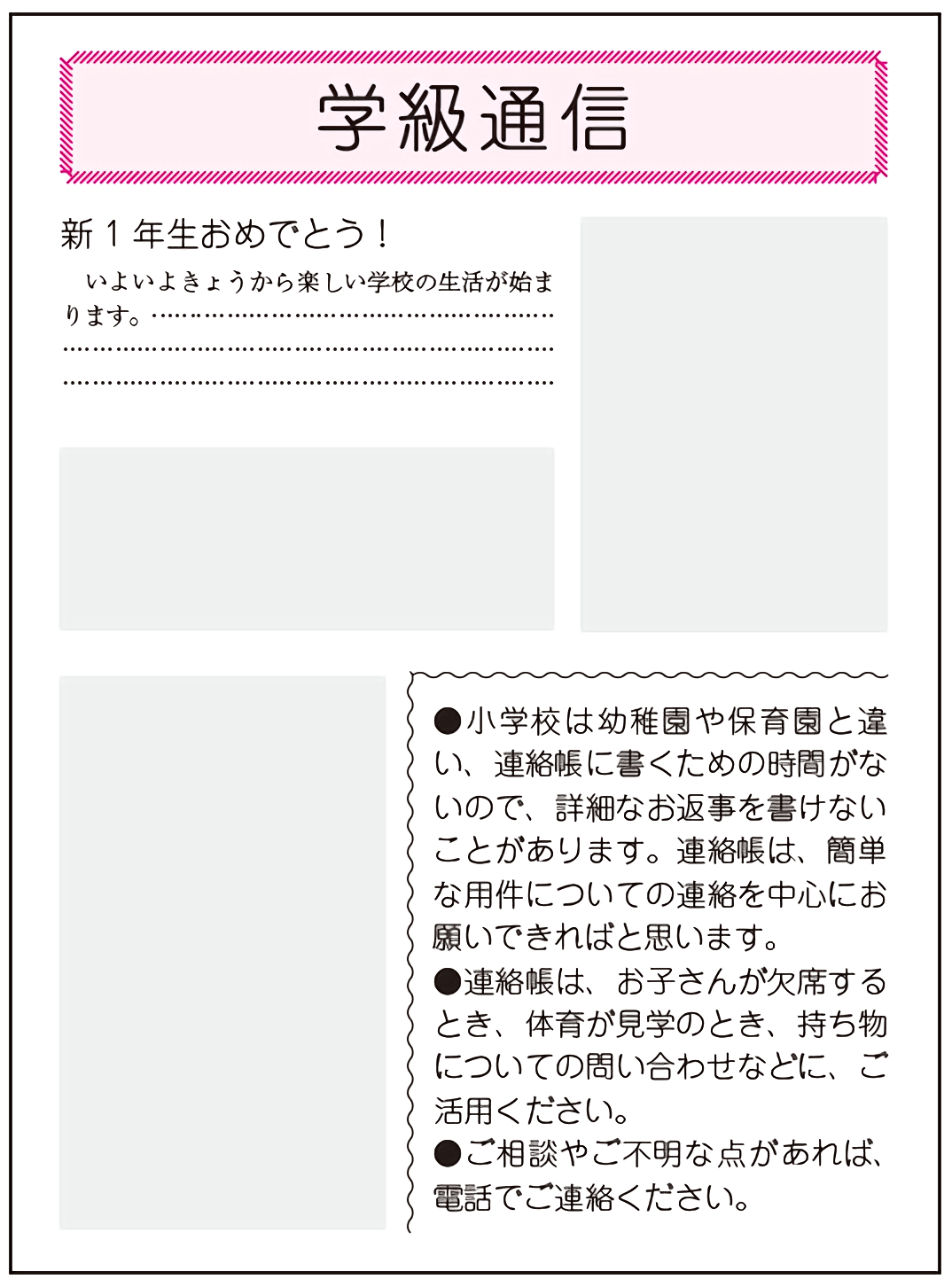ケース別クレーム対応、保護者会…春の保護者対応のキモをまとめます!
春の季節によくある保護者対応を具体例を挙げながらご紹介します。 この記事でとりあげた事例やヒントをもとに、ぜひ保護者とのよりよい関係を築いていきましょう。
執筆/長谷川かほる

目次
1年生入学前後
保護者の不安を思いやって
入学式前のクレームや要望は、入学式後と比べるとそう多くはありません。しかし、どの学校でも前年の秋ごろに実施される新1年生の就学時健診や校長面接などの機会をとらえて、保護者が要望を伝えてくることがあります。また、入学式の何日か前に学校に電話で伝えてくることもありますが、いずれにしても、入学してから担任に要望してくることが多いようです。
♦実際のクレームや要望の例
①「幼稚園のとき、A子のお母さんとうまくいかなかったので、うちの子とA子を絶対に同じクラスにしないでほしい。」(入学前)

②「となりに座っている子がいじわるをしたり、ぶったりする。席をかえてほしい。」(入学から1 〜2 週間後)

③「先生が連絡帳への返事をあまり書いてくれない。」(入学後)
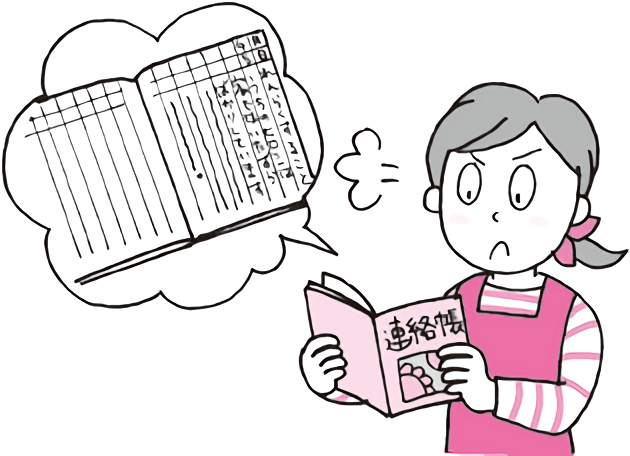
♦学校側の対応として
①について
どちらかといえば、子どもより保護者の問題なので、こうした要望は校長の判断になります。担当者は(入学前で、担任がまだ決まっていないとき)、教頭や校長にそのクレームを伝えましょう。どんな事情でA子のお母さんとの関係が悪くなったのかを支障のない範囲で聴き、子ども同士の関係に影響が出そうであれば、違うクラスにします。しかし、すべてを聞きいれるわけにはいかないので、ときには保護者へ毅然とした態度で、できないことはできないと伝えることも必要です。
②について
入学してから何日かたつと、子どもたちも緊張感が薄れ、友達とのかかわりがでてきます。そんな時期に保護者からの連絡帳の内容で多いのが、この事例のような友達とのトラブルです。とくに、初めてわが子を入学させた保護者は神経質になりがちです。そしてわが子の言い分のみを信じて、担任にクレームをつけてくる人がいます。
こんなとき、一方的に「お宅のお子さんにも原因があります。」などと返事をしてはいけません。まずは、「子どもたち(両者)の言い分をしっかり聞いて指導します。」と伝えましょう。そして、その結果を必ず保護者に伝えることが重要です。ときには、保護者の要望どおりに座席をかえることが必要になることもあるでしょう。しかし、どちらにしても子どもの様子をしっかり見取ることが大事です。そして、必ず記録しておきましょう。
③について
わが子のことを、連絡帳に日記のようにびっしり書いてくる保護者もいます。しかし、担任は一人ひとりの連絡帳にびっしり返事を書く、時間も余裕もありません。そこで、連絡帳の使用目的や受け渡し方法、返事は毎日書けないことなどを、最初の保護者会や学年だより、学級だよりなどで、入学後、早い時期に知らせておきましょう。
クラスがえのあった学年
安心感をもたせることが大事
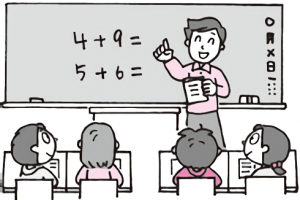
クラスがえがあった学年は、それぞれのクラスが落ち着くまでに少し時間がかかります。また、新学期のこの時期は、子ども同士のトラブルや保護者からのクレームも多くなります。しかし、この時期に保護者への対応をしっかりしておけば、その後の信頼関係の構築がらくになるはずです。とにかくこの時期の保護者には、〝この先生なら大丈夫〟という安心感をもたせることが大事です。
♦実際のクレームや要望の例
①係の決め方(席の決め方)が公平ではない。
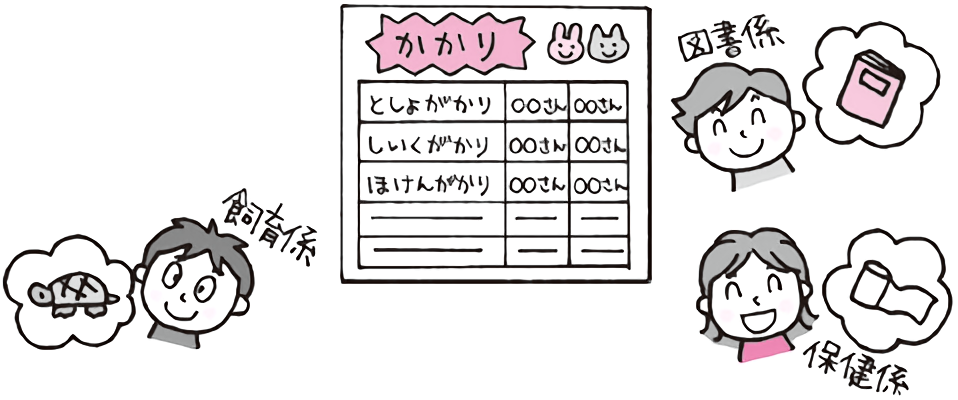
②宿題の出し方について不満がある。(宿題をたくさん出して。出さないで。)

③となりのクラスでは持ってきてよいものが、わが子のクラスではどうしてだめなのか。(シャープペン・蛍光ペンなどの文具類)
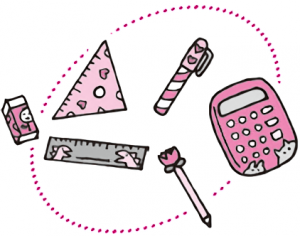
♦学校側の対応として
①について
それまでの決め方と、新しいクラスでの決め方が違うのは当然です。まず、子どもたちが理解できるように決め方のルールを説明し、どの子も納得できて、不公平感をもたせないようにします。子どもたちからそれまでのクラスでのやり方を聞いて、部分的にとりいれるという方法もあります。それでも保護者からクレームがきたら、担任としてどのように考えて係を決め、子どもたちにどう指導したか、明確に説明できるようにしておきましょう。
クレームをつけてきた保護者の子どもに、どんなところが納得いかないのか、あらためて聞くことも必要です。また、誤った解釈をしていることもあるので、その子の思いや感じたことを聞く機会をもつことが大切です。子どもへの対応をしっかりとして、子どもの心を受けとめていれば、ほとんどの保護者は、それ以上にクレームをつけてくることはまずないでしょう。
②について
宿題は家庭学習の習慣をつけるためにも必要です。「宿題を出さないで」という保護者には、宿題の意義や、担任としてどんなねらいをもって宿題を出しているのかを伝えましょう。

それぞれの家庭に教育方針があることを受けとめたうえで、学校としての方針を伝えることが大事です。〝勝手なことばかり言って〟という思いで保護者に対応していると、相手も必ず同じように感じるものです。
また、「もっと多く宿題を出して」という保護者には、宿題以外に自由勉強でよいので、家庭学習に取り組んでほしいと伝えます。少し手間はかかりますが、家庭学習での自由勉強にも赤ペンを入れてあげましょう。
③について
これはクラス単位で決めることではなく、学年または学校全体で決めることです。学習に使わない文具類は、ふつうはどの学校でも持ってきてはいけないというきまりがあるはずです。生活指導部と連携して学校全体で共通理解し、クレームをつけてきた保護者には「学校として決められていることです。」とはっきり答えましょう。また、持ってきてもよいとしているクラスの担任には、保護者からクレームがあったことを具体的に話し、学年として歩調を合わせた生活指導ができるようにしましょう。