「結果の整理」や「結果の共有」の改善と工夫【理科の壺】

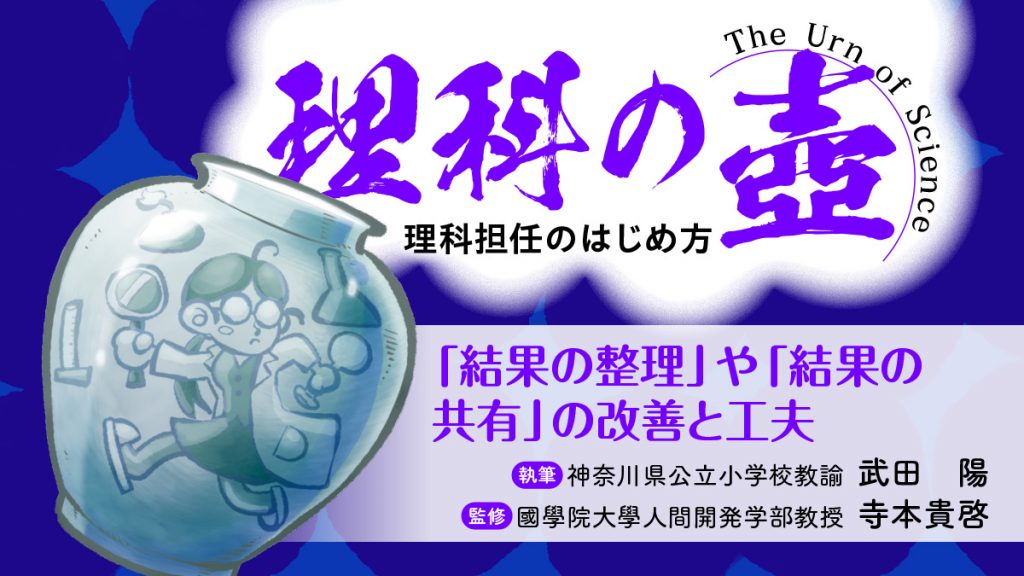
「理科の授業づくりを頑張るぞ!」と思ったとき、「どんな教材で実験・観察をしようかな?」「どんな感じで考察の話合いを進めるのがよいかな?」ということを最初に検討されることが多いと思います。
一方、「結果の整理・共有の仕方」は後回しになり、授業が失敗しやすいです。そこで、今回は、ちょっとの改善と工夫で授業をレベルアップすることができる「結果の整理・共有の仕方」を紹介します。 優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?
執筆/神奈川県公立小学校教諭・武田 陽
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
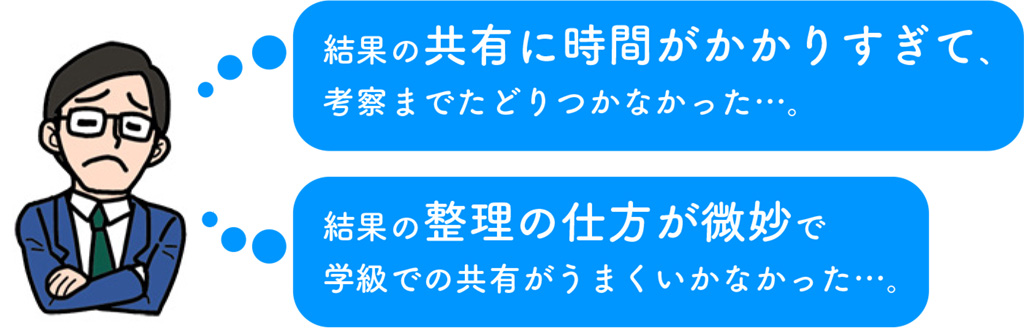
1.“失敗あるある” と指導の前提となるポイント
「結果の整理・共有の仕方」には、様々なものがあり、学習内容によってパターン化されているものも多いです。しかし、指導書の板書案通りに結果の整理を行っても、
「あれ…。うまくいかないぞ?」
となることはありませんか? なぜうまくいかなかったのでしょう。まずは、「結果の整理・共有の仕方」場面でどのような “失敗あるある”があるのか、確認してみましょう。
【「結果の整理・共有の仕方」の失敗あるある】
①結果の整理・共有に時間がかかりすぎて考察までたどりつかない。
②学級全体で押さえたい結果のポイントを共有できず、考察もバラバラ。自分の結果からしか考えていない。
また、「結果の整理・共有の仕方」の指導のポイントの説明に入る前に、まずは授業づくりで大切にしたい指導のポイントを押さえておきましょう。。
【ポイント】
①短時間で分かりやすく整理・共有ができるようにする。
②学級内で異なる複数の結果が出ているときは「傾向」「結果のズレ」などについて全体で確認の時間をとる。
もちろん、「結果の整理・共有」の指導に重点を置きたい場合は時間がかかることもあります。どの授業でも、教師が「この授業・単元では、○○の力を身に付けさせたい!」というねらいをしっかりもっておくことが大切です。
この点を確認したうえで、「結果の整理・共有の仕方」の指導のポイントを確認していきましょう。
2.「結果の整理・共有の仕方」の指導のポイント
「結果の整理・共有の仕方」について、基本的には以下のような流れになることが考えられます。
【基本の流れ】
(1)個人や班の結果の記録をノートに書く。
(2)個人や班の結果の記録を黒板に「貼る」「書く」「データ共有」「発言」などの方法を使って学級で共有する。
1つめの「個人や班の結果の記録をノートに書く場面」についてですが、「個人のノートにはどこまで書かせればいいのだろう?」と悩むことはありませんか?
他の人の結果を書いていて子どもたちが話合いに参加しないというケースも見られます。基本的にノートには個人の記録のみを書いて、結果の記録の共有での話合いに参加することが大切です。
2つめの「学級で共有する場面」については、学級全体で得た結果が、子どもたちに目で見て分かりやすいように黒板にまとめます。子どもたちが、黒板に示された学級での結果の記録を比較して考察しやすいように整理していくことが大切です。

