“未知”と“既知”をつなぐ“予備実験”のススメ【理科の壺】

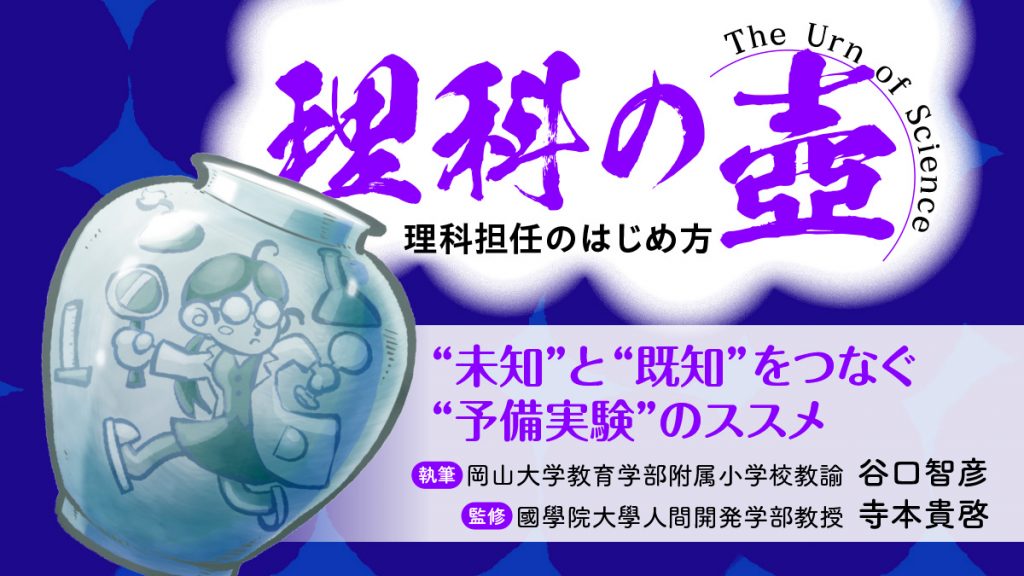
車の運転での「ヒヤリハット」はよく言われますが、理科実験においても「ヒヤリハット」があります。小学校実験ではけがをしそうな授業はそれほど多くはありませんが、薬品の実験や外出しての観察など事故が起こる可能性があります。それは先生が授業展開だけ意識するのではなく、その周辺の可能性まで意識しているかどうかに関わってきます。今回はどのような時に「ヒヤリハット」が起こるのか考えてみましょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?
執筆/岡山大学教育学部附属小学校教諭・谷口智彦
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
事故やヒヤリハットの発生
時々、理科の学習中に起こる事故を耳にします。それは「子どもがやけどをした」といったようなものから「実験中にガラス器具が破裂し、子どもが怪我をした」というようなものまで。また、事故には至らなかったけれど、「ヒヤリハット」が起きたということはさらによく耳にします。
どんな時に、事故やヒヤリハットが起こるのでしょうか。

私の経験で言うと、
- 先生! みんなの電池を繋げてみたら、すごいことになりそうだからやってみたい。
- 今使っている試験管だけじゃなくて、大きなフラスコでも実験させてあげれば、子どもが喜びそうだ。
といったような、子どもが「先生、○○してみたい」と、おもしろそうで魅力的な提案をしてきたときや、教師が、授業中に子どもの活動を見ていて「○○させてあげたら、喜びそうだ」とナイスアイデアを思いついたときに「ヒヤリハット」が起きやすかったように思います。
「未知」と「既知」
少し視点を変えて、どんな条件の時、学習活動が充実し、かつ、安全になるのでしょうか。「ヒヤリハット」を考える2つの軸と「未知(まだ知らない)」と「既知(もう知っている)」という「子ども」と「教師」という2つの軸を組み合わせて考えてみましょう。すると4つに分けることができます。
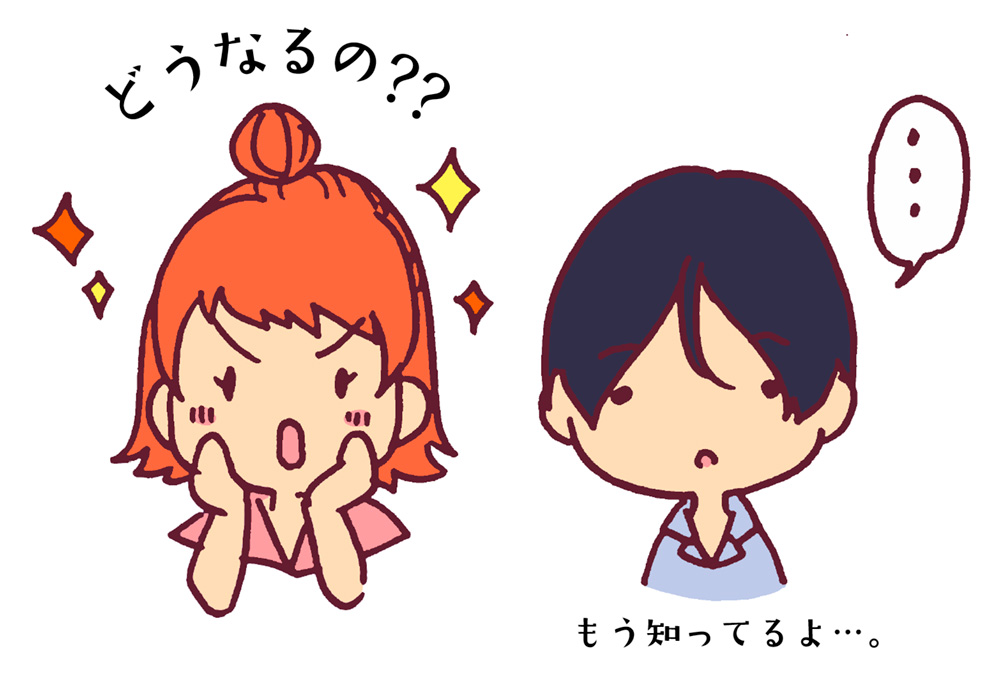
①子どもは「既知」、教師も「既知」
②子どもは「既知」、教師は「未知」
③子どもは「未知」、教師は「既知」
④子どもは「未知」、教師も「未知」
①の状態の授業を想像してみると、両者にとって、なんともつまらない時間が流れていそうですね。
では②。先生の勉強不足。まずいですね。非常にまずい。
それでは③。教師も、わくわくしたり驚いたりする子どもたちの姿を想像して、授業をすることが楽しみになるのではないでしょうか。
最後に④。未知と未知の遭遇。何が起きるかは神のみぞ知る。先生が事前に調べていない事を、子どもと一緒にやる事は、とても危険な事です。
さて、①から④の中で、どの場面で事故やヒヤリハットが起きそうでしょうか。そうですね。④のパターンでしょうね。子どもが前のめりに意欲を高めていて、その結果として起きることを先生も知らないのですから。

①両者が知っている事なので安全。ただ、授業がつまらない。
②子どもが知っている事なので安全。ただ、先生が勉強不足。
③先生が知っている範囲内なので安全。子どもが知らない事なのでワクワクして授業ができる。
④知らない事に挑戦する心掛けはよいが、先生が試していない事をやるのは超危険!!
教師として、子どもが意欲的に何かを提案してきたとき、こんな工夫をしてあげられそうだと考え、子どもの喜ぶ姿を思い浮かべたときは、まさに教師冥利に尽きる瞬間だと私も強く実感しています。しかし、「安全」という視点から見ると、立ち止まる鉄の意志が必要です。
授業中に事故が起きてしまったら、その場の児童への対応や救急活動、管理職への報告、放課後の保護者への対応、善後策の相談、途中やめになった授業の回復、状況によっては教育委員会とのやり取りが生じることも…。「読めない時間」がどんどん生じてしまいます。


