小1生活「どきどきがおの えんの おともだちを にっこりわくわくえがおに しよう」指導アイデア
執筆/大分県公立小学校教諭・生野貴司
編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典、文部科学省教科調査官/愛知淑徳大学准教授・加藤智、大分県教育庁義務教育課指導主事・後藤竜太
目次
期待する子供の姿
知識及び技能の基礎
伝えたいことが相手に伝わるよさや楽しさが分かるとともに、適切なあいさつや言葉遣いをすることができる。
思考力、判断力、表現力等の基礎
これまでの体験を基に、相手のことを思い浮かべながら、伝えたいことを選んだり、伝え方を工夫したりする。
学びに向かう力、人間性等
園の友達に小学校の生活について伝えたいという思いをもち、進んで触れ合い交流しようとする。
単元の流れ(12時間)
えんのおともだちのために したいことをかんがえよう(3時間)
- できるようになったことやがんばったことをふり返ったり、入学前にもっていた不安感や期待感を想起したりして、園のお友達のためにしたいことを話し合う。
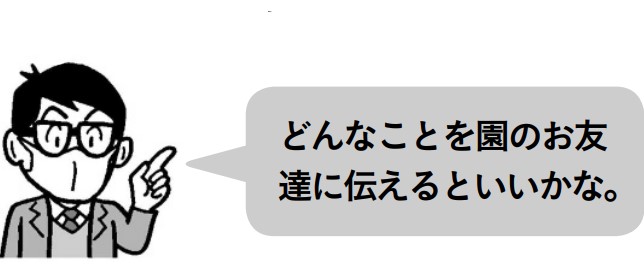
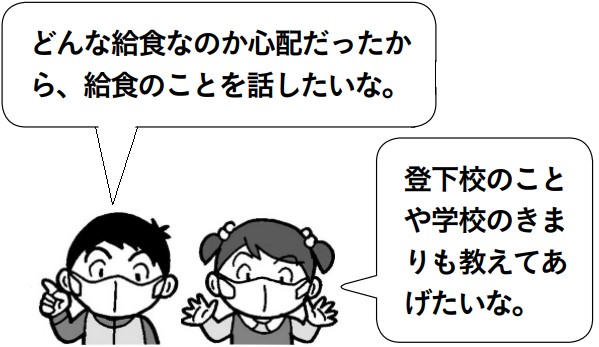
評価規準等
態 園児に小学校の生活について進んで伝えたいという思いをもっている。
※評価規準等の知=知識・技能、思 =思考・判断・表現、態=主体的に学習に取り組む態度の観点を示しています。
えんのおともだちに 伝えよう
(8時間+国語科との関連)
- 「きゅうしょくをいっしょにたべようの会」や「学校のこと おしえますの会」に向けて、準備することや園のお友達に伝えることを話し合う。
- 栄養教諭や給食調理員、交通安全指導員に知りたいことや確かめたいことを尋ねたり、伝える内容や伝え方を班ごとに話し合ったりする。
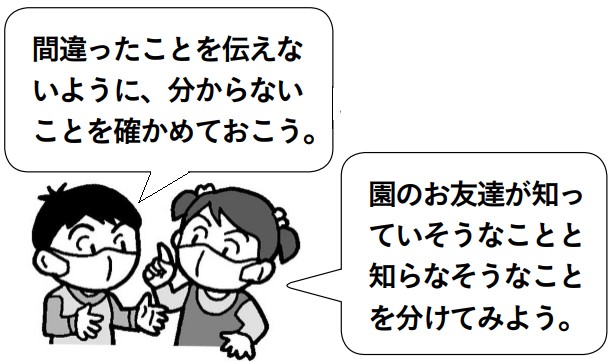
評価規準等
思 園児のことを思い浮かべながら伝えたいことを選んだり、言葉や絵、動作などの伝え方を工夫したりしている。
知 相手や目的に応じて、さまざまな伝え方があることに気付いている。
態 園児と進んで触れ合い交流しようとしている。
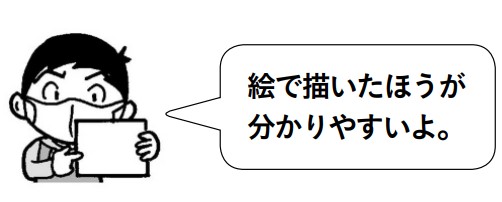
できたことやがんばったことを ふりかえろう(1時間)
「給食のことがよく分かったよ」って言ってくれたよ。 一年生でできるようになったことがまた増えたよ。
4月に入学してくれるのがとても楽しみだな。これからも仲よくしたいな。
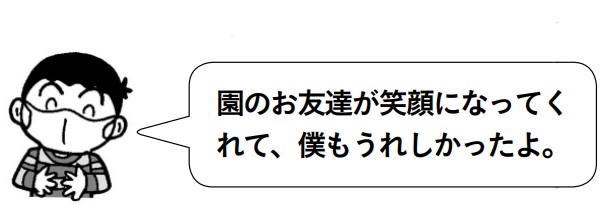
評価規準等
知 伝えたいことが園児に伝わることの楽しさが分かっている。
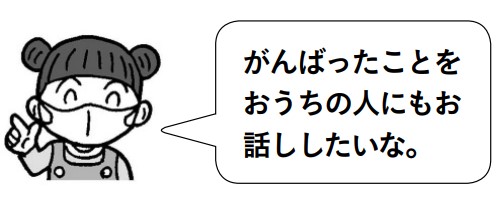
活動のポイント1
目的意識・相手意識を明確にし、「伝えたい」思いを高めるようにする
伝え合い交流する場では、目的意識・相手意識をもたせることが大切です。具体的に「○○園の私のお友達、△△ちゃん」と伝える相手をはっきりさせることです。友達の不安感(どきどき)を減らし、期待感(わくわく)を増やして、「笑顔にしてあげたい」という思いをもつことが、学びに向かう力の基盤となります。
相手意識が十分でないままでは、子供にとって目的意識の薄い「やらされ感」のある学習になってしまいます。
保幼小交流は三学期に行われることが多いのですが、子供と園児が親密さを感じられるような出会いの場を、年間指導計画を見通して構想することが必要です。
【相手意識をもつための工夫】
○年度当初から一緒に遊ぶなど、子供と園児がともに楽しみながら交流する活動を繰り返し設定しましょう。「お世話をすること」を教師側が焦らないことが大切です。おもちゃ大会や秋遊び、音楽発表会などで小学校に招待したり、園の行事に招待してもらったりしてもよいでしょう。
○交流の後は楽しかった思いを伝え合い、交流するよさや楽しさを実感させましょう。
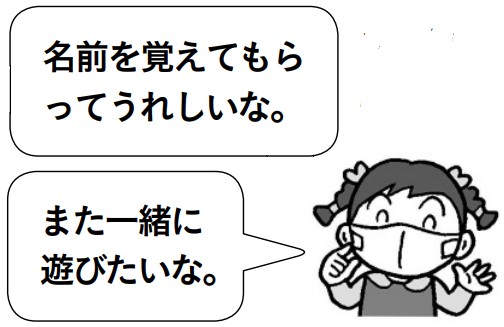
活動のポイント2
内容(8)「生活や出来事の伝え合い」から、内容(9)「自分の成長」への発展を図る
イラスト/高橋正輝
『教育技術小一小二』2020年1月号より






