なぜ不登校やひきこもりは日本だけなのか?!
新型コロナ禍で、「学校より自宅がいいと子供が言い出して、まいった」という親の声を聞きます。学校に行くのが嫌な子の延長に不登校やひきこもりがあります。それらの子供には、きっとある通奏低音が流れているに違いありません。今回はエデュケーショナル・マルトリートメント(教育虐待)の視点から、それを考えてみました。
文/教育ジャーナリスト・高瀬康志
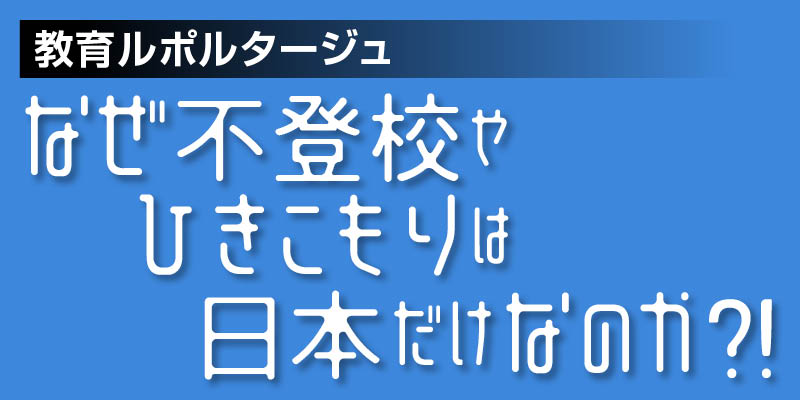
目次
見えないものとして扱われる「不登校」「ひきこもり」
10年以上前のことですが、ひきこもりの人と闇鍋をする集まりに参加したことがありました。そのとき、ひきこもりのひとりが、
「最近、ニートという言葉が出てきたでしょう。不登校もひきこもりも全部ニートにひっくるめられてしまって、もう不登校の子やひきこもりはあってないような存在です」
と漏らしました。筆者が、
「レッテル貼りもそうだけど、目にしたくないもの、耳に入れたくないものはこの世にないと思う人間もいるから、困っちゃうよな」
と言うと、その人は、
「人間は怖いです」
と返しました。別に注目されたいわけではないでしょうが、社会から見向きもされないのはやはり寂しいものです。ふと足元を見れば、いつでも虚無は口を開けて待っています。
子供によかれと思う教育が仇になっていないか
『教育技術小五小六』2019年10月号で、中学受験をめぐって父親が小6の息子を殺した事件を取り上げたとき、教育的行為がエデュケーショナル・マルトリートメント(教育虐待)になりうることを、その第一人者である武田信子・ジェイス代表理事(元武蔵大学教授)のコメントをもらって指摘したことがありました。その武田さんが、エデュケーショナル・マルトリートメントを切り口にして日本の教育に警鐘を鳴らす『やりすぎ教育』(ポプラ社)を上梓されたと聞き、取材しました。
武田さんは執筆動機について、
「学校に行きたくない子供たちをいつまで苦しめたり死なせたりするのでしょうか。子供たちの代わりに声を上げなくてはいけないと思って本書を書きました」
と語ってくれました。
そもそも日本の学校教育の過剰な競争性の問題や強制的な勉強の悪弊については、何度も国連・子どもの権利委員会から指摘されてきました。しかし、日本は学歴社会で、受験戦争は中学受験の段階まで拡大してきました。大人たちはそれを無視し、改善する気配がありません。
エデュケーショナル・マルトリートメントは、カナダやオランダで研究生活を送った武田さんが、日本の教育事情を説明するために考え出した言葉です。親や学校等が子供に対して行う教育の強制行為や剥奪行為を指します。競争的教育環境を是認してきた日本社会の価値観が生んだ現象として、社会全体でその対応に取り組むことをねらいとする概念です。
この概念は、よい教育をしているつもりが、実は子供を苦しめていたという実態をあぶりだすリトマス試験紙だと筆者は理解しました。

