子供たちの心を揺さぶり計画委員会を活性化!【特別活動研究校レポート】
人と信頼関係をつくること、社会にかかわり、よりよくすること、自分のよさを伸ばしていくこと。特別活動で育てようとしているのはこうした力です。子供たちが今後、社会で生きていく上で必要不可欠なものばかりです。杉田洋・國學院大學教授が推薦する、さまざまな学校の「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」を育む実践を取り上げていきます。今回は、東京都府中市立南白糸台小学校の実践を紹介します。
監修/國學院大學教授・杉田洋

目次
特別活動の研究を始めて1年目から成果が現れた
副都心の新宿駅から西に延びる私鉄に乗り、最寄りの武蔵野台駅に降り立ちます。そこは、ちょうど武蔵野台地の崖線が走るところにあり、坂を下っていくと、目当ての小学校があります。
東京都府中市立南白糸台小学校(森嶋正行校長、児童数664人)は、2019年度に校内で特別活動の研究を始め、2020年度から2年間、府中市教育委員会研究協力校として特別活動を研究しています。本校の研究成果は、早くも昨年度に表れたといいます。今回は、その昨年度の取組について、森嶋校長、特別活動主任の小杉厳太教諭、横川朋子教諭にお話しを聞きました。
学級は誰もが自由に発言できる雰囲気に溢れていた
小杉学級(今年度は6年1組)を訪れると、帰りの会が開かれるところでした。
日直「帰りの会を始めます。当番、係、サークルの連絡や言いたいことはありますか」
A「図工当番です。図工の持ち物はのりと絵の具です。それから、配付されたプリントを忘れずに持ってきてください」
みんな「はい」(拍手)
B「忘れてた。Aさん、ナイス!」
C「靴箱傘立てサークルです。今日の靴箱はきれいでした。来週も心がけましょう」
D「土曜日に前髪を切りました。前髪の乱れは心の乱れです。みんなも髪の乱れに気をつけましょう」
みんな「はい」(拍手)
学級から笑い声が起き、筆者も笑いました。サークルとは、「ちょボラ」(友達をちょこっと助けるボランティア)をするグループのことです。
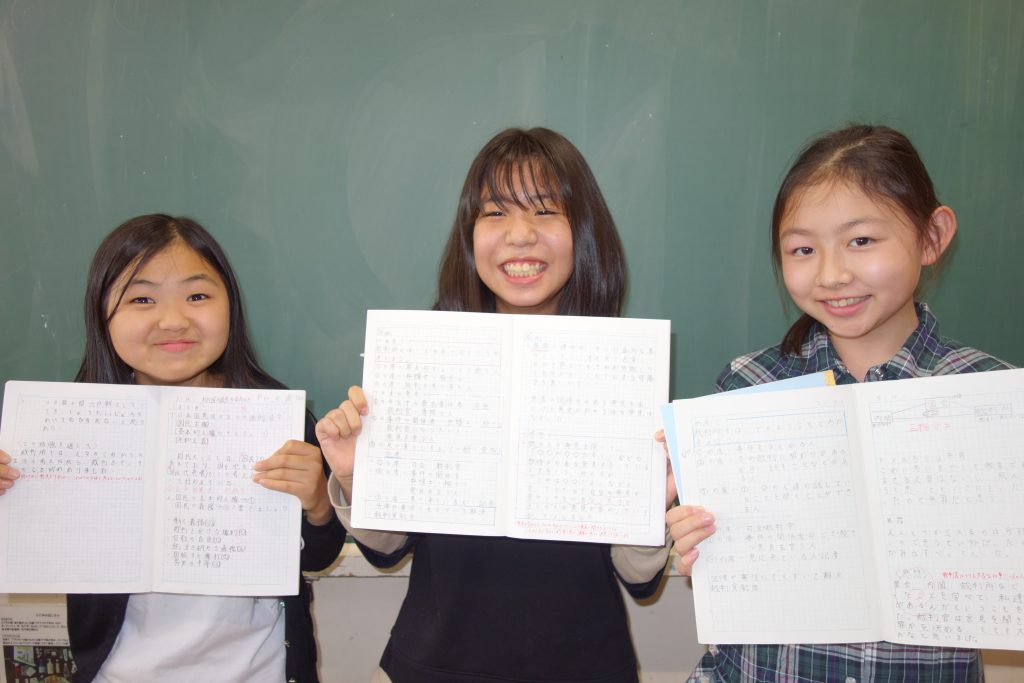
終業後、学級に立っていたら、1組の子だけでなく、隣の2組の子までが、「こんにちは」と声をかけてきました。誰が発言しても構わない雰囲気がありました。しかし、この研究を始める前の子供の姿はそうではなかったらしいのです。森嶋校長はこう話します。

「それまでの子供たちは、教師から言われたことはきちんとしても、何かを生み出そうとする意欲は感じられませんでした。私は子供たちが自分たちでつくっていく学校にしたいと考え、特別活動の研究を始めることにしました」

