【木村泰子の「学びは楽しい」#42】障害に応じた対応ではなく、一人の人として

子どもたちが自分らしく生き生きと成長できる教育のあり方について、木村泰子先生がアドバイスする連載の42回目。今回は、普通学校と特別支援学校の両方で学んだ体験をもつ一人の女性の言葉から、インクルーシブ教育の意味を問い直していきます。(エッセイのご感想や木村先生へのご質問など、ページの最後にある質問募集フォームから編集部にお寄せください)【 毎月22日更新予定 】
執筆/大阪市立大空小学校初代校長・木村泰子

目次
いつ何が起きるかわからない!
夏休みはリフレッシュされましたか? 私はほぼ休みなく全国の先生方と学ぶ毎日でした。まさに、伸び盛りの私を実感しているところですが、先日、初体験をしました。
8月10日に福岡県弁護士会のインクルーシブ教育を考えるシンポジウムに出席して大阪に戻る予定だったのですが、大雨の影響で夕刻から突然、新幹線が運休になりました。急いで福岡空港に向かい、伊丹空港行きの最終便をとることができ安心していました。こちらも夕刻からの便がすべて止まっていて、順番に出発するとの放送に安堵したのですが、19時15分発の便が20時前になり、突然欠航とのアナウンスです。「エッ!」その後バスターミナルに走りましたが、高速バスもすべて運休です。自分の力では身動きがとれない状態になってしまいました。
覚悟を決めてホテルを探すのですが、さすがに近辺のホテルはすべて満室です。テレビでよく見ていた光景が自分事になりました。博多駅も福岡空港も人であふれ返っていて、床に新聞紙を敷いて寝る準備をされている方もたくさんおられました。私は一人でどうすることもできなくて、家族や知人に助けを求めてホテルを見つけてもらい、一夜を明かしました。
翌日は埼玉県での講演です。若い人たちが前々から準備していて、何があっても行かなくてはとの思いです。私の予約していた便は最終便のため、それまでに欠航が決まった人たちが翌日の振替便をとっているので、もう翌日の座席が残っていません。さすがにどうしたらいいのか、自分の力だけでは何一つできない状況に陥りました。そのときのような焦りと無力感は初体験でした。これまでも「世の中いつ何が起きるかわからない」が大空小での合言葉でしたが、まさにその瞬間に遭遇したのです。
困ったときは「人の力を活用する力」を発揮するに限ります。どんな状況に遭遇しても「何とかなる!」とあきらめないで前に進むことだと痛感した初体験でしたが、先に述べた福岡県弁護士会主催のインクルーシブ教育を考えるシンポジウムでは貴重な学びを得ましたので、紹介します。
シンポジウムの講演の言葉から
以下は、当日、講演された橋口侑果さん(社会福祉士、熊本学園大学大学院修士課程2年、障害名:脳性まひ)の言葉です。「普通学校にも特別支援学校にも通ったことで学んだ『人権』」という演題でお話をされました。
◎小学校就学について
・5歳の時、知能は2歳児と言われ、「発達、知能の遅れのため」と私抜きの話し合いで特別支援学校に入学する方向へ。
・自分のことなのに私は話を聴くだけで、自分の気持ちを伝えると、「パンツも自分で上げられないのに何のために勉強するの? まずは自分のパンツ上げられるようになってから勉強しようね」と言われ、自分の希望がわがままだと思い、何も言えなくなった。
・一番仲よかった保育園の友達みーちゃんに「小学校行けない、リハビリの学校」と伝える。すると、みーちゃんが「今だって一緒に何でもできるのにおかしい。困ったら私がいるじゃん。リハビリの学校に行かなくても、帰ってから習い事でやればいいよね?」
・それからみーちゃんが「ゆかと同じ学校行くんだ」と大人に言って回り、大人の意識が変わり、両親が中心に動いてくれ、無事に地域の小学校へ。支援委員会よりみーちゃんが私の一番の味方だった。就学決定の壁は高かったが、地域の学校に入学できた。
◎楽しかった地域の学校
・介助員を付けてもらい地域の学校で過ごす。
・勉強は分からなくなり追いつけないこともあって、そばから見ると支援学級がよいのではと思われていたかもしれないが、普通学級にいることが生きがいだった。「みんなが私の存在を認めてくれて居場所がある」と実感していたため、それを壊したくなかった。
・障害に応じた対応ではなく、一人の人として関わってもらえた。ぶつかることも避け合うこともあったが、同じ空間にいたからこそできたこと。大好きな仲間たちが自分の障害を受け止めてくれて、自分のことを好きになれた。障害のことでいじめられるようなことはなく、みんな肯定的で、先生たちも不慣れな中で私がどう参加したいか直接聞いてくれる。参加できなかったら、同級生が「おかしい」と声を上げてくれるので安心だった。いろんな体験ができた。
◎悔しい高校の進路決定
・希望する高校からは様々な理由で断られ、特別支援学校を勧められ入学したが、苦しんだ。
・周囲の大人が子どものために考えてそれぞれに合った支援が行われているのかもしれないが、子ども一人一人の声が聴かれていないと感じることもあり、言いたいことがあってもどうせ聴いてもらえないと我慢する。
・合理的配慮が効率性を意識したものになっている場合があり、自分のやりたいことより周りの効率や迷惑ではないかを気にする。
・人と人との対等な関係性が築けなくなり、いざ卒業すると本当の独りぼっちになった。
・周囲の人に芽生えてしまう「かわいそうな存在」、同情心。
・自分の権利がわからなくなっている。「わがままじゃないの?」障害に対して「治さなければ」という考えが強い。
・できるかできないかを先生がはっきりと決める。できないことばかりに目を向けられ自己肯定感が下がっている。
・小中では尊厳が守られ人とつながることが楽しくできていたが、支援学校に入ってから人を避けるようになり、人権もきれいごとだと思うようになった。人間らしい人格の発達が小中では可能だったが、支援学校に進学後、見失った。
・小中では地域社会に居場所があったのに、支援学校卒業後は周囲との関わり方に苦しみ、社会参加のハードルが上がった。
そして、最後に語られた言葉です。
「子ども時代を分離しておきながら、その後、共生を目指すのは都合のいい話」
私たちは真摯に侑果さんの言葉に学び、今を問い直したいと思います。
〇特別支援が大人の都合や効率性を優先したものになっていないか、子ども一人一人の声を聴いた上での合理的配慮が行われているかを問い直そう。
〇できないことばかりに目を向けると、子どもの自己肯定感は下がる。あるがままを受け止めることで、人としての尊厳が守られ、どの子ものびのび成長できる。
〇ともに学び合うインクルーシブな環境の中で、子どもたちは互いの存在を認め合い、対等な関係性を築く力をつけることができる。
【関連記事はコチラ】
【木村泰子の「学びは楽しい」#41】「大空20祭」が教えてくれたこと
【木村泰子の「学びは楽しい」#40】子どもの主体性を育てていますか?
【木村泰子の「学びは楽しい」#39】子どもの「ほんとの声」を聴ける大人になるには
※木村泰子先生へのメッセージを募集しております。 エッセイへのご感想、教職に関して感じている悩み、木村先生に聞いてみたいこと、テーマとして取り上げてほしいこと等ありましたら、下記よりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。
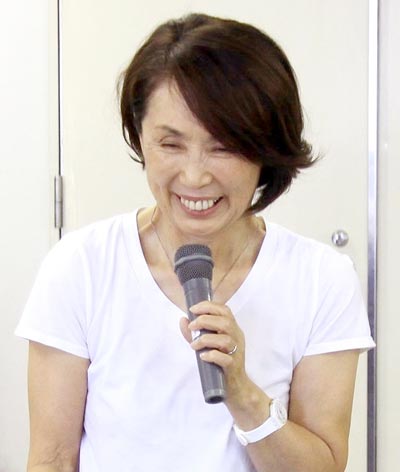
きむら・やすこ●映画「みんなの学校」の舞台となった、すべての子供の学習権を保障する学校、大阪市立大空小学校の初代校長。全職員・保護者・地域の人々が一丸となり、障害の有無にかかわらず「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに尽力する。著書に『「みんなの学校」が教えてくれたこと』『「みんなの学校」流・自ら学ぶ子の育て方』(ともに小学館)ほか。
【オンライン講座】子どもと大人の響き合い讃歌〜インクルーシブ(共生)な育ちの場づくり《全3回講座》(木村泰子先生✕堀智晴先生)参加申し込み受付中! 大空小学校時代の「同志」お二人によるスペシャルな対談企画です。詳しくは下記バナーをクリックしてご覧ください。

