小1算数「あわせていくつ」指導アイデア《ブロックをうごかしておはなしをしよう》
国立教育政策研究所教育課程調査官の監修による、教科指導のアイディアと授業のヒントをまとめた指導計画例です。次時の授業にお役立てください。
執筆/福岡教育大学附属小倉小学校教諭・川原雅彦
編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏
目次
単元名「あわせていくつ」
●本時のねらいと評価規準(本時の位置 1/6)
【本時のねらい】
2つの数量の合併の場面について、数量の関係に着目し、具体物を操作する活動を通して、加法の意味や式の表し方を理解する。
【評価規準】
2つの数量の合併の場面について、その意味を理解している。(知識・理解)
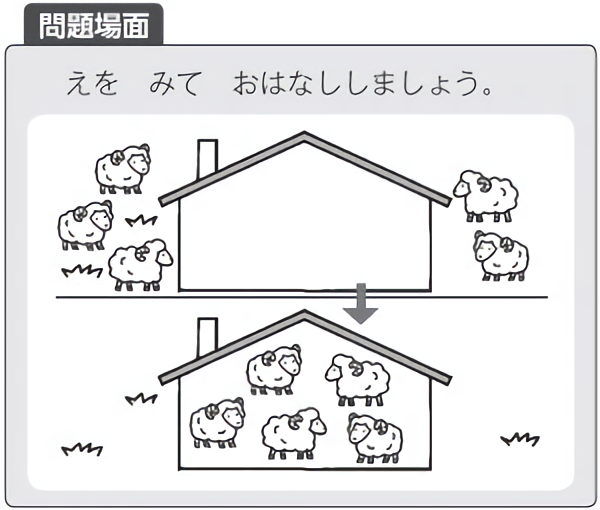
(上半分の絵を見せる)この絵を見てお話ができますか。
ひつじさんがいます。
左には3匹、右には2匹います。
お話は、まだ続きますよ。(下半分の絵も見せる)続けて、お話ができますか。
ひつじさんが、みんな小屋に入っています。
小屋に入ったひつじさんは、合わせて何匹になったか、数えてみましょう。(全員で確認する)友達同士で、ブロックを使ってこのお話をしましょう。
本時の学習のねらい
ぶろっくを うごかして おはなしを しよう。
【見通し】

友達にお話をするとき、ブロックをどのように使ったらよいですか。
今までの勉強の時と同じように、ひつじさんの上にブロックを置きます。
ブロックを、動かしたらいいと思います。
なるほどね。今までの勉強でしたように、ブロックを置いて、動かしたらいいんだね。
【自力解決の様子】
A:つまずいている子
3個と2個のブロックを置くが、その後、何をしてよいかわからない。
B:素朴に解いている子
3個と2個のブロックを置き、その総数を数えるなどして求めるが、ブロックは動かさない。
C:ねらい通りに解いている子
3個と2個のブロックを「□□□→←■■」のように、中央に合わせている。
【学び合いの計画】
同時に存在する2つの数量を合わせた大きさを求める場面の理解を目指します。そのために、ひつじをブロックに置き換え、ブロックを動かしながら、合併の様子を友達に伝え合うようにします。これまでの学習でもブロックを使ったことを想起しながら、「合わせる」という言葉とブロックの操作とを関連付けるようにします。
【ノート例】
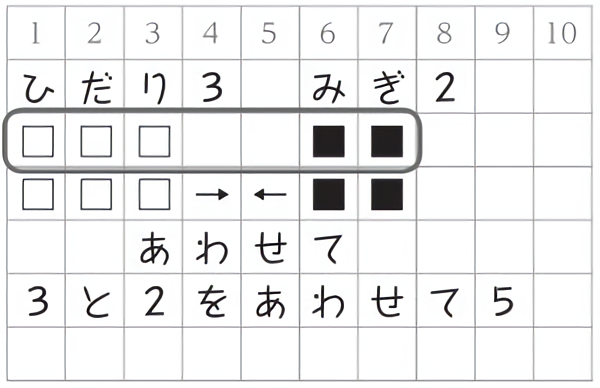
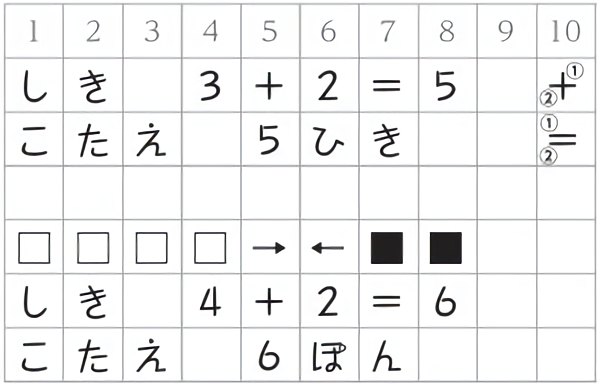
【全体発表とそれぞれの考えの関連付け】
ブロックを、どのように動かしていましたか。
左にひつじさんが3匹いるので、ブロックを□□□と3個置きます。右にはひつじさんが2匹いるので、ブロックを■■と2個置きました。5匹になります。
小屋に入ったから、ブロックをこうやって(□□□→←■■)合わせました。
ブロックを動かして合わせると、お話がよく伝わりますね。何匹と何匹で合わせて何匹になりましたか。
3匹と2匹で、合わせて5匹です。
このように、合わせるときに「+」という記号を使います。そして、「3+2=5」と表します。これを「式」と言い、このような計算を「たしざん」と言います。
【学習のねらいに正対した学習のまとめ】
左右のブロックを中央にまとめる。
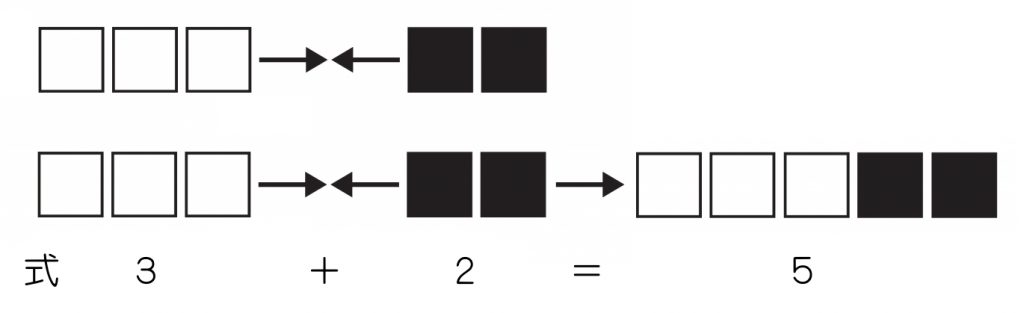
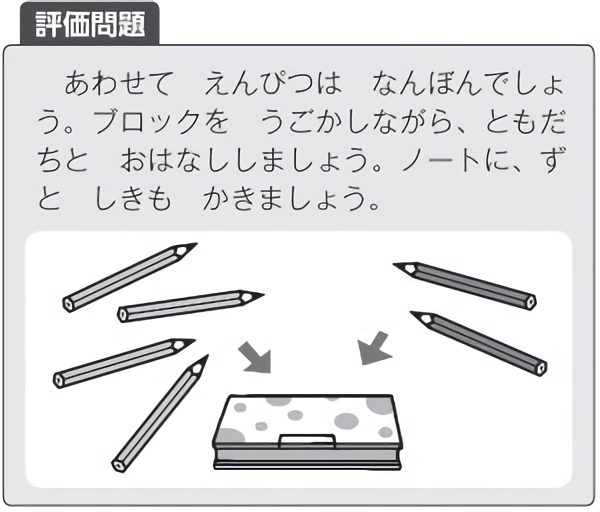
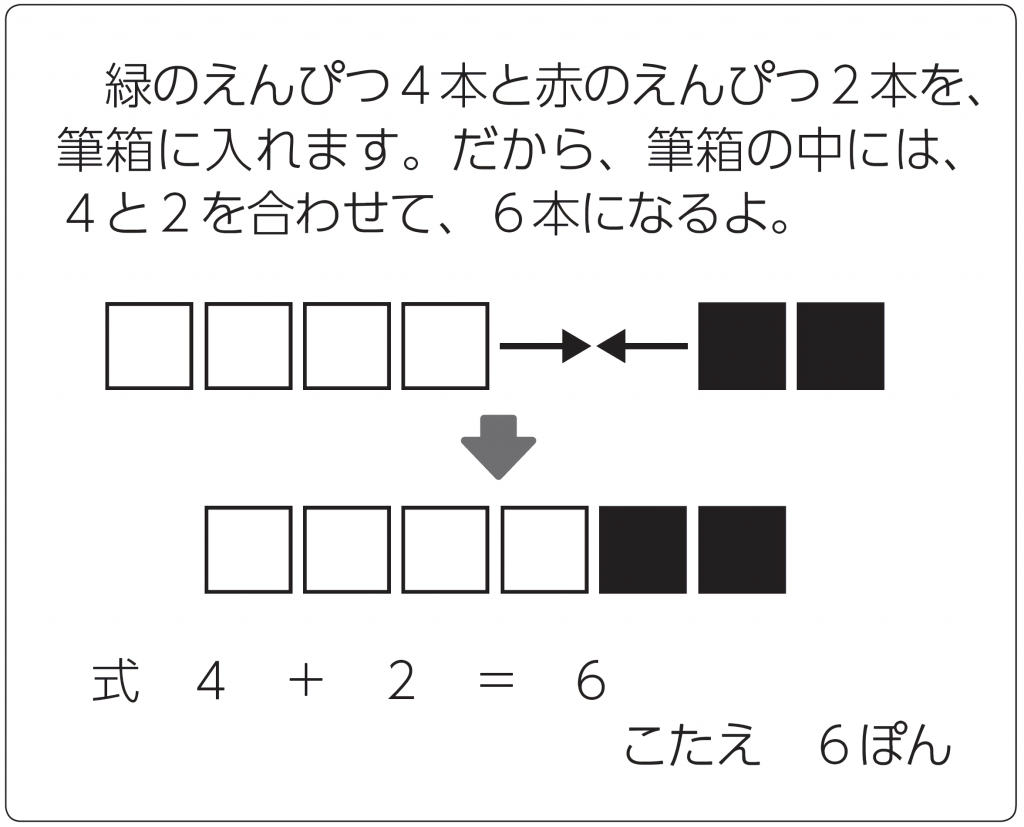
【子どもの感想】
ブロックを動かすと、お話がわかりやすくなると思います。
式を使うと、合わせてのお話が簡単にできます。
単元名「ふえるといくつ」
●本時のねらいと評価規準(本時の位置 2/6)
【本時のねらい】
数量の増加の場面について、数量の関係に着目し、具体物を操作する活動を通して、加法の意味や式の表し方を理解する。
【評価規準】
数量の増加の場面について、その意味を理解している。(知識・理解)
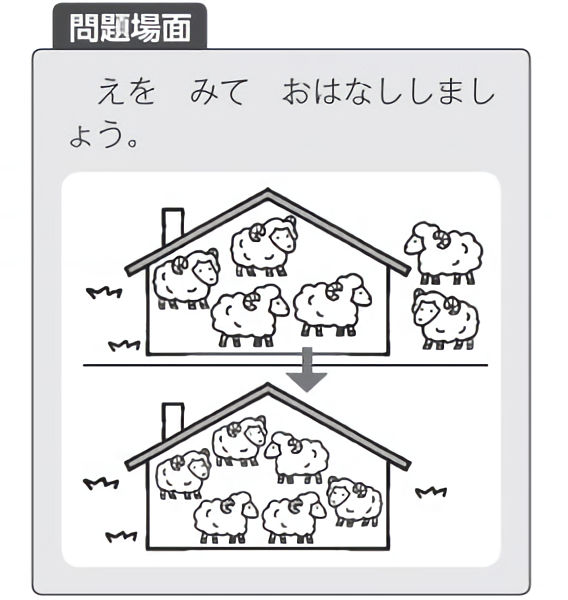
(上半分の絵を見せる)この絵を見て、お話ができますか。
イラスト/佐藤雅枝・横井智美
『小一教育技術』2018年6月号

