「清掃活動をゲーミフィケーション」で主体的なお掃除に

「フリーランスティーチャー」という型にとらわれない教職を貫く田中光夫先生が、多様でアイディアあふれる授業実践を紹介します。
文/フリーランスティーチャー・田中光夫
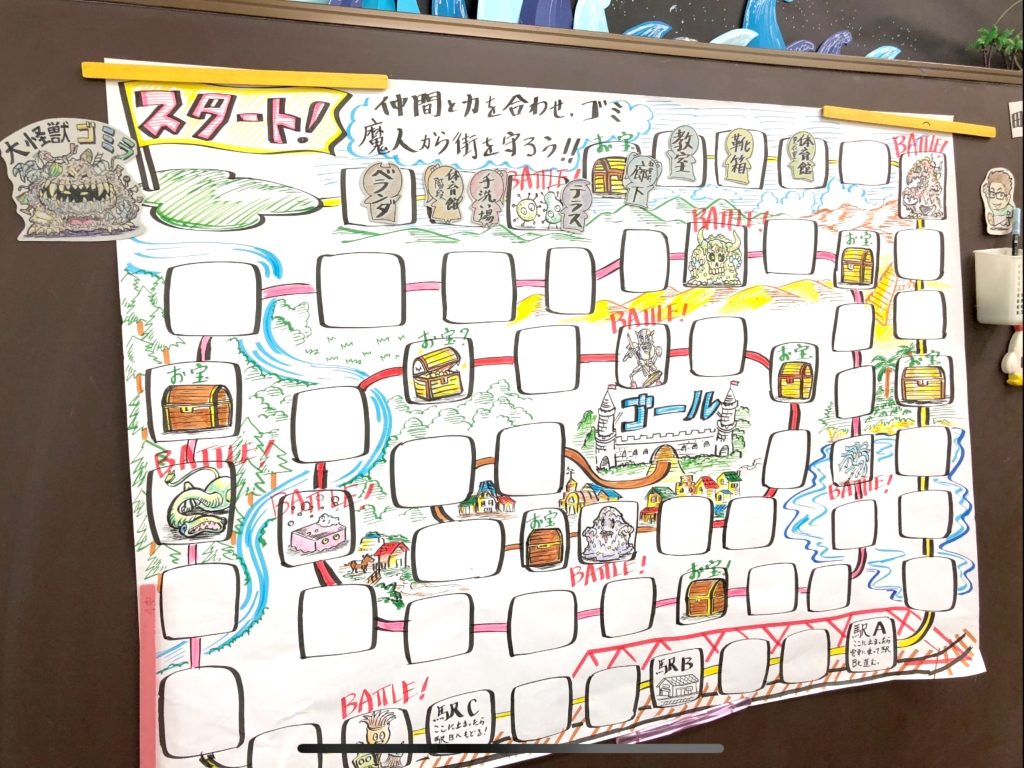
目次
「ゲーミフィケーション」ってなんだ?
あなたはゲーム好きですか? 僕は大好き。テレビゲーム、カードゲーム、ボードゲーム、いろいろなゲームにはまりました。オンラインゲームははまりすぎて4年間に渡りネトゲ廃人を経験しました。
そして子どもたちもゲームが大好き!
Nintendo Switchで対戦ゲームにはまる子、スマホのソシャゲ、TPS*系の『フォートナイト』や『荒野行動』なんかが流行ってますね。学校でも、お楽しみ会などでゲーム大会をすると大盛り上がりです。
※TPS……「サード・パーソン・シューター」 ゲームのこと。プレーヤーキャラクターを後ろからカメラが映す表示スタイルのこと。第三者目線での操作システム。対して、一人称目線の操作システムをFPS(ファースト・パーソンシューター)という。
今回は「ゲーミフィケーション」の話。
ゲーミフィケーションとは、「ゲームではない活動にゲームの要素を組み込むことで、主体性を引き出したり、継続して取り組ませたりする」というものです。それによって「活動の習慣化」が期待できます。
ゲームに内在する素敵な力
ゲームは、私たちを惹きつけてやまない様々な秘密を内在しています。いくつか例を挙げてみましょう。
〇「明確なルールがある」
ゲームには、試行錯誤によって作り出された明確なルールがあります。ルールに従って遊ぶことで仲間と楽しむことができます。
〇「ゴールがある」
ゲームにはゴールがあります。例えばRPGなら「ラスボスを倒す」がとりあえずのゴール。これを目指してさまざまなミッションをクリアーしながら進めます。
〇「繰り返すうちに上達する」
はじめのうちはなかなか上手くいかなくても、繰り返すうちに次第にスキルが身につき、スムーズに遊べるようになります。自身の成長を実感することは楽しく、のめりこんでしまいますね。
〇「具体的報酬が与えられる」
ゲームには「報酬」があります。 「勝敗」「経験値獲得によるレベルアップ」「アイテム」など。最近は「ログインボーナス」なんてのもあります。 得た時に嬉しくなる「わかりやすい報酬」はゲームへの継続性を高めます。
〇「仲間との交流が進む」
一人でやるゲームもありますが、誰かと競ったり協力したりして課題をクリアーするというのも楽しさの一つ。私がネトゲ廃人だった時、やめたくてもやめられなかったのは全国の仲間とのやりとりが楽しかったからでもありました。
他にもゲームの持つ特性はありますが、これらの要素は人々をゲームに熱中させる鍵です。
ゲーミフィケーションは、ゲームではない活動にこれらの要素を組み込むことで「やってみたい」「続けたい」を引き出すことができるという考え方です。
今、さまざまな企業が顧客を虜にするためゲーミフィケーションを取り入れています。 次回の「行動経済学」の回でも紹介しますが、私たちの多くは、自己決定をしているようで実は他者の意図に「乗せられている」ことが多いです。 よい響きではないように感じる人もいますね。

