小2生活「ほらっ ふゆがやってきた」指導アイデア
執筆/宮城県公立小学校教諭・岡稚佳
編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典、宮城県公立小学校教諭・鈴木美佐緒
目次
期待する子供の姿
【知識及び技能の基礎】
冬の行事について調べたり行事に参加している人と関わったりする活動を通して、冬の行事に対する人々の思いや願いに気付いているとともに、生活上必要な習慣や技能を身に付けている。
【思考力、判断力、表現力等の基礎】
冬の地域の行事に関わる活動を通して、地域による違いや特徴、人々の思いに気付き、伝えたいことや伝え方を考えて表現している。
【学びに向かう力、人間性等】
冬の地域の行事に関わる活動を通して、気付いたことや分かったことを自分の生活に取り入れ、楽しく生活しようとしている。

子供の意識と指導の流れ(6時間)
こんな声や姿を学習につなげたいですね。
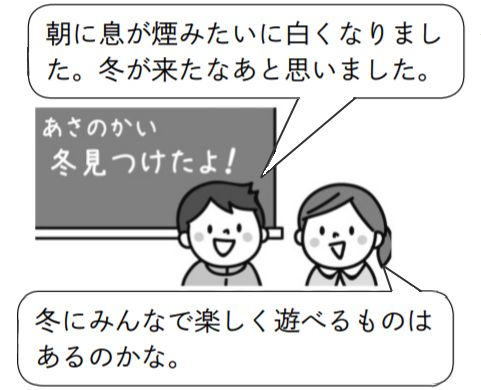
一年生では、冬の自然の様子や変化を体全体で感じながら、冬の自然現象を利用した遊びを行いました。二年生では、正月などの日本の伝統的な行事や、雪祭りなどの季節の行事に気付かせながら、より広い視野をもって学習に取り組ませます。 地域の冬の行事を調べたり参加したりする活動を通して、日本の伝統を感じたり地域への愛着を深めたりできる子供を目指しましょう。
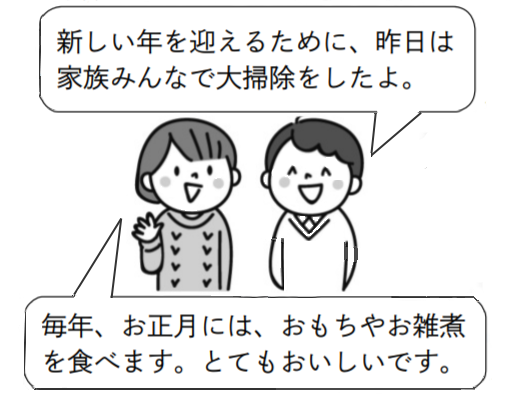
冬の行事を調べよう(2時間)
冬にはどんな行事があるのかな。
•冬の行事について話し合ったり調べたりする
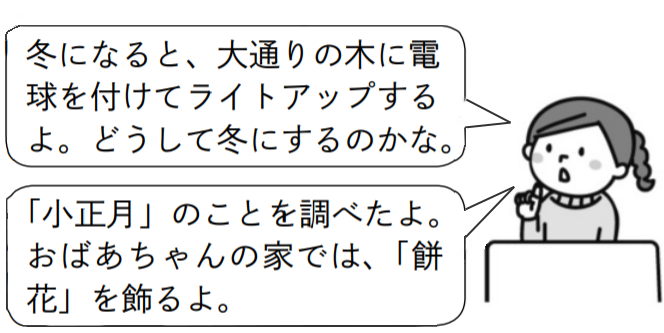
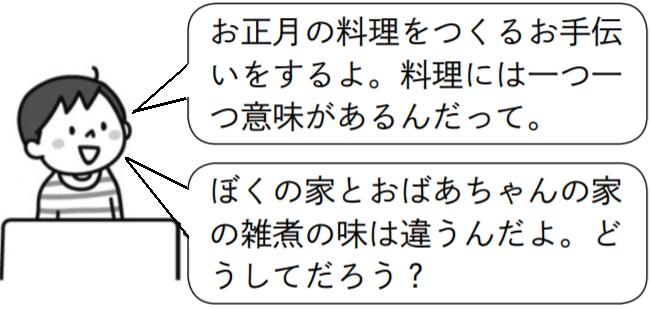
子供たちが、地域の伝統的な行事の意味や、その行事に関わる人々の思いに触れることができるように、行事を通して体験したことや気付いたことをお互いに共有できるような学びの場を工夫しましょう。
冬を楽しもう! (3時間)
「冬」の行事に参加しよう。
•冬の行事に参加する
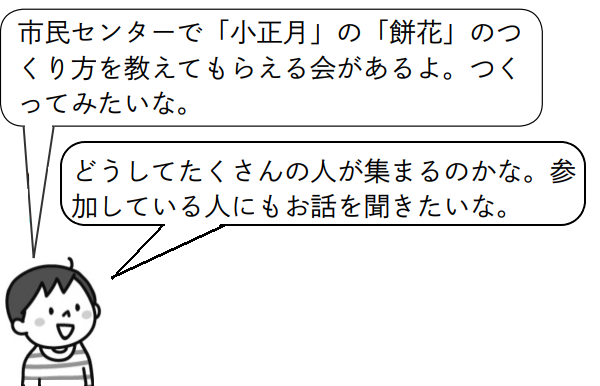
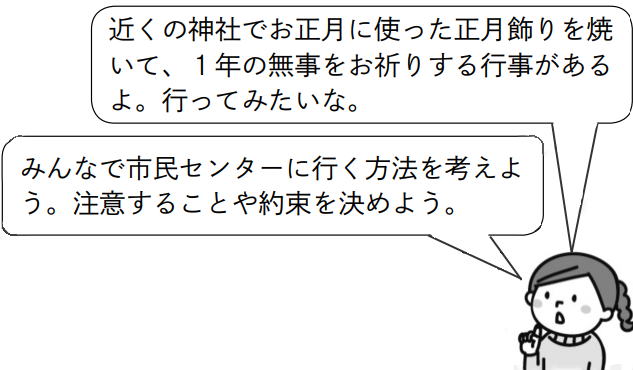
子供たちが行事のよさや関わっている人の思いに気付くことができるように、日頃から地域の行事に目を向け、積極的に参加するよう、保護者にお便りなどで声かけするのも一つの方法です。
冬の行事を知らせよう!(1時間)
•一年生に冬の行事を紹介する
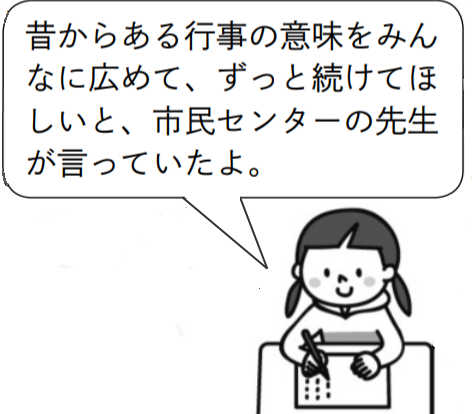
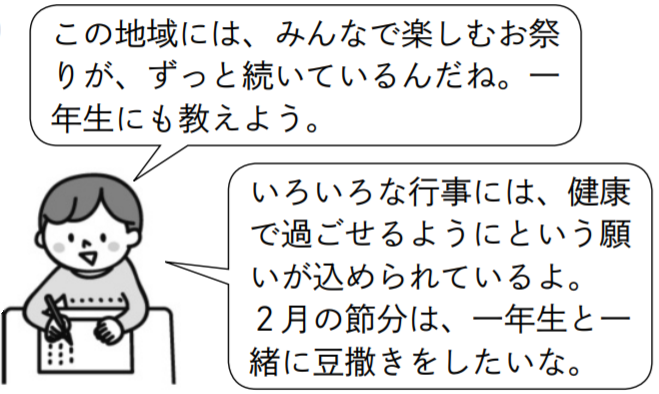
子供たちが普段の生活の中で、季節の変化を実感しながら冬の遊びを楽しんだり、生活を工夫したりしたことを想起し、まとめることができるように支援しましょう。
活動ポイント1
子供の気付きを学習につなげ、興味・関心を高める
朝の会や学習環境の場の設定
日記や朝の会、帰りの会での発表から、季節の変化への気付きを共有し、「冬の行事」に関心が向くよう働きかけます。季節の行事やお祭りの本を紹介したり、催し物について書かれた市政便りやタウン誌などの掲載部分を掲示したりしておくことも効果的です。
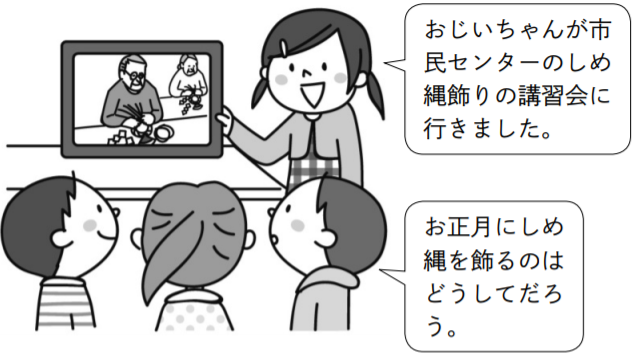
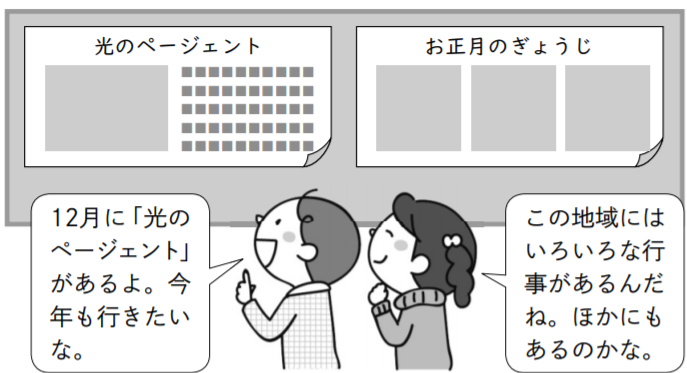
他教科・他単元との関連
イラスト/熊アート
『教育技術小一小二』2019年12月号より

