小5国語「千年の釘にいどむ」指導アイデア
教材名:「千年の釘にいどむ」 光村図書
指導事項:C「読むこと」 オ
言語活動:エ
執筆/福岡教育大学附属小倉小学校教諭・廣口知世
編集委員/文部科学省教科調査官・菊池英慈、福岡県公立小学校校長・城戸祥次
目次
単元で付けたい資質・能力
①身に付けたい資質・能力
自分の考えを広げたり深めたりするために、本を読む力を育成します。
②言語活動とその特徴
本単元では、「写真付きの本を読んで推薦の文章を書く」という、言語活動を位置付けます。これまでの読書の範囲を広げる学習においては、子供が個人で選ぶ本のジャンルは多岐にわたり、指導の収拾がつかなくなってしまったり、教材の読み取りや言語活動である書く活動に、大幅な時間をかけ過ぎたりしていました。
そのため、子供は同じジャンルの本ばかりを読んだり、教師は教材をいかに教えるかに意識が傾き、できあがった表現物の内容で読む力を評価したりする課題がありました。特に、第五学年になれば、自分の好みのジャンルが定まり、新しいジャンルの本に手を伸ばすことが少なくなります。
しかし、それでは読書の幅は広がらず、自分の考えの広がりや深まりが期待できないだけでなく、指導と評価の一体化もなされません。この機会に読書ジャンルを広げ、様々な考えに出合わせるとともに、同じ本を読んだ人でも考えが異なることを知り、自分の思いや考えを広げたり深めたりできるようにしたいものです。
本教材「千年の釘にいどむ」の特徴は、職人の生き方が伝わるように、文章に合う写真が効果的に配置されているところにあります。「本を読む」ということを、「文章を読むこと」という狭い範囲で捉えず、「文章や写真、図などを含めたテキスト自体を読むこと」と捉えると、読書の範囲が広がります。
よって、写真付きの本を読んで、推薦の文章を書くという言語活動は、本単元で育成を図る資質・能力「自分の考えを広げたり深めたりするために本を読むこと」(C読むこと オ)の育成にふさわしい言語活動であると考えます。
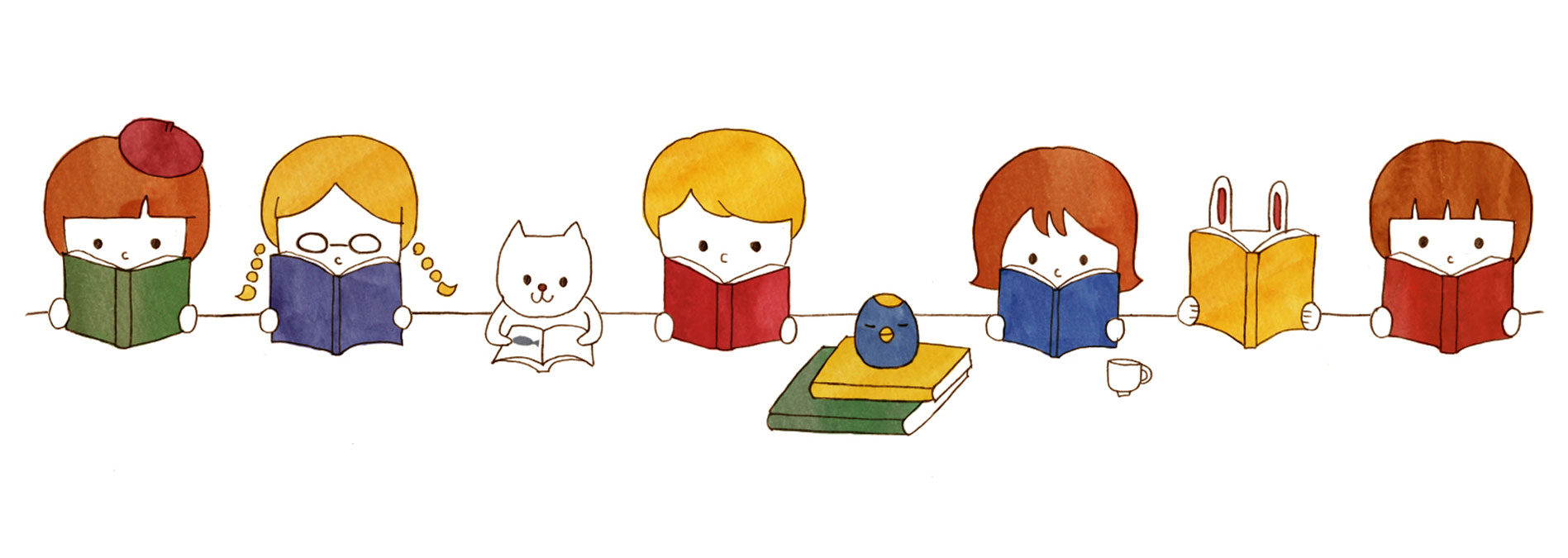
単元の展開(5時間扱い)
主な学習活動
第一次(1時)
①学級文庫の写真付きの本を読む時間を設けて、気が付いたことを出し合い、単元を設定し、学習計画を立てる。
→アイデア1 主体的な学び
【学習課題】写真付きの本を楽しもう
第二次(2~3時)
②教材「千年の釘にいどむ」を読み、心に残った言葉や写真を伝え合う。
→アイデア2 対話的な学び
③教材「千年の釘にいどむ」のよさについて話し合い、自分の考えをまとめる。
第三次(4~5時)
④学級文庫の写真付きの本を二、三人組で読み、その本のよさについて伝え合う。
→アイデア3 深い学び
⑤学級文庫の中から写真付きの本を選び、推薦の文章を書く。
アイデア1 共通の読書経験を生かした単元の設定

単元の導入ではまず、教師が準備した写真付きの本を読む時間を設け、「どの本にも写真が載っている」ことに気付けるようにします。そして、「写真付きの本を楽しもう」という単元を設定します。
読書経験は個人差が大きいと考えられますので、全ての子供が主体的に学ぶことができるように、共通の読書経験をもちます。そして、推薦の文章を書くという見通しをもちます。
主体的な学びにするためのポイントは、下図資料1のような「読書ジャーナル」を配付することです。これにより、「載っている本を全て読みたい」という読書に対する意欲が喚起されます。資料1の「読書ジャーナル」の選書は一例です。選書に当たっては、次の3つをポイントにして選ぶとよいでしょう。
- 写真が効果的に使われている本であること。
- 環境問題や食育、人物の生き方など、自分の考えが広がったり深まったりするジャンルの本であること。
- 複数冊準備できる本であること。
【資料1 読書ジャーナルの例】
イラスト/横井智美
『教育技術 小五小六』2019年6月号より

