【小1・算数「10より大きい数」】学び方を選び取る力を育てる〈デジタル×深い学び〉
紙とデジタルを行き来しながら、課題の難易度や進め方を子供自身が決めるーー。板橋区立志村第二小学校の9月の研究授業では、1年生が「自分の学び方を選ぶ」ことに挑戦しました。実践を行ったのは、1年1組の大谷かおり主任教諭[T1]と香川志保里 学力向上専門員[T2]、1年2組の野本結花教諭。さらに、昨年度まで教育庁で統括指導主事を務め、現在は東久留米市立本村小学校の副校長として授業づくりを支えている池田守先生のコメントも交えて紹介します。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の22回目です。記事一覧はこちら

東京都板橋区立志村第二小学校
学校教育目標は、「明るく思いやりのある人」「よく考える人」「たくましい人」の育成。ICTを効果的に活用しながら、子供に学びを委ねる授業デザインを全校で実践・研究しています。
目次
「学び方を選べる子」を育てる――1年生から始める学びの土台づくり
板橋区立志村第二小学校が全校でめざしている児童像は、「学び方を適切に選びながら学習を進められる児童」です。なかでも、低学年の分科会では「いろいろな学び方を知り、取り組もうとする児童」をめざしています。ここでいう「学び方」とは、課題の難易度や進め方(順番・速さ・誰と取り組むかなど)のことです。
1年生では、学習規律や教科書の読み方、発表の仕方、ノートの書き方といった学びの基本を身に付けます。そして2年生では、1年生で培った力をさらに発展させ、教師が示した方法だけでなく、自分で学び方を選んだり、友達と協働したりする経験を重ねながら、学ぶ楽しさや意欲を育てていきます。
こうした低学年での学びの積み重ねが、中学年以降の「自ら学ぶ力」を支える確かな土台となります。
「自分に合った学び方」を選び取る3つの工夫
前述の児童像を踏まえ、授業づくりの柱となっているのが「子供自身が学び方を選び、進め方を調整できる授業」です。その実現に向けて、授業は次の3つの視点から構成されています。低学年の特性を踏まえ、無理なく「自分で学びを整える力」を育てる設計です。
●授業の3つの柱
・自己決定の入り口づくり…課題の難易度・進め方、紙・デジタルの手段を選ぶ。
・現在の力の自己理解…事前アンケート等で希望と実力をすり合わせ、コースを設定。
・対話の基礎スキル…相手を見て「聞く」「うなずく」「さえぎらない」「否定しない」など、話し合いの作法を共有する。
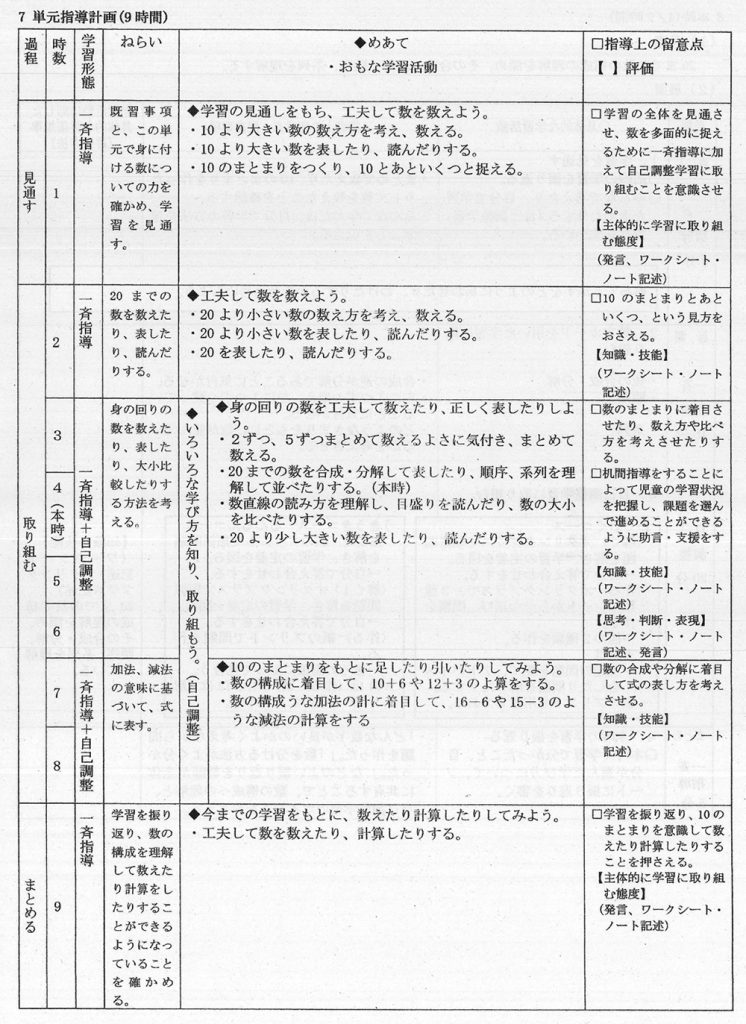
1年生では、2学期からこの考え方をもとに習熟度別学習をスタート。子供たちは、自分のペースや関わり方に合わせて3つのコースから学び方を選びます。
●3つの学びのコース
・るんるんコース…先生や友達と《ゆっくり》考えて、《るんるん》しながら学ぶコース。
・うきうきコース…先生や友達と《じっくり》考えて、《うきうき》しながら学ぶコース。
・わくわくコース…自分のやり方を考えて伝えたり、友達の方法を試したりして《わくわく》しながら学ぶコース。
「『どんなコースで学びたいですか?』というアンケートを行ったところ、1学年では、るんるんコースが13人、うきうきコースが18人、わくわくコースが29人、そして『まだ選べない』と答えた子が6人でした。想像していたよりも、子供たちは《ゆっくり、しっかり学んで、できるようになりたい》という気持ちを持っている子供が多いと感じました」と野本教諭は話します。

