【連載】坂内智之先生の 愛着に課題を抱えた子が伸びるアプローチ~学級担任にできること~#11 「体」からのアプローチ、7つのポイント ―実践編その7―
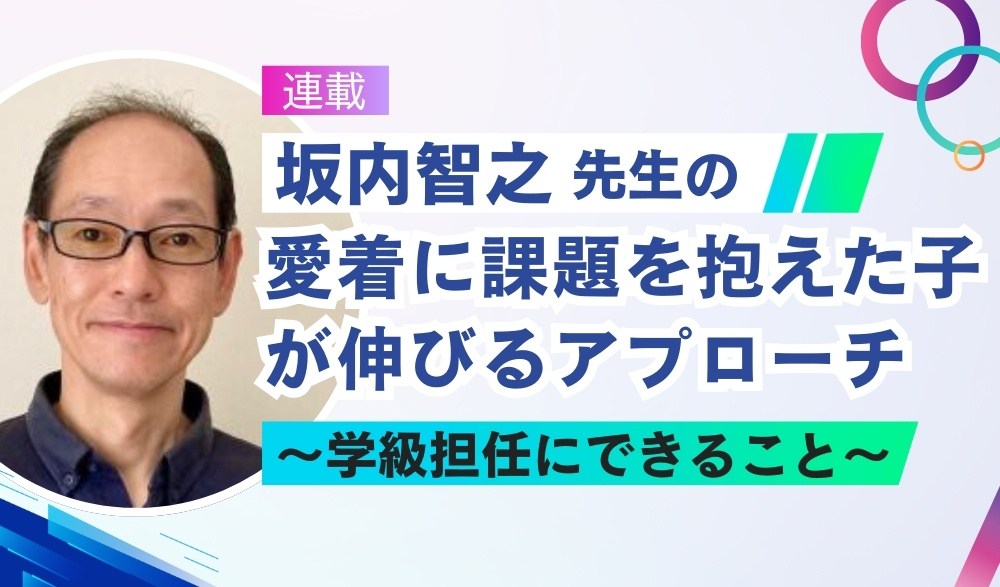
近年、教員たちが対応に苦慮し、学校現場を根底から揺るがしている「愛着障害に苦しむ子どもたち」。そうした子どもたちによって荒れた学級を何度も立て直してきた坂内先生が、今、学級担任に何ができるのかを提案し、これからの学級のあり方について考えていく連載第11回。今回は、愛着障害の子どもたちを伸ばす「体」へのアプローチを提案します。
執筆/福島県公立小学校教諭・坂内智之
目次
はじめに
学級や学校内の子どもたちを見ていると、体の様子がとても気になることがあります。筋肉がとても緊張している子ども、動きがぎこちない子ども、表情のない子ども、椅子に座れない子どもなど、「どうしたのかな?」と思うような子を見かけます。
そうした子はたいてい問題行動を起こしていたり、不登校傾向だったりすることが多く、子どもの心と体が連動していることがよく分かります。また、頭が痛い、お腹が痛いなどという身体症状も、病気だけでなく心の問題を抱える子どもに多いことは、現場の教師なら誰でも知っていることだと思います。
近年では、脳腸相関など、神経ネットワークについても研究が進み、これまでの「心→体」という一方通行の情報だけでなく、「体→心」というこれまで考えられてきたものと逆方向の情報伝達も同じくらいあることが分かってきました。つまり、体が心にも作用していると言うのです。
今回は、そんな子どもの体と心との関連に着目していきます。
「体」からのアプローチ
なぜ、子どもの体なのか。そこには自分自身の気づきがあったからです。
ちょうど20年ほど前、風邪の症状をきっかけに、そこから5年ほど大きく体調を崩したことがあります。近年よく耳にするコロナ感染の後遺症と似ていて、全身の蕁麻疹が止まらず、とにかく体がだるく、立っているだけでつらいなと思うような毎日でした。そうした症状は徐々に回復していったものの、5年ほどは運動ができる状態ではありませんでした。そこからの回復をきっかけに、ジョギングを始め、マラソンやロードバイク(自転車)にもチャレンジするようになりました。今では、学校への通勤距離が片道11kmほどありますが、年間の半分ほどは自転車で通います。ここで大きな気づきがありました。自転車で通勤していると、明らかに自分の心の状態がよいのです。朝からとてもポジティブな気持ちにあふれ、行動も素早くなります。一方で梅雨の時期や冬場など、自家用車で通勤していると、朝の気分がとても重く、苦しいのです。
そうしたことから分かってきたのは、心と体はとても密接だということです。それは以前、筋肉体操で活躍されている、順天堂大学スポーツ健康科学部教授の谷本道哉さんの講座に参加したときに、「運動は抗うつ薬と同等の効果がある」とお話しされていたことと重なります。私たちはこれまで、子どもの問題行動を心の面からばかり見つめ、心をうまく回復させれば体の状況もよくなると考えてきました。
しかし、自らの体と心の状態を見つめると、体から心へのアプローチもまた重要なのではないかと感じるのです。
私は学校現場で、体の状態を変えることで子どもたちの心によい影響を与えていくことはできないか、と考えてきました。
以下、これまでの私の取組の中から、子どもの心の状態を安定させていくための3つのアプローチ、「動作と体」「呼吸やリズムと体」「表情と体」について解説していきます。
動作と体
体の動作は心と密接に連動しています。体からのよい刺激に、心を安定させ不安を解消させる力があることは、私たち大人もよく知っています。体を伸ばしたり、深呼吸したり、マッサージを受けたりすることが、心のリフレッシュにつながっていることを感じていると思います。
これは子どもだって同じはずです。とは言え子どもですから、自分の体の状態を見つめ、それに合わせた動作をすることは難しそうです。ですから、私たち教師側から子どもたちの体に適切な刺激を入れていき、心の状態を安定させていくことが必要です。適切な刺激があると、子どもたちの表情は変わり、不安の解消、落ち着きにつながっていきます。
では、学校現場ではどんな動作を取り入れていくことが可能なのでしょうか。
ここでは3つのポイント、「遊びで体を動かす」「正しい姿勢をつくる」「お互いに触れ合う」を紹介していきます。
ポイント1「遊びで体を動かす」

坂内智之プロフィール
ばんない・ともゆき。1968年福島県生まれ。 東京学芸大学教育学部卒業。福島県公立小学校教諭。協働学習の授業実践家で「学びの共同体」から『学び合い』の授業を経て、20年以上にわたり、協働学習の授業実践を続ける。近年では「てつがく」を取り入れた授業実践を行う。 共著に『子どもの書く力が飛躍的に伸びる!学びのカリキュラム・マネジメント』(学事出版)、『放射線になんか、まけないぞ!』(太郞次郎社エディタス)がある。

