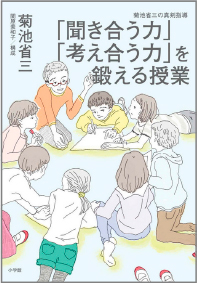<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #22 高知大学教育学部附属小学校2年B組④<後編>

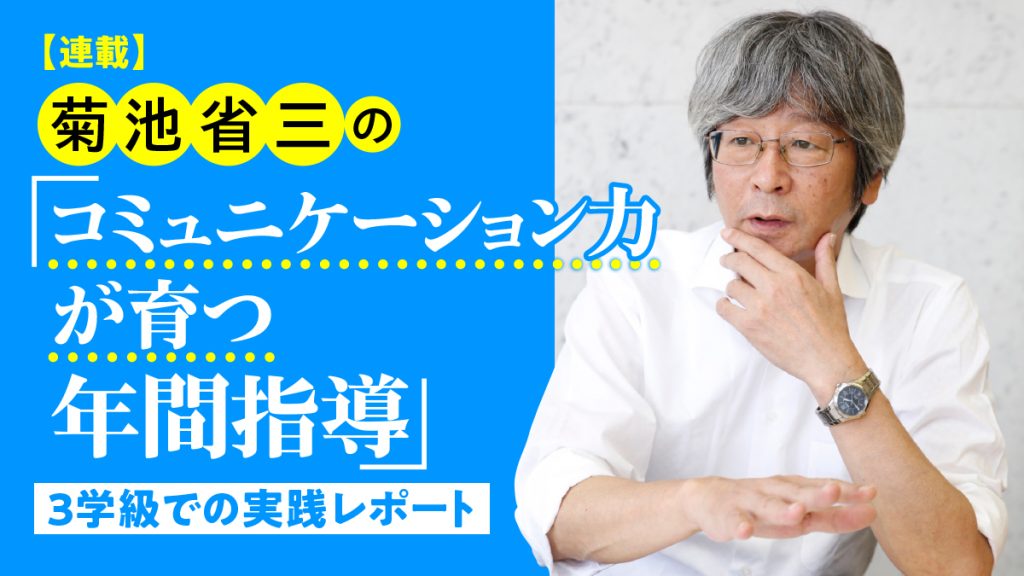
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする好評連載。今回は高知大学附属小学校の小笠原学級(2年生)における2025年2月の授業レポートの後編です。菊池先生と小笠原先生による、2時間続きの熟議の合同授業の記録です。

目次
工夫を凝らした発表に盛り上がる
残り4班の発表が続いた。
5班「ほめ言葉のシャワー・ナンバーワン」
●発表内容と発表の方法
「いいところ見つけ(ほめ言葉のシャワー)」では、その日のヒーローがみんなからいいところを見つけてほめてもらいます。最初は小笠原先生がみんなのことをほめていましたが、『私たちもできるよ』と言って、5月29日から『ほめ言葉のシャワー』を始めました」
説明の後、5班の子供たちは「ほめ言葉のシャワー」の動画を見せた。
●この活動をやってよかったこと
・自分のいいところがわかる
・言われた人はうれしくなる
・ほめ言葉をいっぱい言えるようになる
・大きな声を出せるようになる
「2Bは『ほめ言葉のシャワー』をして、いいクラスになりました。話し合いのときも、話さない人は1人もいません」と発表を締めくくった。
●他班から5班への質問・感想
感想「姿勢がよかった」
感想「聞こえやすいちょうどいい声だった」
感想「動画を見せていたのがよかった」
感想「声が大きかった」
質問「(動画は)なぜ、Aさんのいいところ見つけにしたのですか?」
5班の回答「Aさんがうれしそうだったから」
●参観者からの質問・感想
感想「発表の姿勢が素晴らしかった」
質問「ほめ言葉のシャワーの中で、自分が言われてうれしかった言葉は何ですか?」
5班の回答「サッカーを頑張ってるね」「友達思い」……などと次々に答えた。
菊池先生は、
「相手に何かを伝えるときには、3つの大切なことがあります。
一つは『口』、2つめは『眉毛』、そして3つめは『目』。中でも、『目』が一番大切です。Aさんが選ばれたのは、『目』がよかったからじゃないかと思います。
『言われてうれしかったほめ言葉は何ですか』」という(参観者からの)質問に対して、『サッカー頑張っているね』という答えがありました。自分が頑張っていることをほめ言葉で言ってもらえるのはうれしいよね。
同時に、『ほめ言葉のシャワー』では、自分が頑張っていること以外のことを言ってもらえることがあります。例えば『リーダーみたいだね』など、自分が思っていなかったことを言ってもらえるのもうれしいものです」と講評を述べた。
![]()
4月に参観したとき、Aさんは自分の世界に没頭し、授業に集中することができない場面もありました。しかし、授業を参観するごとに、Aさんが集団との関わりの中で成長していることが感じられました。周りの子供たちも、Aさんを仲間として受け入れていることがわかりました。
ほめ言葉のシャワーの動画で、Aさんがみんなからほめられた後、お礼の言葉を述べる場面では、照れくささもあったのか、早口でまくし立てる口調でした。それでも子供たちは、「Aさんがうれしそうだったから」、その場面をほめ言葉のシャワーの紹介で使ったのです。
教室が呼応できているから、Aさんも活きてくる。対話・学び合いを通して個と集団を育て、聞き合う関係になっていきます。
6班「フリートーク」
●発表内容と発表の方法
「フリートークは、テーマを決めて自由に話す、難しくて楽しいゲームです。お題(テーマ)に関わることだけしか質問してはいけません。僕たちがやってみます」
と言って、フリートークを実演した。
※まずはじゃんけんで、質問される人を決めた。
「今日のテーマは『リンゴとバナナ、どっちが好きか?』です。どっちが好きですか?」
「私はリンゴです。シャキシャキしていておいしいからです」
「ぼくはリンゴです。赤い色が好きだからです」……
実演が終わると、
「次は、みなさんが近くの人とやってみてください」と声をかけ、「リンゴとバナナ、どっちが好きか」というテーマで、全員が隣同士のフリートークを楽しんだ。6班の子供たちは最後に、
「フリートークをすると、いろいろな人と話せるようになります」と発表を締めくくった。
●他班から6班への質問・感想
感想「今やってみて、またフリートークをしたいと思った」
感想「自分たちだけじゃなく、聞いている人にもやってほしいという気持ちが伝わった」
●参観者からの感想
「ハキハキ大きい声で、こっちまで伝わってきた。近くの人とやってみるというのが、今までのグループにない発想で、みんなと話す良さが伝わってきた」
菊池先生は、
「いろいろな友達と自由に話す。楽しみながら、言葉を交わし合う――。だからみんなが仲良くなって成長し合えるんだな、と気づきました」と話した。
![]()
質問・感想のとき、小笠原先生が「言いたくて仕方ない人?」と声をかけると、多くの子が手を挙げました。担任も子供もみんなが参加者となって授業をつくり上げていました。
「今はじっくり考えるとき」「今は聞き合うとき」、そういうメリハリのある負荷を与えて、呼応する教室を育てる。
そういう場をつくるとともに、「自分もその流れに乗らなければいけない」という緊張感を持ち続ける担任の教室だからこそ、子供たちも自然に、「頑張ろう!」と意識できるのです。
7班「2つのチームでの話し合い」
●発表内容と発表の方法
「2Bでは、道徳の時間に、それぞれが○か✕かを決めて話し合ってきました」と話してから、実演スタート。
(教材『ぐみの木と小鳥』で)「小鳥のしたことはよかったのでしょうか? ○か×か」
「私は✕です。嵐の夜に行くのは危険だと思う」
「僕は○です。人を助けようとするのはいいことだと思うからです。(以前、道徳で学んだ)『七つのほし』でも、人を助けるのはいいことだと学びました」
実演後、実際の道徳の授業で、2つのチームに分かれて話し合っている動画を見せた。
「2つに分かれて話し合うことで、深く考えることができます。それに、✕の考えでなくても、✕の立場で話せる人もいます。考え方が成長できます」と発表した。
●他班から7班への質問・感想
感想「動画でわかりやすく説明していた」
感想「鼻と目と口とおへそを向けて話していた」
感想「○と×で話し合う(実演)のがよかった」
●参観者からの感想
「○と✕、2つに分かれて実演したのがわかりやすかった。『深く考えて成長する』という説明がとてもよかった」
菊池先生は、先ほどの道徳授業の動画を再び再生しながら、
「今日の発表は、みんなが台本を書いて覚えて、一生懸命練習したものです。でも、この授業での話し合いは、その場で考えて話し合っていました。
コミュニケーションには、『書いて丁寧に発表する話し合い』と、『そのときそのときに考えたことを伝える話し合い』の2つがあります。
2つに分かれた話し合いでは、書いてあることだけではなく、その場でぱっと考えて言わなければならない場面が多くなります。つまり、2つ目のコミュニケーションの力が伸びていくんですね。
この動画の話し合いでは、みんなが頭をくっつけて輪っかになっていますね。こういう状態でコミュニケーションを取ることで、深く考え合うことができ、みんなで成長し合えるんです」と説明した。
![]()
台本通りに発表するのではなく、即興力を活かすことで、動きがある発表になります。
8班「ほめ言葉のシャワー・天才」
●発表内容と発表の方法
最初に子供たちが、「ほめ言葉のシャワー」のデモンストレーションをした。
「これから、○○さんのいいところ見つけをします」
「笑顔と優しさで文句なしです」
「声が大きくて詳しいので素敵です」
「姿勢がよくて友達とも仲がいいので、完璧です」
言われた子が感想を述べた。
「みなさん、僕のいいところを見つけてくれてありがとうございます。これからも、みなさんにいろいろなことを教えたいです」
みんなが拍手をして終了。
「このように、毎日『ほめ言葉のシャワー』をしています。
(参観者に向けて)「えっ!? みなさんもやってみたくなった!?」
「そうでしょう、そうでしょう」
「今なら、なんと無料でご紹介します。お買い得ですよ」
「そうそう、お買い得……って、最初から無料です」
「えへっ」
発表者4人のボケとツッコミを入れた漫才トークに、みんなが大笑いした。
●他班から8班への質問・感想
感想「お笑いのときの笑顔で演じているのがとてもよかった」
感想「言葉がおもしろかった」
質問「なぜお笑いを入れたんですか?」
8班の回答「みんなが笑ったら、(参観者の)先生たちもやりたいと思うかな、と考えました」
●参観者からの感想
「『ほめ言葉のシャワー』の実演で、発言を終えた2人が、次の友達のことを見ていたのもとてもよかった」
菊池先生は、
「以前、受け持っていた学級の子供たちと『ユーモアはコミュニケーションのホームラン』という言葉を考えたことがあります。発表の中心にユーモアを持ってきたのがさすがだと思いました」とほめた。
いよいよ審査結果発表!! 最優秀賞は……
全チームが発表を終えると、菊池先生を含めた授業参観者たちが審査。子供たちも話し合いながら、自分たち以外のよかったチーム(班)を選んだ。
そしていよいよ、授業参観者が選んだ賞と、最優秀賞の発表。
●みんなが選んだ「子供賞」……8班
●ほっこり平和賞……1班
「あふれさせたい言葉をみんなに広げたい、という言葉がよかった」
●笑わせてくれたで賞……8班。
「楽しそうに演じていて、教室みんなが笑顔になった」
●ユーモアあふれていたで賞……2班
「ユーモアあふれるゲームを通して、みんなが仲良くなれた」
●即興力アップで賞……7班
「即興的な会話によって、いろいろな力をパパッと発揮できる力がつくことが伝わってきた」
●言われてうれしいで賞……5班
「ほめ言葉を言われてうれしくなると、もっとやりたいと感じ、成長につながる」
●みんなとたくさん話せるで賞……6班
「いろんなテーマで話せるのがいい」
●頑張って2Bを支えたで賞……4班
「いろいろな係活動でみんなを支えてくれた」
●次につながる成長で賞……3班
「『私たちにとって大事』という言葉がググッときた」
そして、最優秀賞には、「係活動」について発表した4班が選ばれた。
小笠原先生が、「1位になれないことでがっかりする子もいるかな、と思ったけれど、みんなが笑顔で拍手し合っていました。今日に向けてみんなが頑張ってきたことを、先生は知っています。だから、1位になれなくてもいいんです。どの班もめちゃくちゃよかったです。みんなの成長を祝ってみんなで拍手しましょう」と話すと、菊池先生が、
「みんなで2Bを成長させたので、みんなで拍手をしましょう!」と続け、子供たちは大きな拍手を送り合った。
菊池省三先生による授業解説
きちんと立って発表する、隣の人と相談する、班を作って話し合う、みんなの前で話す、前に出て書く……そうした経験を通して、学級全員ができるようになっていきます。
こうした一つひとつの活動の意味を、個人だけでなく、学級全体の成長としても位置づけ、全員で体験することがとても大切です。
一人ひとりの小さな成長のストーリーを見つけて活かすプロデュース。その成長を学級全体の成長という大きなストーリーにつなげていくマネジメント。教師は、この2つの役割を意識することが重要です。
「Aさんはこういうところが素敵だね」という小さなストーリーを、「あなたの良さが、このクラスを明るくしてくれているね」と価値づけて、個々にフィードバックしていくのです。
どの子も、学びの中で、“突き抜けてくる” 場面があります。それを見つけてプロデュースし、全体に広げるマネジメントするタイミングを見極めるためには、常に子供たちの姿にアンテナを張っておくことが必要です。
教師はついプロデュースに重点を置きがちですが、全体に広げるマネジメントも同じくらい大切だということを意識しましょう。
頑張っている最中の子供たちは必死で、自分の成長を客観視することができません。成長ノートで振り返り、教師が価値づけをしていくことで、子供たちは少しずつ、現在と過去を比較できるようになり、未来への目標を明確に持てるようになっていきます。
そのような視点で見ると、「成長を祝う会」は単なる発表会ではなく、自分を振り返り、省みて、自分に必要な成長を見つけていく重要な機会です。だからこそ、儀式的な重い意味をもつのです。
コミュニケーションあふれる温かい学級づくりの柱となる、「ほめ言葉のシャワー」や「成長ノート」。授業で話し合いを活発にする「分裂する問い」。こうした柱の土台となる係活動や学習ゲーム。
今回の「成長を祝う会」は、子供たちが1年間を通して経験した学びに沿った発表内容となりました。
今回、参観者の皆さんには、子供たちの発表を、「自分自身が取り入れてみたいか」という視点を持って聞いてもらいました。子供たちの発表の中に、「全国の学校でも取り入れてほしい」という発言が多くありました。参観者に向けて発表することで、単なる活動内容の説明だけでなく、「全国にも広げたい」という意識を持ったのです。
コミュニケーションの学びを体験し、発表することで客観的に振り返る。さらにその学びを実感したからこそ周りに広げていきたいと自信を持って発信する。
これこそが、教室から飛び出し、“社会化” する学びといえるでしょう。「コミュニケーション“を”学ぶ」ことから、「コミュニケーション“で”学ぶ」集大成の発表会となったのです。

菊池先生の最新刊、今までにない提案性を孕んで発売中!
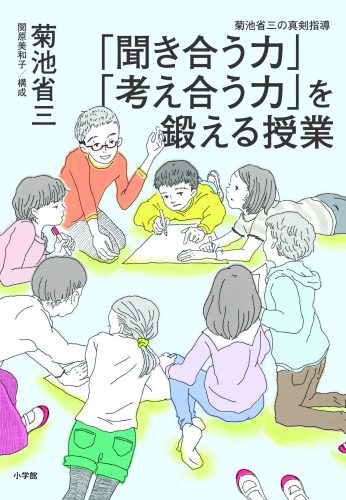
2025年3月22日のリアル対面セミナーの記録動画(有料)を公開中です!
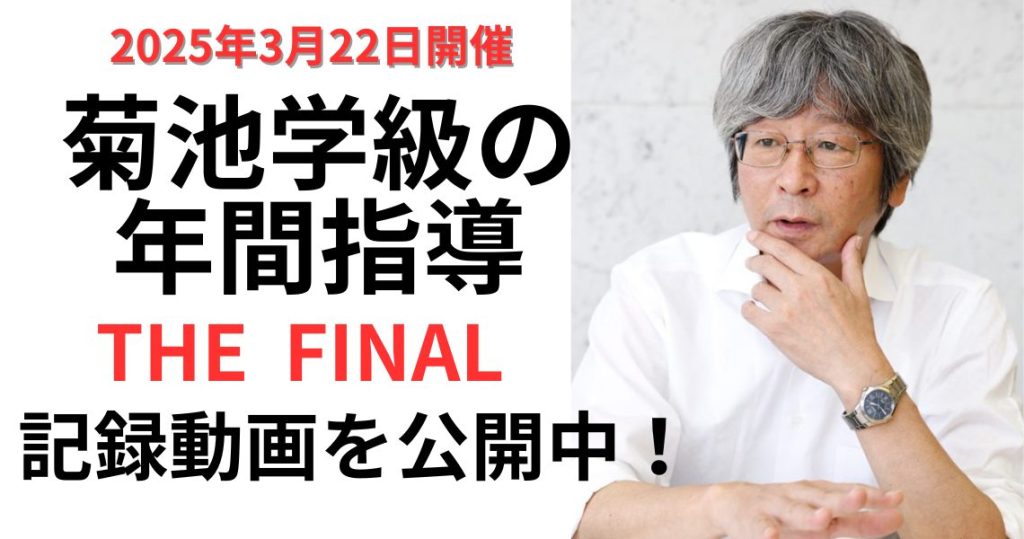
↓2025年3月発売の最新刊
「聞き合う力」「考え合う力」を鍛える授業
好評発売中です!
↓若手が菊池実践を学ぶために最適の単行本
「一人も見捨てない!菊池学級 12か月の言葉かけ」 発売中です!
取材・文/関原美和子

Profile
きくち・しょうぞう。1959年愛媛県生まれ。北九州市の小学校教諭として崩壊した学級を20数年で次々と立て直し、その実践が注目を集める。2012年にはNHK『プロフェッショナル仕事の流儀』に出演、大反響を呼ぶ。教育実践サークル「菊池道場」主宰。『菊池先生の「ことばシャワー」の奇跡 生きる力がつく授業』(講談社)、『一人も見捨てない!菊池学級 12か月の言葉かけ コミュニケーション力を育てる指導ステップ』(小学館)他著書多数。